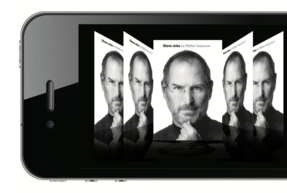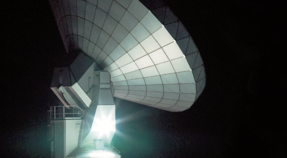-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
スティーブ・ジョブズの教え
スティーブ・ジョブズの伝説。それは、起業家精神から生み出された創造性を超越し、神話となった。
1976年、ジョブズは実家のガレージを拠点に、アップルを共同創業した。85年、そのアップルを追放されるも、97年には、破産の一歩手前で復帰し、立て直した。2011年10月に死去した時点では、アップルを時価総額で世界一の座に導いていた。
この過程で、パーソナル・コンピューティング、アニメーション映画、音楽、電話、タブレット・コンピューティング、小売り、デジタル・パブリッシングという7つの業界で、変革を成し遂げた。
これにより、トーマス・エジソン、ヘンリー・フォード、ウォルト・ディズニーらと並び、アメリカを代表する、偉大なる革新者としての名声をほしいままにしている。ここに名前を挙げた人々は、だれ一人として聖人ではない。しかし、創意を基にテクノロジーと事業を発展させたその功績は、人物像が忘れ去られた後も、末永く歴史に刻まれるだろう。
私がジョブズの伝記を上梓した後、たくさんの人が、マネジメント上の教訓を引き出そうとしてきた。なかには示唆に富んだ指摘もあるが、多くの読者、特に起業経験のない読者は、ジョブズの性格の荒っぽさに気を取られすぎているようだ。
私が見たところ、ジョブズのビジネス流儀は、彼の性格と切り離せないものであり、これこそが彼の本質だった。彼は常識にとらわれないよう行動し、製品をつくる際にも、日頃から抱えている情熱や激しさ、強烈な思いをぶつけていた。およそ寛容とはいえず、カンシャク玉を破裂させていたが、これもまた完璧主義の表れだった。
ジョブズの伝記をおおむね書き上げた後、私は、永遠の別れの前に、何度か彼と会った。ある時、他人に手荒く接する気質について、あらためて尋ねてみたことがある。そうすると、こんな言葉が返ってきた。
「これまでの結果を見てください。私と一緒に仕事をした人たちは、逸材ぞろいです。他社でも第一線の仕事を与えられるはずの人材です。『不当な扱いを受けている』と心底思ったのなら、移籍していたのではないですか。けれども彼らはそうしなかった」
それから、しばしの沈黙の後、まだ言い足りなさそうに、こう言った。「私たちは、素晴らしいことを成し遂げました」
実際に、ジョブズとアップルはここ十数年で、今日存在している他の革新的といわれる企業と比べても、はるかに大きな成功を収めてきた。〈iMac〉〈iPod〉〈iPod nano〉〈MacBook〉〈iPhone〉〈iPad〉〈OS X Lion〉〈iTunes Store〉、そしてアップルストアである。また、ジョブズと縁の深いピクサー・アニメーション・スタジオも、素晴らしい作品ばかりを世に出してきた。
晩年は、死の病と闘ったジョブズの傍らに、長年にわたり彼の薫陶を受けた、忠誠心が厚い多くの同僚と、愛情あふれる妻、妹、4人の子どもたちが寄り添っていた。
以上のことから、スティーブ・ジョブズの本当の教えを引き出すには、彼が実際に残した功績に着目する必要がある、と私は考えている。
かつて本人に、「ご自身の最も重要な創造成果は何だと思いますか」と聞いたことがある。〈iPad〉か〈Macintosh〉という答えを想定していたのだが、返ってきた答えは、アップル、だった。
永続的な企業を生み出すほうが、偉大なる製品を創造するよりもはるかに難しく、はるかに重い意味を持つ。彼がそれを、どうやって成し遂げたのかは、今後100年にわたり、ビジネス・スクールの研究対象であり続けるだろう。
それでは、ジョブズの成功のカギは何なのか、以下で私なりの考えを述べたい。
[01]フォーカスする
97年にジョブズが復帰した時、アップルは、一貫した方針がないまま、種々雑多とコンピュータや周辺機器を製造していた。当時は、〈Macintosh〉だけで10種類もあった。
「やめだ! 馬鹿げている」。何週間かに及んだ製品レビューの後、ついに、彼の堪忍袋の緒が切れた。
ペンをつかみ、素足でホワイトボードに歩み寄った。そして、4マスから成るマトリックスを描き、「必要なのはこれだ」と言い放った。
横軸に「消費者」と「プロフェッショナル」、縦軸には「デスクトップ」「ポータブル」と書いた。その4マスそれぞれに対応した、素晴らしい製品づくりにフォーカスすることが君らの仕事だ、と部下たちに説いた。そして、それ以外の製品はすべて撤退すべきだとも言い放った。
その場のだれもが言葉を失った。けれどもジョブズは、機種を4つに絞ることによって、アップルを救ったのだった。「『何をしないか』を決めるのは、『何をするか』を決めるのと同じくらい大切なのです」と彼は私に語ってくれた。「これは、企業と製品の両方に当てはまります」
アップルの業績を、回復へと導いた後、「トップ100」と呼ばれる幹部100人を率いて、合宿をすることを毎年の恒例行事にしていた。
その最終日は、ジョブズがホワイトボード(ホワイトボードは、状況を掌握し、焦点を絞るのに役立つため、彼の愛用品だった)を背にして、「次にやるべきことを10挙げるとすれば何か?」と参加者全員に問いかけることになっていた。
そこでは、参加者たちが争うようにして、自分の意見を取り上げてもらおうとしていた。ジョブズは各人の意見を書き出し、「ダメだ」と思うものに斜線を引いていった。あれこれ入れ替えを行った末に10項目のリストが完成した。するとジョブズは、下から7つを消して、「実現できるのは3つだけだ」と宣言する。
「フォーカス」は、ジョブズの性格に染みついており、禅の影響でいっそう研ぎ澄まされていった。ジョブズはじゃまとか余計だとか思われるものは、容赦なく切り捨てた。
同僚や家族は時々、法律問題や健康診断など、彼にとって大事だと思われる事柄を、対処させようとして説得した。しかし、当人は冷めた視線を相手に向けるだけで、自分の心積もりができるまでは、ごく限られた対象から頑として関心を逸らさなかった。
死を間近に控えた時期、ラリー・ペイジがジョブズを訪問した。ペイジは当時、みずから共同創業したグーグルの実権を再び握ろうとしていた。グーグルは、アップルの競争相手であるにもかかわらず、ジョブズはペイジに助言を惜しまなかった。
その時のことを、ペイジはこう振り返っている。「主に強調して話していたのは、フォーカスすることについてでした」
ペイジによると、事業を拡大させた後のグーグルの望ましい姿とは何か、それを探りなさい、と語ったという。
「いまはあれもこれもと手がけているが、重視しているサービスを5つ挙げるとしたら、それは何かと考えることだ。そして、それ以外は足を引っ張るだけだから、打ち切るべきだよ。このままだとマイクロソフトのように、可もなく不可もないサービスを生み出す状況になる」
ペイジはこの助言に従って、2012年1月、社内に向けて、〈Android〉や〈Google+〉など、優先すべき少数のサービスだけにフォーカスするように、さらに、ジョブズがやっていたように、「美しさ」にこだわるように、と伝えたのだった。
[02]シンプルに
ジョブズは、禅の精神に似た集中力に加えて、直観力も従えていた。本質だけに注目し、不必要な部分を削ぎ落とすことによって、物事をシンプルに見る能力である。
アップルが最初に作成したマーケティング用のパンフレットには、「シンプリシティは究極の洗練である」と謳っている。その意味を知るには、アップル製ソフトウエアを、たとえばマイクロソフトの〈Word〉と比べるとよい。〈Word〉は、直観では理解できないナビゲーション・リボンや、わずらわしい機能を雑然と詰め込むことによって、見苦しさを増す一方だ。これを見ると、アップルが追求するシンプリシティの素晴らしさが思い起こされる。
ジョブズは大学を中退した後、アタリで夜勤務をしていた。その時に、シンプリシティを尊ぶようになったようだ。アタリ製のゲームには、操作マニュアルがついておらず、酒に酔ったゲーム初心者でも理解ができるくらい簡潔にできていた。たとえば、ゲーム〈スター・トレック〉の操作案内は、「(1)25セント硬貨を投入します。(2)クリンゴン(宇宙人)から逃げてください」だけだった。
シンプルなデザインを好む傾向は、70年代末に、アスペン研究所の設計カンファレンスに参加した時に磨きがかかった。開催場所のキャンパスは、すっきりした輪郭と機能的なデザインを重視した合理的な設計思想により貫かれていて、余計な装飾や気を散らすものは何もなかった。
ゼロックスのパロアルト研究所を訪れて、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)とマウスを用いたコンピュータの構想を目の当たりにした時は、もっと直観的に使える、もっとシンプルな設計を考案しようと腰を上げた(直観的に使える機能の具体例として、配下のチームは、仮想デスクトップ上でのドラッグ・アンド・ドロップ操作による文書やファイルの移動を実現していた)。
たとえば、ゼロックスのマウスは、3つもボタンがついていて、そのコストが300ドルだった時、ジョブズは、地元の工業デザイン会社を訪れていた。創業者の一人ディーン・ハビーに、15ドルのコストで、ボタン1つのシンプルなマウスをつくるよう要請し、ハビーはそれに従った。
ジョブズは、複雑なものを無視するのではなく、克服することで、シンプリシティを実現しようとしていた。シンプリシティを極めれば、利用者の前に立ち尽くすのではなく、親しげに寄り添うような形のコンピュータができあがるだろう、と気づいていたのだ。「何かをシンプルにすることは、大変骨が折れる仕事です。根本的な問題を徹底的に突き詰めて、洗練された解決策を見つけ出すことなのです」
ジョブズがアップルの工業デザイナー、ジョナサン・アイブと出会った時、「上辺だけではない究極のシンプリシティを一緒に追求する同志を得た」と感じたという。2人は、シンプリシティの追求は、必要最小限で済ませるだけでも、じゃまなものを取り除くだけでもない、もっと違ったものだと心得ていた。
ネジ、ボタン、余計なナビゲーション・ウインドーを省くには、おのおのの役割を深く理解する必要があるのだ。アイブによる説明はこうである。「シンプルを極めるには、とことんまで突き詰めなくてはいけません。たとえば、製品からネジをなくそうとすると、恐ろしく込み入ったものになりかねません。シンプリシティを突き詰めていくためには、まずは製品のあらゆる側面と製造方法を理解することが、いちばん大事なことです」
〈iPod〉のインターフェース設計を行っていた時期、ジョブズは会議のたびに、余計なものを取り除く方法を探そうとした。そして、どの要求にも、3回のクリック操作で済むよう強調していた。
たとえば、楽曲を検索する画面で、「曲名、アルバム名、アーティスト名のどれで行うか」を利用者に尋ねるナビゲーション・ウインドーを入れていたが、ジョブズは「なぜ必要なのか」と詰問したため、設計者は、そのウインドーはなくてもかまわないことに気づいたのだ。
〈iPod〉開発チームを率いたトニー・ファデルは、こう述べている。「僕らがユーザー・インターフェース絡みの問題に頭を悩ませていると、スティーブから何度も、思いもかけない発想が持ち上がりました。みんな意表を突かれましたよ。問題や手法を新しい切り口からとらえ、そのおかげで僕らの些細な悩みは解決したのです」
ある時ジョブズは、極めつけのシンプルな提案をした。電源スイッチをなくそうというのだ。チーム・メンバーは当初、キツネにつままれたような気分になったが、やがて、電源スイッチは不要だと理解することになる。デバイスが使われず、そのままの状態ならば、少しずつパワーを落とし、利用者が再び操作しようとしたら、パワー全開の状態に戻せばよいからだ。
〈iDVD〉をめぐっても似たような逸話がある。動画DVDを作成する際のナビゲーション・ウインドーが雑然としていた。それを見せられたジョブズは、すくっと立ち上がると、ホワイトボードに簡単な長方形を描いた。「新しいアプリケーションを想定しよう。ウインドーは1つだけ。DVDに焼きたい動画をドラッグし、『作成』ボタンをクリックすれば終わり。こういうものをつくるんだ」
ジョブズは、混乱気味の業界や、製品カテゴリーに存在する、複雑でわかりにくい製品をつくる会社を、いつもアンテナを高くして探していた。
2001年、ポータブル音楽プレーヤーと楽曲ダウンロードがその条件に当てはまり、この気づきが〈iPod〉と〈iTunes Store〉の誕生につながった。
そして、次の標的は携帯電話だった。ジョブズは会議の席上で携帯電話を手に取り、アドレス帳など便利な機能と呼ばれるものの半分は、だれも使い方を知らないと毒づいた(もっともな指摘である)。死の間際には、テレビ産業に狙いを定めていた。シンプルな機器にして、好きな時に好きな番組を見られるようにとの構想だった。
[03]全体に責任を負う
ジョブズは、ハードウエアやソフトウエア、そして周辺機器が快適に連動するよう気を配ることが、シンプリシティを実現する最善の方法だと知っていた。
〈iPod〉を〈Mac〉につないで〈iTunes〉ソフトウエアを使うというように、アップル製品だけで統一すると、機器がよりシンプルになり、スムーズに同期ができて、不調は生じにくくなるだろう。新しい曲目(プレイ)リストを作成するような、やや複雑な作業は、コンピュータでやればよいだろうから、〈iPod〉の機能とボタンは減らせるはずだ、と。
ジョブズとアップルは、他の企業ではあまり行ってはいないが、すべての顧客経験(ユーザー・エクスペリエンス)に責任を持つ姿勢を取っていた。〈iPhone〉に搭載されているARMマイクロプロセッサーの性能から、アップルストアでの購買に至るまで、顧客経験のあらゆる側面をしっかりつなぎ合わせたのだ。
80年代のマイクロソフトや、ここ数年のグーグルは、もっとオープンに方針を掲げ、OS(オペレーティング・システム)とアプリケーション・ソフトをさまざまなハードウエア・メーカーに開放してきた。実は、こちらのビジネスモデルのほうが優位な場合もあると判明している。
それにもかかわらずジョブズは、「そんなことをすれば『いい加減な製品』(crappier product:これは彼の専門用語である)しかできない」と信じていた。「人は忙しいのです。コンピュータと他の機器をどうつなごうかと頭をひねるよりも、もっとほかにすることがあるでしょう」
機器類とソフトウエアすべてに責任を持つことに対する激しい執着は、一つには、物事を支配しようとする性格によるもので、完璧さを追求し、洗練された製品を生み出そうとする情熱にも突き動かされていたのだろう。
ジョブズは、アップル製の素晴らしいソフトウエアが、創造性に乏しい他社製ハードウエア上で動くことを想像すると、いても立ってもいられなかった。非の打ちどころのないアップル製ハードウエアが、非公認のアプリケーションやコンテンツで汚されることを考えると、激しい拒否反応が起きた。
この姿勢は、目先の利益の最大化には、必ずしもつながらなかったが、ガラクタのような機器、意味不明なエラー・メッセージ、うっとうしいインターフェースがあふれるなかで、快適なユーザー・インタフェースを特徴とする驚異の製品群を誕生させた。
アップルの世界にいると、ジョブズが愛した京都の禅庭を散策する時のように清々しい気分になる。どちらも、オープン化を崇拝したり、多数の花を咲かせたりすることによって生み出されたのではない。時には、支配欲の強い人物の掌の上にいるのも悪くないのかもしれない。
[04]後れたら巻き返す
新しいアイデアを真っ先に思いつくだけが、革新的な企業の持ち味ではない。後れを取った場合に、一気に挽回する方法も知っていることもそうだ。
初代〈iMac〉を開発した時、ジョブズは、写真や動画の管理を容易にすることを重視していたが、音楽への対応は後手に回った。〈ウィンドウズ〉マシン上では、楽曲のダウンロードや共有、CDの作成が行われていたが、〈iMac〉ではCDの作成はできなかった。「間抜けを恥じました。機会を逃したとね」
しかし彼は、〈iMac〉のCDドライブを改良し、後れを取り戻しただけでは飽き足らず、音楽産業を革新へと導くような統合システムを生み出そうと決意していた。こうして、〈iTunes〉〈iTunes Store〉〈iPod〉の組み合わせにより、他のどの機器よりも、楽曲の購入、共有、管理、保存、再生に適したものができあがった。
〈iPod〉が大ヒットしても、ジョブズは喜びをじっくり噛みしめるどころか、「〈iPod〉を脅かすのは何だろうか」と気を揉み始めた。携帯電話に音楽プレーヤーが搭載される可能性が考えられた。そこで、〈iPod〉の売上げを共食いするのを覚悟で〈iPhone〉の開発に乗り出した。「みずから共食いしなければ、他社にしてやられるかもしれない」
[05]利益よりも製品を優先する
80年代初めに、数人の仲間と初代〈Macintosh〉を開発した時、ジョブズの至上命題は「とんでもなく凄い」ものをつくることだった。利益の最大化にも、コストのトレードオフにも、いっさい言及しなかった。初代のチーム・リーダーには「価格については悩まなくていい。コンピュータの性能仕様だけをまとめてくれ」と告げていた。
開発チームとの初回の合宿では、冒頭で、ホワイトボードに「妥協はしない」というスローガンを書き出した。しかし、完成した製品はコストが高くつきすぎ、それがジョブズがアップルを追放されるきっかけとなった。
同時にこの製品は、家庭向けコンピュータ分野の革命を加速させるきっかけにもなった。「世のなかに多大な影響を及ぼした」(ジョブズの言葉)のである。しかも、長い目で見れば帳尻が合った。偉大な製品をつくることに注力すれば、利益は後から着いてくるのである。
83年から93年まで、アップルの経営を舵取りしたジョン・スカリーは、ペプシコでマーケティング・セールス分野の幹部を務めた人物である。彼はジョブズが去った後、製品デザインよりも利益の最大化を重視し、アップルの業績を次第に悪化させてしまった。
ジョブズは、「企業はなぜ凋落するのか。これについては、私なりの理由があります」と語っていた。素晴らしい製品ができあがると、今度は利益を増やすために、セールスやマーケティング畑の人材が、社内で幅を利かせるというのである。「セールス畑の出身者が経営の実権を握ると、製品の専門家は出る幕が減って嫌気が差してしまいます。スカリーが入ってきた後のアップルもしかり。これは私の失策です。マイクロソフトでも、スティーブ・バルマーがCEOになると、同じことが起きました」
アップルの経営者として返り咲いた時、ジョブズは革新的な製品づくりに重点を引き戻した。光り輝く〈iMac〉〈Power Book〉、次いで〈iPod〉〈iPhone〉、さらには〈iPad〉を世に出した。本人の説明はこうである。
「私は、『偉大な製品をつくろう』と意気込む人たちが集まる、永続する企業を築くことに情熱を傾けてきました。これ以外は副次的なものでした。もちろん、利益が上がれば素晴らしいですよ。利益があってこそ偉大な製品をつくれるわけですから。ですが、動機はあくまでも製品であって、利益ではありません。スカリーは優先順位を逆さまにして、金儲けを目的に据えてしまいました。些細な違いですが、これによってすべてが決まってしまいます。どういう人材を雇うか、だれを昇進させるか、会議で何を話し合うかなど、すべてが、これによって決まってしまうのです」
[06]フォーカス・グループの言いなりにならない
ジョブズが初代〈Macintosh〉開発チームと最初の合宿を行った際に、あるメンバーから、顧客の要望を探るために市場調査をすべきかどうかと質問が出た。ジョブズは「いいや。実物を見せられるまでは、顧客は自分の望みがわからないはずだ」と答え、ヘンリー・フォードの「顧客に何がお望みかと尋ねたなら、『もっと速く走れる馬』という答えが返ってきただろう」という言葉を引用した。
顧客の欲求(ウオンツ)を深く気にかけるのは、相手にしきりに要望を尋ねるのとはまったくわけが違う。明確になっていない望みを察知する直観や本能が求められるのだ。ジョブズの言葉を借りるなら、「いまだページ上に書かれていない内容を読み取るのが、我々の役目です」ということになる。
彼は市場調査に頼る代わりに、自分なりの共感力、つまり、顧客の望みを読み取る深い直観を磨き上げた。直観を重んじるようになったのは、大学を中退してインドで仏教を学んでいた時であり、ここでの直観は、経験により蓄積された知恵に基づいている。「インドの田舎で暮らす人々は、私たちとは違い、知性ではなく直観を活かすのです。直観の威力はとても大きく、思うに、知性をも凌ぐのではないでしょうか」
これは時には、一人だけのフォーカス・グループ、すなわち自分自身の意見だけを頼ることを意味した。自分や友人がほしいと思う製品をつくったのである。
たとえば、2000年には、数多くのポータブル・プレーヤーが市場に出回っていたが、ジョブズはどれも中途半端だと感じていた。熱烈な音楽ファンでもある彼は、1000曲を保存してポケットに入れて持ち運べる、シンプルな機器を求めていた。「〈iPod〉は自分たちのために開発しました。自分、親友、家族のために何かをしていれば、手間を惜しんで質の悪いものをつくったりはしませんよね」
[07]現実を歪曲する
ジョブズは、不可能と思われる挑戦を、他人に実現できると吹き込んでしまう能力で、(悪)名高い。映画『スター・トレック』で異星人たちが、精神力だけで現実を歪曲してそれを周囲に受け入れさせてしまう力にちなみ、同僚たちから、「現実歪曲フィールド」と名づけられた。
ジョブズが若い頃だが、アタリで夜勤をしていた時に、後にアップルの共同創業者となるスティーブ・ウォズニアックに〈ブレイクアウト〉というゲームをつくるよう説得したエピソードがある。ウォズニアックは「何カ月もかかる」と抵抗したが、ジョブズは彼をじっと見つめ、「4日でできるはずだ」ときっぱり告げた。ウォズニアックは「不可能だ」と思いながらも、結局は言われるままに完成させた。
ジョブズを知らない人は、現実歪曲フィールドのことを、脅しや嘘を婉曲に表したものだと解釈したが、当人と一緒に働いた人は、自分たちは彼のこの能力に動かされて、時にはカッとしながらも、途轍もない成果を上げたのだと認めている。
ジョブズは、世のなかの一般ルールは自分には当てはまらないと考えていたために、経営資源ではゼロックスやIBMの足下にも及ばないにもかかわらず、「コンピュータの歴史を変えてやろう」と部下たちを奮起させることができた。
初代〈Macintosh〉チームのメンバーで、「今年だれよりもよくジョブズと張り合った従業員」に選ばれた経験を持つデビ・コールマンは、こう回想する。「あの歪曲はおのずと現実になるようにできていたのです。不可能を可能にしてしまうのは、不可能だと知らないからです」
ある日ジョブズは、〈Macintosh〉のOS担当技術者ラリー・ケンヨンの仕事場にズカズカと入り込み、「起動に時間がかかりすぎる」と文句を言った。起動時間の短縮ができない理由を語り始めたケンヨンをさえぎり、「もし人命がかかっていたら、起動時間を10秒縮める方法を見つけられるか?」とまくし立てた。
「多分できるでしょう」とケンヨンは言うと、ジョブズはホワイトボードに歩み寄り、仮に500万人が〈Macintosh〉を使っていて、起動に毎日10秒余計にかかっていたら、年間で総計およそ3億時間、つまり、少なくとも100人分の寿命を超える時間が無駄になっていると説明した。数週間後、起動時間は28秒も短縮されていた。
ジョブズは〈iPhone〉の構想をまとめながら、タッチ・パネルの素材をプラスチックではなく、傷のつきにくいガラスにしたいと考えていた。コーニングのウェンデル・ウィークス会長兼CEOによると、60年代に考案した化学交換法を基に、コーニングでは、〈ゴリラ・ガラス〉という愛称の強化ガラスを開発したのだという。
それを聞いてジョブズは、6カ月以内に、〈ゴリラ・ガラス〉を大量に納入してほしいと伝えた。ウィークスは、「もう製造はしていないし、その能力もない」と答えると、「ご心配なく」という言葉が返ってきた。ジョブズの現実歪曲フィールドに馴染みのないウィークスはたじろぎ、根拠のない自信を抱いても、技術上の課題は克服できないと説明を試みたが、ジョブズは過去に何度もそのような前提をはねつけていたため、「できますよ。わかってください。できるのですから」と少しも動じずにウィークスを見つめた。
ウィークスは、愕然として首を左右に振ったが、とうとう、液晶ディスプレーを製造するケンタッキー州ハロッズバーグの工場長に電話をかけ、「すぐさま全稼働を〈ゴリラ・ガラス〉の製造に振り向けるように」と命じたのだった。「6カ月かからずに納入しました。最高の科学者と技術者を動員して、要望に応えたのです」
こうして、〈iPhone〉と〈iPad〉のガラスはすべて、アメリカ国内のコーニングによって、製造されている。
[08]シグナルを込める
ジョブズは79年に、起業当初の相談相手マイク・マークラから、以下の3原則を守るようにと、強く懇望されたメモを渡された。その最初の2つは「共感」と「フォーカス」で、3つ目は「シグナルを込める」というしっくりとこないものだったが、これはジョブズの大切な信条となった。
彼は、製品や企業の印象は、パッケージや見せ方によって形づくられると知っていたのである。「マークラは、人は表紙を基に本を品定めする、ということを教えてくれたのです」
〈Macintosh〉の出荷準備をしていた84年、ジョブズは箱の色やデザインをどうしようかと、しきりに悩んでいた。同じように、〈iPod〉と〈iPhone〉を収める宝石箱のようなパッケージも、みずから多大な時間を費やして何度もデザインし直し、自分の名前で特許を申請した。
ジョブズと前出のジョナサン・アイブは、パッケージを開ける瞬間のことを、美しい製品が登場する芝居が幕を開けるような儀式だと考えていた。「〈iPhone〉や〈iPad〉の箱を開けながら、製品の感触をつかんでいただければ、と思うのです」
時にジョブズは、機能を実現するだけでなく、シグナルを送るために、製品デザインを活かした。一例として、アップルに復帰して遊び心のある新製品〈iMac〉を開発していた時期、ジョブズはアイブから、筐体上部をくぼませて、目立たないように小さな取っ手をつけたデザインを見せられた。
この取っ手は実用向けというより、装飾的な意味合いを持っていた。デスクトップ・コンピュータなのだから、持ち運ぶ人は少ないはずだ。しかし、ジョブズとアイブは、コンピュータに怖じ気づく人が、当時はまだ多いことに気づいていた。
取っ手があれば、親しみやすく、使い手への敬意や、「お役に立ちますよ」とでも言いたげな雰囲気が醸し出されるだろう。また、取っ手によって、〈iMac〉にさわってもよいというシグナルにもなった。製造チームは「取っ手をつけるとコストがかさむ」と反対したが、ジョブズは「やるのだ」とだけ告げ、理由を説明しようとさえしなかった。
[09]完璧を求める
ジョブズは、製品開発のどこかの時点で、「一時停止ボタンを押して」、初めの計画段階に立ち返って考えることが多かった。それが完璧ではないと感じた時だ。
映画『トイ・ストーリー』の製作時でさえ例外ではなかった。この作品は、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズが映画化の権利を買い取り、ジェフリー・カッツェンバーグ率いるディズニーのチームが、ピクサーの担当者に、悪者が登場するトゲのある作品にするよう強く迫っていた。ジョブズは、ジョン・ラセター監督と力を合わせて製作を中断へと持ち込み、親しみやすいストーリーに書き換えた。
また、アップルストアを開店しようとしていた時、ジョブズと小売りの大家ロン・ジョンソンは、計画を数カ月間遅らせると急遽決断した。製品カテゴリーだけでなく、用途も加味した店舗レイアウトに変更するためだった。
〈iPhone〉をめぐっても同じようなことがあった。当初は、アルミニウムの筐体にガラス製のディスプレーをはめ込む構想だったが、ある月曜の朝、ジョブズがアイブのもとへやってきて「昨夜は眠れなかった。このデザインは好きになれないとわかったんだ」と言ったという。
アイブは、悔しさを感じながらも、すぐさまジョブズが正しいと悟った。「ものすごくバツが悪かったですよ。彼に指摘されるまで気づかなかったのですから」。何が問題だったかというと、〈iPhone〉ではディスプレーが主役であるべきなのに、当初のデザインでは、筐体が脇役に徹するのではなく、ディスプレーと張り合うようにして目立っていたのだ。機器全体があまりにがっしりしていて、仕事中心、効率一辺倒という印象だった。
ジョブズはアイブとその部下たちにこう切り出した。「みんなこの9カ月というもの、身を粉にしてくれた。だが、デザインを変えることにする。全員が夜間も週末も働かなくてはいけない。もしその気なら、いますぐ僕らを殺せるように銃を渡そうか」
チームは、食ってかかったりせずに変更を受け入れた。ジョブズはこの時のことを「アップルでひときわ誇らしく感じた瞬間です」と振り返っていた。
これと似た状況は、ジョブズとアイブが〈iPad〉の仕上げにかかっていた時期にも生じた。ある時ジョブズが見本を見て、かすかなひっかかりを覚えた。手に取って、そのまま持って歩こうと思うほどには、親しみやすさやさりげなさが感じられなかった。ふと片手でつかめそうだと思わせる、そんなシグナルを発するべきだったのだ。
そこでジョブズらは、底縁部にわずかに丸みを持たせようと決めた。こうすれば、注意して持ち上げるのではなく、気軽に手に取っても大丈夫だ、と感じてもらえるだろう。これを実現するには、筐体のへりを薄くして底に向かって緩やかな勾配をつけ、それに合わせて接続部のポートとボタンを設計する必要があった。ジョブズは製品のスケジュールを遅らせて、この変更の完了を待った。
ジョブズの完璧主義は、目に見えない部品にまで及んだ。子どもの頃、家の裏庭に塀を設ける手伝いをしていて、父親から、塀の裏にも表と同じだけ注意を払わなくてはいけないと教えられたという。「だれにもわからないでしょ」と言うと、父親から「お前は知っているだろう」と諭された。本物の職人は、戸棚の裏側、壁に接する面にも上質の木材を用いるから、自分たちも塀の裏側をなおざりにしてはいけないのだと。これは、飽くことなく完璧を追い求める芸術家の習性だった。
ジョブズは〈Apple2〉と〈Macintosh〉の開発を指揮した際、コンピュータ内部の回路基板にこの教訓を活かした。どちらの場合も、集積回路を整然と並べて基板の見栄えをよくするよう、技術者にやり直しを命じたのである。
これは、とりわけ〈Macintosh〉の技術者にとっては奇妙に思えた。ジョブズから、筐体をしっかり密封するよう命じられていたからだ。技術者の一人が「基板はだれの目にも触れないでしょう」と抵抗すると、ジョブズはかつての父親と同じような受け答えをした。
「たとえボックスのなかに隠れていようとも、できるだけ美しく仕上げてほしい。一流の匠は、だれにも見られないとしても、戸棚の背の部分に質の悪い板を使わないだろう」。自分たちは本物の芸術家なのだから、それ相応に振る舞うべきだというのである。基板の再設計が終わると、ジョブズは技術者ほか〈Macintosh〉チームの面々に署名をさせ、彼らの名前がコンピュータ内部に刻まれるようにした。「本物の芸術家は作品に署名をするものだからね」
[10]一流の人材しか受けつけない
よく知られる通り、ジョブズは短気で怒りっぽく、周りの人々につらく当たった。彼の他人への接し方は、称賛に値するものではないにせよ、完璧を求める情熱や、最高の人材とだけ仕事をしたいという思いに端を発していたのだ。
これは「能なしの急増」、つまり、マネジャーが部下にていねいに接するあまり、凡庸な人材がのうのうと、のさばる状況を避けるための、彼流のやり方だったのだ。「みんなを手荒く扱っているつもりはありません。仕事ぶりがお粗末だったら、本人たちに面と向かってそう伝えますよ。本当のことを言うのが私の仕事ですから」
ジョブズに、人当たりをよくした場合も同じ成果が得られたと思うか、と水を向けたら、おそらく得られただろうとも答えた。「もっとも、それでは私ではなくなってしまいますけれど。もしかしたら、もっとよい方法があるかもしれません。全員がネクタイを締めて、上流階級の言葉遣いでオブラートに包んだ話し方をする、紳士の集まりのようなね。ですが、私はそういった世界を知りません。カリフォルニア出身の中産階級ですから」
彼の荒々しい振る舞いや悪態は必要だったかというと、おそらくそうではないだろう。別の方法でチームのやる気を引き出すこともできたはずである。
スティーブ・ウォズニアックの言葉を紹介しよう。「スティーブ(・ジョブズ)がみんなを震え上がらせた逸話は数え切れないほどありますが、そんなことをしなくても彼は偉大な成果を上げられたでしょう。私はもっと根気よく構えて、対立を避けるのを好みます。会社は仲のよい家族のようになれると思うのです」
けれども、ウォズニアックは、紛れもない真実を言った。「もし私のやり方で〈Macintosh〉プロジェクトを舵取りしていたら、きっと混乱していたでしょうがね」
ジョブズの荒っぽさや、ぶしつけさが、人々を鼓舞していた事実を、大いに尊重すべきである。彼はアップルの従業員に、「画期的な製品をつくる」といういつまでも変わらない情熱や、「不可能に思えることでも成し遂げられる」という信念を植えつけた。
私たちは、いまある結果を基にジョブズを評価しなくてはいけない。彼の家族は結束が固かったが、同じことがアップルにも当てはまった。社内の逸材たちは概して長くともに働き、会社に厚い忠誠心を抱いていた。他社、たとえばジョブズよりも優しく寛大な経営者が率いる会社と比べても、この傾向は強かった。他のCEOがジョブズを研究して、忠誠を引き出す彼の能力を理解しないまま荒っぽさだけを模倣しようと決めたら、手ひどい失敗をするだろう。
ジョブズの言葉を引きたい。「私が長年学んできたことは、本当に優秀な人材に恵まれたなら、彼らを甘やかす必要などないということです。素晴らしい仕事をするよう期待すれば、それに応えてくれます。〈Macintosh〉開発チームのだれに聞いても、『苦労したが、そのかいはあった』と答えるでしょう」
実際、ほとんどのメンバーはそう言っている。デビ・コールマンはこう振り返った。「会議でジョブズは、『馬鹿野郎、お前なんか何一つまともにできないだろう』などと怒鳴り散らすのです。それでも私は、彼と一緒に仕事ができたなんて、どう考えても世界一の幸せ者だ、と感じているのですよ」
[11]じかに会って話し合う
デジタル世界の住人であるにもかかわらず、ジョブズは、じかに会って話すことの重要性を強く信じていた。あるいは、デジタル世界では孤立するおそれがあることを、知り尽くしていたからかもしれない。
「ネットワーク時代のいま、eメールやインスタント・メッセンジャーの〈iChat〉でアイデアをまとめればよいと考えたくなりますが、とんでもない。創造性は、ふとしたことで始まった打ち合わせや、成り行き任せの議論をきっかけに解き放たれるものでしょう。だれかとバッタリ会って、『何をしているの?』と尋ねたところ、意外な発見があり、すぐにあれこれアイデアが広がる、というように」
彼はピクサーの本社ビルを、ふとした出会いや協働が生じやすいように設計させた。「建物がそのようにできていなければ、偶然の出会いから数々のイノベーションや魔法のような成果が生まれる可能性が、潰れてしまうでしょう。ですから私たちは、建物の設計を工夫したのです。みんなが自分の部屋から出てきて、中央のアトリウムで、他では接する機会のない人たちと交流するようにとね」
建物正面のドア、主な階段や廊下はすべてアトリウムへと通じていて、そこにはカフェや郵便受けが設置されていた。会議室の窓からはアトリウムが見下ろせた。座席数600の劇場と、それより小さい2つの上映室は、アトリウムにつながっていた。
「初日からスティーブの狙い通りのことが起きました」とジョン・ラセター監督は振り返る。「何カ月も会っていなかった人たちと次々と鉢合わせしましたよ。協働や創造性を引き出すのにあれほど適した建物は、他に見たことがありません」
ジョブズは形式張ったプレゼンテーションを嫌い、対面での自由闊達な会議を好んだ。幹部らを毎週集めて、正式な議題なしに、アイデアについてあれこれ議論したほか、水曜日の午後には、これと同じことをマーケティング・広告担当チームと行うのを定例にしていた。
スライドを用いたプレゼンテーションはご法度だった。「じっくり考えることをせずに、スライドでプレゼンをするのはごめんです。プレゼンの準備をすると、課題と向き合います。ですから、何枚ものスライドを見せるのではなく、議論に加わって、アイデアを出してほしいのです。課題をよく理解しているなら、〈PowerPoint〉などいらないはずです」
[12]全体と細部の両方をつかむ
ジョブズは、大小どちらの課題にも情熱を注いでいた。CEOのなかには、ビジョンに秀でた人もいれば、「神は細部に宿る」ことを心得た管理巧者もいる。
タイム・ワーナーのジェフリー・ビュークス会長兼CEOは、ジョブズについて、包括的な戦略を思い描く一方、ごく些細なデザインをも大切にしようとする熱意と能力において傑出していた、と述べている。たとえば、ジョブズは2000年に、PCは「デジタル・ハブ」(拠点)となり、利用者の音楽、動画、写真、コンテンツすべてを管理すべきだ、とする壮大なビジョンを掲げた。
そして、このビジョンを基にパーソナル機器事業に参入し、〈iPod〉、次いで〈iPad〉を世に出した。2010年にはこれに代わる戦略として、「ハブ」をクラウドに移行する構想を打ち上げた。
アップルは、巨大なサーバー・ファームの建設に着手し、利用者のコンテンツすべてをサーバーにアップロードして、そこから各種のパーソナル機器に円滑に同期できるようにした。ジョブズはこのように、壮大なビジョンを示しながらも、〈iMac〉内部のネジの形状や色についても頭を悩ませていたのだった。
[13]人間らしさと科学を結びつける
ジョブズが伝記に協力しようと決心した日、私にこう語ってくれた。「子どもの頃はいつも、自分の関心は人間に向いていると思っていましたが、一方で電子機器も好きでした。そのうちに、私にとって英雄の一人である、ポラロイドの創業者エドウィン・ランドの言葉を目にしたのです。ランドは、人間らしさと科学が交差する位置にいる人々の重要性を説いていました。それを聞いて、自分もそういう人間になりたいと思いました」
ジョブズは、あたかも自分の人生のテーマについて語っているようだった。ジョブズについて調べるにつれて私は、これこそがまさしく、彼の物語の本質だという確信を深めた。
ジョブズは人間らしさと科学、創造性とテクノロジー、芸術とエンジニアリングを結びつけた。技術者の世界には、スティーブ・ウォズニアックやビル・ゲイツなど、もっと偉大な人物がいた。デザインや芸術の分野でも、ジョブズに勝る人物はいた。しかし、詩的な美しさとプロセッサーを融合してイノベーションを巻き起こすことにかけて、彼の右に出る同時代人はいないだろう。
しかも、ジョブズはこれを、事業戦略を直観的に判断しながら行っていた。この10年というもの彼は必ずといってよいほど、新製品の発表を一般教養(リベラル・アーツ)とテクノロジーの交差点を示すスライドで締めくくっていた。
強烈な個性を持った人物が、人間らしさと科学の両方を理解することによって発揮する創造性は、私がベンジャミン・フランクリン[注1]とアルバート・アインシュタインの伝記[注2]を書きながら、最も関心を惹かれた対象である。
このような創造性こそ、21世紀の革新性あふれる経済を築くカギになるだろう。これは、想像力を応用して、具体的な成果を上げるために必要な本質であり、だからこそ、将来的に高い創造性の発揮を目指す社会にとっては、人間らしさと科学の両方がきわめて重要なのである。
ジョブズは死の床にあってなお、「さらに多くの業界に風穴を開けてやろう」という気概を持っていた。〈Mac〉があればだれでも、教科書を美しい作品に変えられる、そんなビジョンを温めていたのである。
アップルはこのビジョンを具体化し、2012年1月に製品として発表した。またジョブズは、デジタル写真向けの魔法のようなツールを開発したり、個人向けのシンプルなテレビを提供したり、といった夢を持っていた。これらも間違いなく形になるだろう。
ジョブズは夢の成就をみずから見届けはしない。しかし、ジョブズ流の成功ルールをよりどころに築かれた企業アップルは、中核部分に彼のDNA(遺伝子)が宿っている限り、すでに種の蒔かれたものを含む、きわめて画期的な製品の数々を生み出すだけでなく、創造性とテクノロジーの交差点に留まり続けるだろう。
[14]貪欲であれ、愚直であれ
スティーブ・ジョブズは、60年代後半にサンフランシスコの湾岸地域(ベイエリア)で起きた、2つの大きな社会運動から多大な影響を受けた。
一つは、幻覚剤、ロック・ミュージック、反権威主義などに象徴される、ヒッピーや反戦活動家による反体制文化である。2つ目はシリコンバレーのハイテク、ハッカー文化である。その担い手は大勢の技術者、オタク、コンピュータ・マニア、電話の不正使用者(ハッカー)、サイバーパンク作家、道楽者、ガレージを根城にする起業家だった。
この2つに染まると、禅とヒンズー教、瞑想とヨガ、プライマル・スクリーム療法と感覚遮断、エサレン法と心身統一訓練など、さまざまな自己啓発への関心が芽生えた。
これら文化の混合形態は、活字の世界にも波及した。スチュアート・ブランドが発行した『ホール・アース・カタログ』誌はその具体例である。
『ホール・アース・カタログ』の第1号の表紙には、宇宙空間から地球を写した有名な写真が掲載され、「道具への誘い」(access to tools)という副題がついている。その根底には、「人間はテクノロジーを味方にできる」という発想があった。
ヒッピー、反逆者、求道者、電話のハッカー、電子機器愛好者など、一人でいくつもの顔を持つジョブズは、この雑誌を熱心に愛読した。
ジョブズが高校生だった71年、その年に発行された最終号には、特に強い思い入れがあったようだ。大学に入った時も、中退後にリンゴ農園で生活共同体の一員として暮らしていた時も、この最終号を身近に置いていた。後にこう回想している。
「最終号の背表紙には、早朝の田舎道の写真が載っていました。いかにも冒険好きがヒッチハイクをしそうな場所です。写真の下には『貪欲であれ、愚直であれ』というコピーが刻まれていました」
ジョブズは職業人生を通して終始、貪欲で愚直な姿勢を貫いた。事業家、技術者としての自分を常々、風流を愛し、ドラッグにはまり、悟りを求めていた頃からの、ヒッピー風反逆者としての自分で補うことにより、完璧を目指そうとしたのである。
彼のなかでは、どのような女性とつき合うか、ガンの宣告にどう対処するか、事業をどう舵取りするかなど、人生のあらゆる局面において、実に多様な側面が互いにせめぎ合い、歩み寄り、最後には一つに溶け合って、行動を導き出すのだった。
アップルがひとかどの企業になった後でさえ、ジョブズは、広告にも反抗的、反体制的な性格を反映させた。「本当の自分はいまなお、ハッカーでありヒッピーなのだ」と宣言するかのようだった。
有名な『1984』という広告は、女性の反逆者が思想警察を振り切りながら走ってきて、ビッグ・ブラザー(ジョージ・オーウェルの小説『1984』の登場人物)を模した人物を映し出したスクリーンに、大きなハンマーを投げつける様子を描いている。
追放を経てアップルに復帰した後にジョブズは、『Think Different』広告のコピー作成にも一役買った。「クレイジーな人たちがいる。反逆者。やっかい者といわれる人たち。四角い穴に丸い杭を打ち込むように……」。意識していたかどうかは別として、彼は自分を表現していたのだろう。最後のくだりが、この推測を確信へと変える。
「彼らはクレイジーといわれるが、私たちは天才だと思う。自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが、本当に世界を変えているのだから」
【注】
1)Walter Isaacson, Benjamin Franklin: An American Life, Simon & Schuster, 2003.(未訳)
2)Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe, Simon & Schuster, 2007.(邦訳『アインシュタイン(上・下)』武田ランダムハウスジャパン、2011年)
有賀裕子/訳
(HBR 2012年4月号より、DHBR 2012年11月号より)
The Real Leadership Lessons of Steve Jobs
(C)2012 Harvard Business School Publishing Corporation.
ウォルター・アイザックソン(Walter Isaacson)
アスペン研究所社長兼CEO。著書にSteve Jobs, Simon & Schuster, 2011.(邦訳『スティーブ・ジョブズ(Ⅰ・Ⅱ)』講談社、2011年)ほか、ヘンリー・キッシンジャー、ベンジャミン・フランクリン、アルバート・アインシュタインの伝記がある。