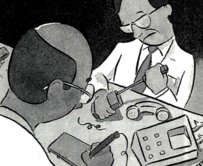改善活動の継続における
2つのアプローチ
改善活動の継続を考える上で、ここでは対照的な2つのアプローチを紹介します。以下2つのアプローチは、ある意味でそれぞれ極端な例ですから、実際の企業で行われている改善活動は、これら2つのアプローチの中間に位置づけられるものです。ただ、強いて言えば、自社の改善活動がどちらのアプローチにより近いかを判定できると思います。
1-1消耗型改善とは
第1のアプローチは、消耗型改善と名付けるアプローチで、主に改善活動の直接効果を短期間で狙うアプローチです。横軸に時間、縦軸に改善成果をとって、改善活動の軌跡を示せば、左上に凸のグラフが描けるアプローチです。このアプローチの特徴は、他社で導入実績があり評判の高い流行の手法・技法を自社にも適用することで、短期間で効率的に改善活動を進めようとする所にあります。
多くの場合、このアプローチは何らかの形で、企業が危機的状況に直面した際に採用されます。他社で導入実績のある、いわば「お墨付き」の手法・技法を採用するため、最初から効果が出やすく、活動の初期段階から改善が進みやすいと言えます。あるいは、効果の出やすい改善から意図的に着手していると言っても良いかもしれません。
また、多くの場合には、導入プログラムが事前に詳細に出来上がっているので、1つの改善が終わったら、次にどのような改善を行うべきか、その次に何を行うかなど、改善の進め方・ステップが整然と明示されており、計画的に安心して導入することができます。
1-2消耗型改善の限界
しかし、このアプローチの最大の欠点は、いずれ限界が来る、あるいは、いずれ改善のネタが尽きる、という点です。特定の手法・技法をマスターすることが目的になりやすく、特定の手法・技法が照らし出す範囲内の問題はすぐに解決できるものの、活動が進めば進むほど特定の手法・技法で解決できる問題が少なくなり、そのため活動の推進力は徐々に低下していきます。このような状況で、改善活動を推進するスタッフが考えることは、次の手法・技法の探索です。改善活動を長期間継続して実施していくためには、活動の継続を支える次なる手法・技法の採用が必要になるのです。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)