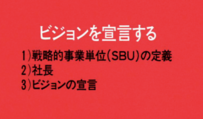これに加えてもうひとつは、こちらの方が深刻な問題なのだが、その会社の戦略や能力や文化との非適合。この場合、鳴り物入りで導入された「新しい制度」が、その会社の「本当にやりたいこと」や「本当にありたい状態」をかえって阻害してしまい、組織の人々の力を抑圧する。言うまでもなくそうした制度は社内の人々から自然と受け入れられないため、制度だけが浮き上がってしまうという結果になる。
「制度はいいのだけれども、運用がついていかない」という問題の立て方が根本的に間違っていると思う。問題の本質は「制度化するのが早すぎる」ことにある、というのが僕の見解だ。ある新しい動きが制度やシステムに先行して会社のどこかで現実に始まり、それが目にみえる効果を発揮し、徐々にその効果に納得した周囲の人々に受け入れられる。制度化するのはそれからでも遅くない。
すでに起きて成果を出している動きを「追認」する形で制度が導入される、というのがもっとも望ましいものごとの順番なのではないか。制度を設計してからそれを実行なり運用に移すのではなくて、すでに実行されている動きを制度化するという発想に立てば、「運用上の問題」は定義からしてほとんどなくなる。
ようするに、制度やシステムは現実の運用に「遅れて」導入されるべきだ、というのが僕の言いたいことだ。このところの取締役会改革、能力主義の人事評価システム、女性の登用を促進するための「ダイバーシティ・プログラム」、こうした制度改革にかけ声倒れの失敗例が続出する背後には、「制度先行の落とし穴」がある。
制度先行の失敗は、企業よりもさらに政府のやることなすことで顕著だ。何か問題があると、担当者がすぐに制度に逃げる。問題の原因を「制度が悪かった」「システムが不備だった」ことにしてしまい、ひたすら制度設計の作業に埋没する。ここに変革が進まない根本的な理由があるように思う。しばらく前の話だが、天下りを抑制するために官僚OBの「人材バンク」という制度をつくったものの、数年たってもほとんど誰も利用しなかったという情けない事例があった。コストをかけて制度をつくっても、新しい動きが起きない。これでは何も変わらない。
現状に問題を感じ、変革を起こしたい人は、制度設計に逃げてはいけない。新しい制度が敷かれるのを待たずに、まず自ら動くことだ。とりあえずは自分の影響の及ぶ範囲でよい。まず自ら新しい動きを起こし、「小さな成功例」をつくる。それを目に見える形で組織の他の人々に示す。賛同する人が出てくる。彼らが同じような動きを起こせば、その他大勢もそのうちについてくる。制度やシステムを考えるのはその後で十分だ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)