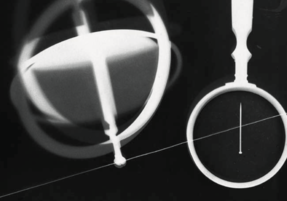-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
エレクトロニクス企業の巨額赤字計上などの悪いニュースが出るたびに、「日本のものづくりは衰退した」と騒がれるが、このような意見は、現場・企業・産業・経済の根本的な違いを無視し、「ものづくりは現場で起こる」という基本認識を欠いている。かくも多数派のものづくり論が混乱するのは、長期的な「現場視点の歴史観」の欠如によるものではないだろうか。そこで本稿では、戦後の国内ものづくり現場の略史を、約20年刻みの時代区分で試みる。すなわち、戦後の復興・冷戦成立期を経た、1950~60年代の「移民なき高度成長期」、70~80年代の「冷戦下の国際競争期」、そして90~2000年代の「冷戦後の世界競争期」である。特に直近20年の国内現場に注目すると、円高が進行するなか、低賃金の隣国との過酷な競争を強いられた「暗黒時代」だったといえる。これらのハンディを能力構築で克服して生き残り、なお生産性向上の大きな伸びしろを持つ国内の優良現場は、今後20年は、過去20年より存続可能性が高まるだろう。内外賃金差が急速に縮小しているからである。日本の優良現場は、言わば「夜明け前の闇のなか」にいると見るのが、現場の歴史観から想定される、現場の近未来である。
ものづくり論の混乱と歴史観の欠如
日本のものづくりの象徴であったエレクトロニクス企業が巨額の損失を計上し、日本の十八番と考えられていた国内テレビ産業が急速に競争力を失い、貿易収支が数十年ぶりに赤字化し、国内総生産の長期低迷は続く──日本の企業・産業・経済に関する近年のニュースは、たしかに明るいものが少なく、人々が悲観的になるのは無理もない。株価や円レートに一喜一憂する心理もわかる。
しかし、これらをもって「日本のものづくりは衰退した」とする大勢の意見は、現場・企業・産業・経済の本質的な違いを理解しておらず、「ものづくりは現場で起こる」という基本認識が欠けており、総じて誤りである。