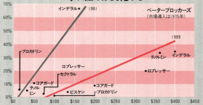-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ハーバード・ビジネス・レビューでは、毎月、本誌にご執筆いただいた方を講師にお招きして勉強会を開催している。少人数によるディスカッションを中心とした勉強会は、魅力と活力にあふれた会として好評だ。今回はマッキンゼー・アンド・カンパニーの佐藤克宏氏を講師に迎え、「競争優位は持続するか」というテーマで、プレゼンテーションを行っていただいた。
【テーマ】「競争優位は持続するか」
【 講師 】佐藤 克宏氏(マッキンゼー・アンド・カンパニー プリンシパル)
【 日時 】2013年11月8日(金) 19時~20時30分
【 場所 】d-labo コミュニケーションスペース(ミッドタウン・タワー7階)
DHBR勉強会について
ハーバード・ビジネス・レビュー(DHBR)では、毎月1度、本誌にご執筆いただいた方を講師にお招きして勉強会を開催しています。各回のテーマに沿ったプレゼンテーションの後、参加者の方々とディスカッションを行う形式をとっています。アットホームな会場、20名という少人数、隔たりのない講師の方との近さという贅沢な空間が、ほかにはない活発な議論を誘い、これまで参加いただいた方々からも好評をいただいております。また、参加者の年齢や職種も幅広い層にまたがっており、大変刺激的な会となっています。
ケイパビリティが不足する日本企業
今回のテーマは「競争優位」。講師にはマッキンゼー・アンド・カンパニー プリンシパルの佐藤克宏氏をお招きし、競争優位の源泉となるケイパビリティ(組織能力)とは何なのか、どのように活かすべきなのか、お話しいただきました。
これまではWhere(どこで)What(何をもって)How(どのように)の3つを決めることが戦略だと言ってきましたが、変動の激しい今の世では戦略そのものに加えて、先を見通す力のような、次の戦略を生み出す原動力となるケイパビリティも競争力の源泉として重要になってきています、と述べられました。

この距離感も特徴のひとつ
ケイパビリティに関して、日本企業には3つの問題があることを示されました。まず、日本ではファンクション(組織機能)という概念が欠けていること。ファンクションはケイパビリティの前提にあるものです。グローバル企業ではファンクションごとにスキルとして定式化されていますが、日本にはそもそも概念がないため、組織として構築されたスキルをもっていませんでした。2つ目は、ファンクションがあってもスキルが組織化されていないということ。個人技を組織全体のものとして形式知化することで、はじめてケイパビリティが生まれるのです。3つ目は再現性がないということ。こうした組織化の範囲も、限定的なところに留まってしまっていてはケイパビリティとは言えません。
つまり、日本企業は何をもってケイパビリティとするのか。どのような形で組織化するのか。どうそれを再現性ある形でスケールアップするのか。これらについて答えを出す必要があるのです。そして、理論だけでなく実務に当てはめることで、スキル構築が可能となる、と語られました。
コーポレート・アカデミーの果たす役割
いま、世界的にコーポレート・アカデミー(企業大学)が注目されています。少し前までは幹部のリーダーシップ教育が主眼でしたが、いまはそれに加えてケイパビリティの伝道も大きな目的となり、内容も変化してきたそうです。
企業にとって一番重要なのは戦略です。しかし、戦略を実行するにはケイパビリティが欠かせません。ケイパビリティを生み出し、広める役目はコーポレート・アカデミーが担っているのです。そのような教育をするために、形式知化が土台として求められています。

右:佐藤克宏氏 左:弊誌編集長
実際には、場面によって必要とされるスキルは変わってくるものです。コーポレート・アカデミーでは、巡航速度として持っておくべきスキルについてはコンピテンシー・スクール、今後身につけたいスキルはブレークスルー・アカデミーというように分けています。そして時間経過とともにブレークスルーがコンピテンシーに移り、新しいブレークスルーが生まれてくるという循環が出来上がっています。
このようなコーポレート・アカデミーは欧米から広まり、最近はアジアでも活発になってきていますが、日本ではまだまだ取り組みが少ない状況です。日本人は戦略を掘り下げるスキルが不足しています。それをしなければ、ただの自己満足となってしまうことに注意しなければいけません。このような習慣を持つこともケイパビリティの一つなのです、と述べられました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)