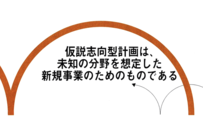-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
本誌2014年1月号(2013年12月10日発売)の特集「人を動かす力」関連記事、第5回。前回は、影響力を行使する5つのスタイルを紹介した。特定のスタイルへの固執を避けるために、それぞれがいつ効果を発揮しないのかを説明する。
今日の複雑に入り組んだ組織では、他者に影響を及ぼす能力が、成功を収めるためのカギとなる。前回の記事では、影響力のスタイルの分類を示し(理由づけ、主張、交渉、鼓舞、関係づくり)、当社の提供する自己診断ツール(influence style indicator)へのリンクを載せた。影響力のスタイルについて学び、自身がどれに該当するかを知ることは、個人の能力を開発するために欠かせない。
私たちは無意識のうちに、自分が好む影響力のスタイルを1つか2つ持っている。その同じスタイルを他者に行使されると、最も影響を受けやすい。5つのスタイルを効果的に、臨機応変に使い分けることを身につけない限り、他者に影響を及ぼす能力とその効果は限定的なままである。
自分自身のスタイルを知り、それ以外のスタイルについても学んだら、次のステップは、各スタイルがどんな時に効果がないのかを知ることだ。前回の記事に寄せられた賢明なコメントにもあるように、誰もがすべてのスタイルを1度や2度は用いたことがあるはずだ。つまり、どのスタイルも本質的に悪いものではない。実際、影響力を行使する者が状況を十分に考慮すれば、いずれも機能しうる。状況とはつまり、関わっている人々、彼らの関心、組織文化である。
しかし、望んでいる結果にばかり注意を向け、状況を十分に考慮しない場合、その影響力には効果がない。短期的には望ましい結果を出せるかもしれないが、長期的には自分の能力開発においても組織にとってもマイナスとなる。人々が自分に耳を傾けるのをやめ、不信感が醸成され、イノベーションや進歩の可能性が減じてしまう。
あるスタイルが効果的か否かは、完全に状況次第である。したがって、自分が用いているスタイルが適切でないことに気づくのは難しい。同じ議論やプレゼンテーションでも、聞いている人によって解釈が異なる。したがって、あるスタイルが効果的でないと認識するには、人間関係を十分に見極めることが必要だ。それによって、自分の訴えが人々にどう理解されているかを正確に判断しなければならない。
異なるスタイルを臨機応変に使い分けるために、各スタイルがうまく機能しない状況を紹介しよう。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)