自社の強みへの立脚
日本企業が有効な成長戦略を採れないもう1つのカベは、「伸びそうな市場だから参入する」「他社もやるから自社も参入する」という事業展開パターンを採りがちなことである。これでは結局、横並びの過当競争になってしまう。なぜこうなるのかというと、事業参入の判断の多くが事業部レベルで行われ、その動機が自部門の売上減を隣接領域に進出することで糊塗しようという場合が多いためである。
隣接領域といっても、そこには従来からの企業が陣取っており、独自の強みをもって顧客を押さえているはずである。そこに、強みが相対的に劣る企業が隣接分野から参入してきても、顧客を獲得することはなかなか難しい。そこで、低価格訴求で食い込もうとすることになる。隣接分野に参入して事業部の売上げが増え、利益もギリギリで確保できていれば、事業部全体としても増収増益である。ただし、利益率は本業分野よりも低いものが混じるため、従来よりも低下していく。
また、事業部レベルで参入判断を行う場合は自前主義で考えることになりやすく、強みのない業務も自前ですべて行おうとすることになりやすい。他社との提携といった話になると事業部だけでは決められず、経営会議などの判断を仰がなければならないからだ。もともとの動機が自部門の売上減を糊塗しようとしているのであり、できれば「こっそり」と事業部内で賄いたいというのは自然な流れである。これでは、グローバル企業とのアライアンスなどは選択肢にも入らなくなる。
こうした問題を避けながら成長戦略を追求するには、コーポレート(世界本社)のレベルで、自社固有のケイパビリティは何か、自社に不足するケイパビリティは何か、それを補うアライアンス候補はどこかを考えることが必要になる。
では、そもそも自社独自のケイパビリティとは何なのか。それをあぶりだすために有効なのは、「仮にX社とアライアンスを組むとしたら」を考えてみることである。自社とは強みの異なる他社を具体的に念頭に置き、自社はX社のどんな強みを手に入れたいのか、そしてX社は自社のどんな強みに興味を持ちそうなのかを考えるのである。必要であれば、強みの異なるY社、Z社を仮想パートナーとして、さらに検討してみてもよい。他社が必要とするような強みが自社になければ、そうしたアライアンス構想も単なる妄想に終わる。自社内では当たり前すぎで気づかないようなことが、他社から見ると羨ましい強みになっていることもある。
そうして自社の強みを再認識し、それをもとにしてメガ・トレンドの成長機会にチャレンジすることができれば、長期的な成長戦略が描きやすくなっているはずである。





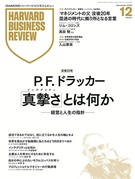
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









