自社の目指すべき、勝ちパターンの特定
世界本社機能を確立し、強みの再認識ができ、どのメガ・トレンドに乗るべきかを特定できたとして、もう1つ重要となるのが、どういう勝ちパターンを作れるのか構想することである。サッカーで言うと、どういう「ゴール・イメージ」を持ち、そこに持っていくためにどういうパスを誰を起点に出すのかを考え、そこへの流れをどう持っていくかを全員でイメージするのである。この流れのイメージのないままにボール・キープ率だけを高めても、いつまでたっても得点は入らない。
長期の成長ビジョンの「ゴール・イメージ」として、儲かる分野を追求していくにはいくつかのパターンが考えられる。
1.メガ・トレンドのテーマのうち、自社のコア事業の強みを活かせる(=他社では追随も難しい)分野に経営資源を集中させる。自前でこれが実現できるのであれば、一番王道と言えるパターンであろう。
2.グローバル市場の中で、自社のコア事業の強みを横展開できる成長市場を特定し、買収や提携なども用いながら、地理的に事業を次々と拡大する。すでに何カ国かで成功した勝ちパターンをさらに繰り返していける場合、すなわち市場の特徴がどの国でもほぼ似ているという場合には有効なパターンである。
3.自社のビジネスモデルの強みを活かし、その仕組みの上に載せることが可能な関連事業の規模を買収や提携を通じて拡大する。典型的には、顧客ベースをきっちりと押さえている場合、その顧客ベースに重ね売りできるような事業を外部から次々と導入してくるというパターンである。
4.自社のビジネスモデルの弱みを認識し、相対的に優位性の低い業務からは撤退(=提携先などに譲渡・委託)して、自らは得意分野に集中してグローバルなスケールを狙う。欧米企業の場合、製造業務から撤退(台湾企業などに外注)して、技術開発、製品企画、マーケティング、顧客サービスに注力するというパターンを選ぶケースもある。
逆に、長期の成長ビジョンになりえないパターンは極力避けることが重要となる。
1.非関連分野への多角化によって二流の事業をいくら増やしても、各分野でグローバルなトッププレーヤーには到底勝てない。
2.成長分野だからと言ってさまざまな分野に参入しても、他社も容易に参入できるような市場はすぐに過当競争に陥るので利益が出ない。
3.すべての領域を自前で賄おうとしても、グローバルなスケールを活かせるほどの規模にならない限り、利益率のさらなる低迷を招くことになる。
4.とくに「製造」という領域は、新興国企業が低コストを武器に次々と参入できる分野であり、ここでの自前化に過度にこだわっていると苦戦を強いられることになる。
本連載で紹介してきたメガ・トレンドとは、あくまでも成長戦略を構想するうえでのピースでしかない。世界本社機能の確立や自社の強みの再認識をベースに持ち、「ゴール・イメージ」まで明確にできてはじめて、本当の成長戦略になる。とはいうものの、メガ・トレンドという大きな追い風に乗らず、一生懸命に自力で自転車をこいでいるだけでは、なかなか成長はできない。自社の事業の周りには今後どのようなメガ・トレンドが流れていくのかを見極めることが、成長戦略を構想するための第一歩となることを期待したい。
グローバルな経営コンサルティング会社として、世界のトップ企業及び諸機関に対し、経営レベルの課題を解決するコンサルティング・サービスを提供している。全世界57事務所に3,000人以上のスタッフを擁し、クライアント企業との実践的な取り組みを通じて、「本質的な競争優位」と「差別化された優れたケイパビリティ」の創出を支援することを使命とする。
【連載バックナンバー】
第1回「長期的ビジョンはなぜ必要なのか」
第2回「グローバル市場の変化を見通す」
第3回「グローバルな10のメガ・トレンド」
第4回「第1のメガ・トレンド 環境保護主義」
第5回「第2のメガ・トレンド 資源をめぐる戦い」
第6回「第3のメガ・トレンド 人口動態と富」
第7回「第4のメガ・トレンド 人口移動」
第8回「第5のメガ・トレンド 富の再配分」
第9回「第6のメガ・トレンド ビジネスのグローバル化」
第10回「第7のメガ・トレンド パワーシフト」
第11回「第8のメガ・トレンド さらに賢くなる個人」
第12回「第9のメガ・トレンド ライフスタイル変革」
第13回「第10のメガ・トレンド ネットワーキングと生産性」
第14回「メガ・トレンドに関連する成長機会」





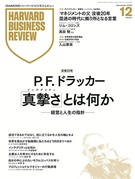
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









