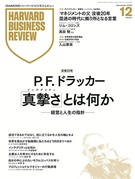次に各シナリオの起こる確率を想定しましょう。
TAは非常に難度が高いので、2つの選択肢における演技の “Good”/“So So”/“No Good”の確率分布は大きく違うと考えられます。
演技の出来がよくなくても、他選手次第では金メダル獲得の可能性はありますが、当然、「TA挑戦」で“Good”のほうが「TA回避」で“Good”の場合に比べて金メダル獲得の確率は高い、等々と考えてそれぞれのシナリオの確率想定を行います。
演技の出来(の見通し)にかなり自信があり、他選手との比較で金メダル獲得の確率が高いと思われる場合は、直感的に迷わずTAを選択すると考えられます。
そのため今回のシミュレーションでは、あえて「演技の出来に自信が持てず、他選手との対比で金メダル獲得の確率が低い」という困難な意思決定の状況を想定して確率分布を設定しました。
なお、ここでの確率はあくまで「主観的な感じ方」を確率で表したもの(=主観的確率)ですが、今回は浅田選手にとってどう感じられるか、筆者の想像で想定しています。
今度は計12のケースの嬉しさの順位を考えます。
浅田選手にとっての価値判断尺度は「自分の得意技であるTAにトライすること、そのこと自体」「TAへの挑戦・回避に関わらず、演技としての出来栄えのよさ」「金メダルを獲れるかどうか」の3つで、この3つの価値判断尺度をトータルしたものとしての「正味嬉しさ総額:Net Pleasure Value(NPlV)」で、各ケースの自分にとっての嬉しさ度合いを判断すると考えられます(ちなみに、NPlVというのは、キャッシュフローの正味現在価値:Net Present Valueをもじって筆者が名づけたもので、お金以外の要素を含めたトータルとしての嬉しさを表現する場合に便利な概念です)。
そこで、このNPlVの考え方に基づき、段階を追って、12のシナリオの嬉しさ順番を考えて行きます。
まず「TA挑戦」の場合で考えてみます。金メダル獲得の3つのシナリオの比較では演技の出来がよいほうがNPlVは大きいと思われますし、金メダルを獲れない3シナリオの比較でもそのことは同様でしょう。そしてもちろん、演技の出来が同じなら金メダルが獲れたほうが嬉しいに決まっています。
さらに、浅田選手は「自らの達成感」よりも「国民の期待に応えて金メダル」をより大きな喜びとすると基本的には思われますが、「自らの出来は“No Good”だったが敵失要素で金」よりも「完璧だったが相手がより素晴らしくて金を逃す」ほうがすがすがしいと考えるのではないかと想定してみました。