また筆者らの調査によれば、インドやウガンダのような、最低限の欲求を満たすことさえ容易ではない非常に貧しい国においても、人に何かを与えたことを思い返した人のほうが、自分のためにお金を使ったことを思い返した人よりも、より満足していた。それだけでなく、わずか数ドルでも他人のために費やすことが、幸福感の増大につながることもある。ある調査では、被験者にその日のうちにたった5ドルを他人のために使うように依頼したところ、1日の終わりには、同じ5ドルを自分のために使った人よりも満足感を得ていた。
賢いマネジャーは、他者にお金を使う行為がもたらす効果を利用して、従業員の幸福感を高めようとしている。たとえばグーグルには、従業員向けのユニークな「ボーナス」プランがある。誰でも自分以外の従業員を150ドルのボーナス獲得者として推薦できるというもので、そのための資金をプールしている。グーグルの平均給与からいって、150ドルのボーナスは少額だ。だがこの制度の特徴――ボーナスを自分が欲しがるのではなく、他の従業員に与えること――は、心理的に大きな見返りをもたらすことができる。
他者のためにお金を使うことは、顧客にも影響を及ぼす。ある遊園地は、入園者が乗り物に乗っている時の写真を本人に売ろうとしていたが、なかなか買ってもらえずにいた。12.95ドルの定価で買ってくれたのは全乗客の1%にも満たない。そこで研究者らは、もっと賢い売り方を試みた。乗客は任意の値段(0ドルを含む)で写真を買うことができ、その金額の半分がチャリティーに寄付されると伝えたのだ。すると、写真を買えばお土産になると同時に、他者への投資にもなる。この選択肢が与えられた後、乗客の4.5%が写真を購入し、1人が平均で5ドル以上を支払った。その結果、同社の乗客1人当たりの利益は4倍に増大した。
ウォーレン・バフェットは、幸福の伝道師である。お金を儲けるために彼の言葉に従ってきた人は、今度は幸福になるための彼のアドバイスにも従うべきだ――筆者らの調査結果はそう告げている。たった5ドルでも、お金の使い方を見直せば、支払うたびにより多くの幸せが手に入る。そしてバフェットの幸福のアドバイスには、経済的な見返りもある。ボーナスの獲得や商品への支払いにおいて、すべてのお金から従業員と顧客が得る幸福を最大化すれば、企業は従業員満足度と顧客満足度を高めることができる。それは収益にも貢献するのだ。
HBR.ORG原文:How Money Actually Buys Happiness June 28, 2013
■こちらの記事もおすすめします
顧客を歓喜させることの価値
「社会を良くしたい」という思いがラグジュアリー消費を後押しする
先進国と途上国をテクノロジーで結ぶ
エンジニアが現地で感じる、新たなひらめき

エリザベス・ダン(Elizabeth Dunn)
ブリティッシュコロンビア大学心理学部准教授。著書に『「幸せをお金で買う」5つの授業』(KADOKAWA/中経出版)がある。
マイケル・ノートン(Michael Norton)
ハーバード・ビジネススクール准教授。経営管理論を担当。著書に『「幸せをお金で買う」5つの授業』(KADOKAWA/中経出版)がある。




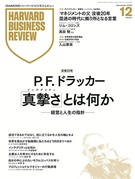
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









