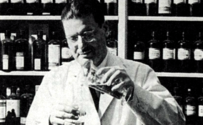●毎日散歩をする
多くの天才たちにとって、頭を冴え渡らせるには散歩が欠かせなかった。セーレン・キルケゴール(デンマークの哲学者)にとって散歩はインスピレーションの大いなる源だった。散歩中にアイデアがひらめくと大急ぎで机に戻り、帽子も脱がず、杖や傘を手にしたまま執筆を再開したという。チャールズ・ディケンズ(ビクトリア朝時代のイギリスの文豪)は、毎日午後に3時間の散歩をしたことで知られており、散歩中に目にしたことを作品に取り入れた。チャイコフスキーは散歩を2時間で済ませたが、120分きっかり歩かなければ病気になると信じ込み、1分たりとも早めに切り上げなかった。ベートーベンは昼食後に長い散歩をしたが、インスピレーションが沸いた時のために紙と鉛筆を携行した。エリック・サティ(フランスの作曲家)もパリから労働者の住む郊外にある自宅まで、かなりの距離を歩いて帰宅した。その道すがらでアイデアがひらめくと、街灯の下に立ち止まってメモをした。そのため、戦時中に灯火管制が敷かれた時には生産性が落ちたという。
●作業ノルマを設け、測定する
アンソニー・トロロープ(ビクトリア朝時代のイギリスの文豪)は1日に3時間しか執筆しなかったが、15分間で250語ずつ書くことをみずからに課していた。また、3時間の途中で執筆中の本が書き上がると、すぐに新しい小説の執筆に取りかかった。アーネスト・ヘミングウェイは「自分を偽らないように」、毎日執筆した文字数を表に記した。B・F・スキナー(アメリカの心理学者)は執筆時間をタイマーで管理し、かかった時間と文字数をグラフ化した。
●大事な仕事と雑務を分ける
eメールが登場する前は手紙が使われていた。当時の人々がいかに多くの時間を手紙の返信に費やしていたかを知り、私は驚くとともに恐れ入った。午前中は作曲や絵を描くという本来の仕事に当て、午後は手紙の返信などの雑務に当てていたケースが多い。なかには、本来の仕事がはかどらない時に雑務を片づけた人もいる。ただし、いつでも届くeメールと違い郵便は一定の間隔でしか届かないので、やり取りの量がいまと同じだったとすると、かつての天才たちのほうが楽だったかもしれない。
●不調な時ではなく、波に乗っている時に仕事を終える
ヘミングウェイは「まだ精力があり、次の展開が頭で描けているところで筆を止め、翌日までその案を寝かせて再び書き始める」と述べている。アーサー・ミラー(アメリカの劇作家)は、「アイデアを枯渇させることはよくない。私は、書きたいことがあるうちにタイプライターから離れることにしている」と言った。例外的に、アマデウス・モーツァルトのように朝6時に起き、慌ただしく音楽のレッスンやコンサート、人付き合いをこなし、深夜1時まで寝ないような者もいた。しかし天才たちの多くは午前中に執筆し、昼食を取って散歩に出かけ、数時間手紙の返事を書いて、2時か3時には仕事を終えていた。「疲れて休養が必要なのに働き続ける人は愚か者だ」とカール・ユング(スイスの精神科医)は書いている。これはまさにモーツァルトのような人を指す。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)