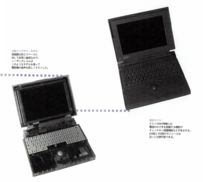訴求力のある製品やサービスを生み出すための問い
5. 自社が取り組もうとしている問題を、すでに解決した企業はないだろうか?
このような問いはアイデアの放棄を促すのではないかと思われるかもしれないが、実際にはその反対である。多くのイノベーターは、取り組みが独創的で難易度が高いというだけで評価されると考えているが、それは誤りだ。もちろん、イノベーションとは他と違うユニークな行為だが、それは顧客と自社に価値を創造するという点においてである。そして必要なのは、価値創造の最短距離を見つけることだ。スペインの偉大な芸術家、パブロ・ピカソの助言に従おう。「優れた芸術家は模倣するが、偉大な芸術家は盗む」。自社が取り組もうとしている課題は、他のだれかが別の状況ですでに解決している可能性が高い。別の業界、国、企業から示唆が得られるかもしれない。それを見つけて自社の問題解決の参考にできれば、イノベーションのスピードは劇的に向上する。
6. 世界中のほとんどの企業が成しえない何かを、自社は実現できるだろうか?
大企業がベンチャー企業のすさまじい速さに伍して市場でイノベーションを起こしていくことは、ますます困難になっている。そして速さだけでは不十分である。企業は、ブランドの信頼性、独自の流通チャネル、独占的な技術などを活用して、「速さ」よりも「巧さ」で勝負しなければならない。自社独自のケイパビリティに焦点を合わせれば、圧倒的な競争力を持つ製品やサービスを生み出す可能性は高まる。
事業アイデアを結実させるための問い
7. 仮説がどう失敗すれば戦略自体が崩れてしまうかを、想定しているだろうか?
どんなアイデアにも、正しいところと間違っているところがある。優れた事業コンセプトであっても、イノベーターがその誤った部分に気づかず素早く修正できなければ、市場への投入に至らず終わる。時間を短縮するべく、優秀なイノベーターは科学的な手法を用いる。仮説を検証するために、アイデアの最も不確実な部分を明確にして、実験を厳密に設計・実行するのだ。そして優秀な科学者と同じように、予想通りの結果と予期せぬ結果を同じように詳しく検証する。
8. どうすれば、より簡単かつ効率的に学ぶことができるだろうか?
実験を複雑で費用がかかるものにする必要はない。専門家に電話1本かければ、事業運営上の重要な仮説について何かが明らかになるかもしれない。アイデアを大雑把な形にした模型を顧客に見せれば、どの程度関心を持ってもらえそうかわかるだろう。資源を有効活用し、シンプルな方法で学ぼうとする努力が、ローンチにこぎ着けるか、その前に資金が枯渇してしまうかの分かれ道となる。
「無理に何かをしようとするな。ただそこに立っていろ」という格言がある。たとえば若い医学生に、ひとまず何もしないのが最善となる場合もあると教える時などに使われる言葉だ。症状の根本原因が明らかになる前に慌てて処置すると、かえって事態を悪化させることがある。イノベーションは積極的に追求すべきものであるのは間違いない。ただし同時に、ここに掲げた8つの問いをじっくりと考えてみてほしい。それによって取り組みの焦点が定まり、成功確率がぐっと高まるはずだ。
HBR.ORG原文:Eight Essential Questions for Every Corporate Innovator January 31, 2014
■こちらの記事もおすすめします
インテュイットは「最高の問い」で創造性を育む
イノベーションにまつわる10の迷信

スコット・アンソニー(Scott Anthony)
イノサイトのマネージング・パートナー。同社はクレイトン・クリステンセンとマーク・ジョンソンの共同創設によるコンサルティング会社。企業のイノベーションと成長事業を支援している。主な著書に『イノベーションの最終解』(クリステンセンらとの共著)、『イノベーションの解 実践編』(ジョンソンらとの共著)などがある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)