ビジュアル・イメージは必ずしも重要ではない
――ブランドのロゴの色やかたちをきちんと定めることが、ブランドを維持するうえで大切だと言われてきました。ところが、グーグルに代表されるように、最近はロゴの色やかたちを柔軟に変えている会社であっても、彼らのブランドは維持されています。こうした時代の変化をどのように捉えればよいのでしょうか。

ブランドのロゴそのものが重要というよりは、むしろビジュアル全体のイメージや背景にストーリー性を持たせ、そのストーリーを語ることが大切なのです。その戦略をしっかりと練って、よいものを打ち出せた会社が成功します。
リッツカールトンやベンツのように、ロゴ自体がステータスシンボルとなっている会社もあり、そこではまだロゴの重要性が保たれています。しかしその一方では、たとえばBMWの場合、ロゴを前面に打ち出すのではなく、ドライバーが運転を楽しんでいるシーンなどをあわせて描くことで、成功を収めています。
つまり、すべての企業にとってブランドのロゴが最重要なのかと言うと、常にはそうではないということが言えるでしょう。
――今回のサミットでは、アル・ライズ氏のプレゼンテーションに登場した「ビジュアル・ハンマー」という言葉が印象的でした。ただ、ブランドにとってビジュアルが大事とはいっても、いまの時代、本当にビジュアルだけで攻めることができるのかと疑問にも感じています。アーカーさんはどうお考えですか。
たしかに、アル・ライズさんが言うように、ブランドに非常に強力なビジュアル・イメージを打ち立てることで、成功している会社はたくさんあります。しかし、それが成功への唯一の道ではないと思います。強烈なビジュアル・イメージを持たなくても成功している会社はありますから。
――先ほどものお話にもあった、スイート・スポットもそのうちの一つですか。
そうです。消費者のスイート・スポットをつかむことが大切で、エイボンがやっている乳がん撲滅の活動はまさにそれです。エイボンにとって最も大切な活動だと思いますし、パンパースが育児や赤ん坊の世話を前面に打ち出し、単にオムツを売る会社ではなくて、育児をとても大切に考えている会社だと消費者に訴えて、成功していることがいい例だと思います。
――それがブランドの背景やストーリーをつくる活動につながるということですね。
ええ。ただ、パンパースのやり方はたしかにとても有効ですが、ほかのやり方もあります。それは、強力なブランドをつくるときに、一般の消費者がそのブランド名を聞いたときに何を思い浮かべるか、を考えることです。
たとえば、消費者がトヨタの〈プリウス〉というブランド名を聞いたときに、独特のスタイルをもった車であるとか、非常に燃費がいいということ、あるいはコンパクトタイプのハイブリッド車だということを思い浮かべるでしょう。さらに、非常にすぐれた技術によってつくられた車であり、化石燃料を最小限に抑えているのでCO2の排出が少なく、長期的に見れば世界を救うような車であるというイメージも持つはずです。
このように、〈プリウス〉という言葉を聞いただけでも、消費者は6つか7つくらいのイメージやストーリーを頭に思い浮かべます。それが強いブランドとして起こるべき現象ではないでしょうか。
――ただし、浮かぶべきイメージは消費者にとって好ましいものでなくてはいけませんね。
そうです。〈プリウス〉はまさにそこを目指していると思います。トヨタは、どこの会社の車にもできることではなく、〈プリウス〉だけが持つ特質であるということを思い浮かべてほしいと考えて、ブランドを構築しているはずです。
――時代によって消費者が好ましと思うイメージそのものも変わっていきます。それによってブランドも発するイメージを変えていくべきでしょうか。
そのとおりです。ブランド名を聞いたときに思い浮かべることやその重要性は、時代によって変化しますから、その点をきちんと押さえたうえで、ブランドのイメージ管理を行っていく必要があるでしょう。
次回更新は10月7日(火)を予定。
【書籍のご案内】
『ブランド論――無形の差別化を作る20の基本原則』(デービッド・アーカー:著、 阿久津聡:訳)
1994年に発行した『ブランド・エクイティ戦略』によって、マーケティングでのブランドの重要性が決定的なものとして認識された。その立役者は、著者のデービッド・アーカーである。その後、アーカー教授は、数々の書籍を執筆し、ブランド・アイデンティティ、ブランド拡張、ブランド・ポートフォリオなどの言葉を世に送り出してきた。本書は、そのアーカー教授の20年に及ぶ研究成果を初心者にもわかるようにコンパクトに紹介したもの。ブランドにかかわるすべての人が読むべき一冊。
ご購入はこちら
[Amazon.co.jp] [紀伊國屋書店BookWeb] [楽天ブックス]

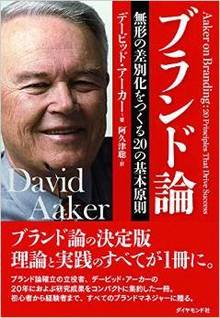





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









