プロジェクト運営を支えた「哲学」の力
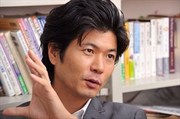
この「ふんばろう東日本支援プロジェクト」が構造構成主義という“哲学”をベースにした活動だと述べると驚く方も多いだろう。ここでいう“哲学”というのは、「私の人生哲学」や「経営哲学」といった「私の考え」といった意味での「哲学」ではない。そうではなく、構造構成主義とはニーチェやフッサール、ハイデガー、ソシュール、ロムバッハといった、いわゆるギリシャ時代から連綿と続く“哲学”における現象論、存在論、記号論といった諸領域の原理を体系化したものである。私はボランティアをするのも初めてで、会社やNPOなどの組織を経営したことはなく、実際、私の唯一の武器は「哲学」だけだったのである。
さて、「哲学」とは何だろうか。いろいろな考え方があるが、ここでは「前提を問い直す」ことと、「物事の本質を洞察すること」という主に二つの機能からなる「考え方」という位置づけで語っていきたい。事実、構造構成主義とは「方法とは何か」「理論とは何か」「価値とは何か」といった根本的な問いに答える理論の体系なのである。
今回はその中でも「方法の原理」を紹介していこう。言うまでもなく、マーケティングの方法、戦略立案の方法、人材育成の方法、あらゆる分野で「方法」は活用されている。通常、「方法」とは先生や先輩といった先達から、「これについてはこうこうこうするのがよい方法だ」という形で倣い覚えていく。そのためそれぞれの業界で「正しい方法」がある、と思うようになる。
たとえば、これは心理学でも同じであり、「こうやって実験したり統計を使ったりすることが正しい心理学の方法だよ」と教わると、「それこそが心理学なのだ」と思うようになり、それ以外のやり方は「そんなものは心理学ではない」と邪道扱いするようになる。多かれ少なかれ、我々はそうして正しい方法を手順として倣い覚える。しかし、だからこそ異なる方法を身につけた人達は必然的に正しい方法を巡る信念対立に陥ることになる。そしてその「正しい方法」が有効などころか足枷になっていたとしても、辞められないという不合理が起こるようになる。
そのような不合理に陥らないためにも、方法の本質を知る必要があるのだ。では「方法」とは何なのか。「方法の本質」、つまりその最も重要なポイントとは何なのだろうか。それに答える理論が「方法の原理」である。




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









