-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
変化の激しい現代、これまで通用していた前例が通用しない事態が増えている。しかし、失敗するリスクを恐れ、前例に囚われる組織は少なくない。組織が前例に囚われる理由を明らかにし、いかに変化を起こしていくのか考える。
組織が前例主義に陥る理由
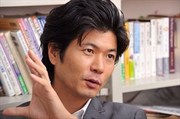
前回は、方法の原理が、埋没コスト(過去)に囚われることなく、状況(現在)と目的(未来)を軸に意思決定することを可能にすると論じた。しかしながら、行政や一定の歴史を経た企業によくみられる保守的な組織が、前例主義に陥ることなく臨機応変に対応するためには、さらなる困難が伴う。
組織はなぜ前例主義になるのか。その構造を把握し、そうした組織で新しい取り組みを進めるにはどうすればよいか洞察を深めていく必要がある。今回は、こうした観点から、「価値の原理」という新たな原理と、これまで論じてきたすべての方法に通じる原理である「方法の原理」のさらなる活用法を紹介しよう。
まず大前提として、我々は基本的に前例にならって仕事をしている、ということを自覚する必要がある。今している仕事を振り返ってみてほしい。仕事を始めた当初は効率が悪かったのものが、いつのまにか自分なりの手順を見つけ、意識しなくてもそのパターンでこなしているところはたぶんにあるはずだ。通常、前例にしたがうことは逐一考えずに自動的に行動できるため、すこぶる効率がよいのである。これは組織においても同じである。
方法の原理によれば、方法の有効性は、⑴状況と⑵目的に応じて決まるのであった。したがって、「前例にならう」という方法は、状況と目的によって良くも悪くもなる。一般的にそれは、目的と状況が変わらないときに機能することが多い。しかし、現代社会のように変化が急速で激しい状況においては、「前例」が機能しない可能性は高くなる。だからこそ今、前例主義の是非が問われているのだ。
ここでいう「前例主義」とは、過去に取っていた方法(前例)が機能しないにもかかわらず、それを見直すことなく踏襲し続けてしまう不合理のことを指す。したがって、成果が出ない場合、新たな方法を採用するならば、トライアンドエラーが機能しているということでもあり問題ではない。しかし、保守的な組織においては多くの場合そうはならない。実際、東日本大震災時、被災地では人数分に満たないという理由で、500人いる避難所では300枚の布団が届いたが配らない、800人いる避難所に700個のケーキが届いたが受け入れない、野菜を配らずに腐らせるといった事態が各所で起きた。これも前例が機能しないにもかかわらず「全員に同時に配る」という公平主義、平等主義を踏襲してしまった例ということもできよう。




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









