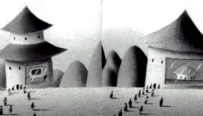イノベーションの意思決定において、黒白がはっきりすることはあまりない。薬効が発現しない、規制当局に却下された、というように断念すべき理由が明白なことも時にはある。市場テストの結果が抜群で、プロジェクトを全速で進めるべきなのは考えるまでもないケースも稀にあるだろう。だが多くの場合、次に取るべきステップとして説得力のある選択肢が何通りも考えられる。このまま計画を進めるか、データに基づいて手直しを加えるか、あるいは予想を下回ったので中止するか。
プロジェクトを支援する幹部は、不満気だった。この反応は、オペレーション上の判断における確実性に慣れている企業でよく見られるものだ。過去の経験に基づいて意思決定の盤石なルールができあがっており、討論や議論の必要がほとんどない。だからといって、彼らは勘に頼ってよいわけではない。イノベーションの意思決定の要諦を、以下に示そう。
●適切な方法で実験を設計する
まず検証すべき「仮説」を立てる。テストの具体的な「目標値」を設定する。何が起こるか「予測」を立てる(これは大まかな推量でかまわない)。そして、予測を正確に測定できる方法で「実行」する。
●公平な第三者に加わってもらう
不完全な情報に基づく意思決定に慣れている人物であれば、理想的だ。いわゆる「悪魔の代弁者」は、否定そのものを目的としているようにも見えるため、イノベーターの間では評判が悪い。だが、当事者が気づかないような弱点を正直に指摘してくれる人は、よい意思決定をするうえで非常に大事な役割を果たす。
●1つの事業アイデアの是非を、それのみで判断しない
1つのプロジェクトだけを考えていれば、それを進めるべき真っ当な理由をひねり出してしまうものだ。したがって、あるプロジェクトに投資すべきかどうかを検討するのではなく、イノベーションのポートフォリオを見よう。他のプロジェクトと比較して、「どちらに投資するほうが魅力的か」を考えるのだ。
●チームに意思決定を強制する何らかの制約を設ける
私が好んで設定する制約条件は、時間である。あえて短期間で決めるよう強制すると、チームには「とにかくアクションを起こそう」という強い観念が生まれる。これが有効な理由は、実際の市場に近づいてこそ最良の学びが得られるからだ。今回の医療サービスのプロジェクトでは、「市場テストをもう1度やってみる」という選択肢がある。その際にはもちろん、現在までに学んだことを参考にできる。したがって、2度目の市場テストに日程上の制約を設けても、早まった判断につながることはない。
そして実際、幹部が選んだのはこの方法だった。まず最初に、リソースを社内の他のプロジェクトに振り向けるべきかを検討したうえで、もう1度実験することを決めた。チームは最初のテストで学んだことを踏まえて修正し、今度は3カ月の市場テストを行った。すると結果は向上し、この会社は本格的な商業化に向けて次のステップへと進むことになった。
こうした意思決定の規律は、厳格だが実践が不可欠である。さもなければ、プロジェクトは保留状態になりイノベーションのサイクルが滞ってしまう。ある時点で断固とした決断をしないならば、それは失敗を免れない道を選んだのと同じことなのだ。
HBR.ORG原文:How to Market Test a New Idea September 3, 2014
■こちらの記事もおすすめします
デジタル・プロトタイピングで忘れてはならないユーザーの心理と感情
行動観察をイノベーションへつなげる5つのステップ

スコット・アンソニー(Scott Anthony)
イノサイトのマネージング・パートナー。同社はクレイトン・クリステンセンとマーク・ジョンソンの共同創設によるコンサルティング会社。企業のイノベーションと成長事業を支援している。主な著書に『イノベーションの最終解』(クリステンセンらとの共著)、『イノベーションへの解 実践編』(ジョンソンらとの共著)などがある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)