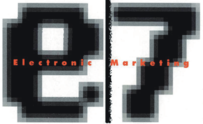(1)経営陣の1人ひとりとじっくり話し合う
これは当たり前と思うかもしれないが、CEOや事業部門長をはじめ主要幹部たちと関係を築いて自社の戦略を理解することは、決定的に重要である。イノベーションの方向性とプロジェクトを、全社の目標に合わせるためだ。
LGエレクトロニクス、シンガポール・テレコム、TEコネクティビティなどで戦略とイノベーションを主導してきたブラッド・ガンビルによれば、最初の100日間は「馬鹿げた質問をして、その事業の基礎をマスターする」ためのよい期間だという。特に「内部の人にとっては当たり前でも、部外者にとっては明白ではない事柄」に焦点を当てるよう勧めている。したがって、意思決定会議がどうしてその方法で行われているのか尋ねたり、戦略やプロジェクトの遂行方法に疑問を呈したりすることを恐れないでほしい。
特に重要なのは、次の2点に関する幹部たちの考えを理解することだ。(1)自社が成長目標を追求するうえで、イノベーションはどんな役割を果たすのか、(2)イノベーションを主導するあなたの役割は何か、である。
既存事業に磨きをかけ拡大することが求められているのか。それとも自社の業態や属する業界を再定義することが役割なのか。経営陣があなたに期待しているのは、新たな成長事業を生み出し育てていくことだろうか。それとも既存のプロジェクトチームを指導することなのか。あるいは新しいアイデアが社内からどんどん生まれてくるような、イノベーションの文化を築くことだろうか。
経営トップらと話し合うにつれ、自分のイノベーションの仕事と既存事業との関係がわかってくるはずだ。
幹部たちは、イノベーションを推進するために自部門の人員や予算を手放すつもりはあるだろうか。社内や社外からメンバーを集めて、新しいイノベーションチームをつくってよいのだろうか。それとも専用のリソースが与えられず、無から有を生むような働きが期待されているのか。
自社の人員や組織の構成、業務プロセス、ロードマップを大きく変えるような提案をしたら、幹部たちは支持してくれるだろうか。それとも、目立たないように変えていくべきなのか。
(2)イノベーションの最大の障壁を特定する
前述の質問を経営陣に尋ねても、答えは人によってさまざまだろう。幹部たちの意見が一致しない部分こそ、イノベーションの主導者にとって最も喫緊の(そして多くの場合、最も根本的な)課題であり、チャンスでもある。
したがって最初の100日間のできるだけ早いうちに、社内で断絶が見られる部分を把握する必要がある。特に注視すべきは、目立たないが自社の戦略を真に決定づけている3つの要素である。(1)どのプロジェクトに資金と人員がどう配分されているか、(2)業績はどう測定され、報酬と結びつくのか、そして(3)会社全体で予算はどこにどう配分されているのか。
会社の予算配分や報酬の実態が、経営陣の言う優先事項と一致していない部分を探ろう。それがわかれば、長期計画を達成するうえでの最大の障壁、そして短期的な回避策が必要となるものを特定できる。
(3)自分の意図を明確に、かつ柔軟に示す
最初から、すべての答えを完全な形で用意しておく必要はない。だが「イノベーションのリーダーとして、全社戦略の達成にどう貢献できるのか」については、着任したその日から見解を持っていなければならない。
すでに進行中のイノベーション案件については、その範囲を拡大させる方法を検討しよう。その際にCEOやCTOに対して、その職域を侵すつもりはないことを理解してもらい、彼らの支援を引き出す必要がある。
ガンビルによれば、こうした信頼関係を築く良い方法は、解決策や代替案を示さないまま問題点を指摘するのを避けることだ。「CEOの周囲には、問題点を指摘する人たちは大勢いる。重要なのは、1日も早く問題解決者としての自分を確立し、良き相談相手として経営陣に認めてもらうこと」であるという。
新規アイデアの創出、他部門のプロジェクトの支援、全社的なイノベーション文化の醸成――これらのバランスをどう取るかを考えよう。これらはお互いに関連するが、やるべき仕事はまったく違う。最初の自分の見解にこだわりすぎず、個々の案件に合った方法を柔軟に採用していこう。
(4)自社を取り巻くイノベーションの状況について見解を持つ
ウォルグリーン、キャンベルスープ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ウェイトウォッチャーズなどでイノベーションと戦略を主導してきたコリン・ワッツは、「顧客の発想や視点に基づいて、自社の市場を明確に定義すること」を推奨している。
一般に企業は、「提供する製品」や「参入している分野」で自社の市場を定義しがちだ。しかし顧客は常に、自分の課題を解決してくれる最良の方法を探しており、その解決策がどの業界やカテゴリーのものかは気にしない。顧客がどのように製品やサービスを選んでいるかを理解すれば、従来とはまったく別のライバルたちが見えてくることが多々ある。そして自社の市場も役割も再定義され、事業の成功条件も変わってくる。
またワッツは、隣接分野をよく見ることで市場を形成できる可能性があると言う。「もはや単独で存在する市場はない」。イノベーションのレンズを通して周囲を見れば、自社の中核事業が見落としたかもしれない変化の兆候に気づきやすい。
(5)短期と長期の取り組みから成るイノベーション・ポートフォリオの第一案を作成し、素早い失敗による損失も想定しておく
あなたの主な職務は当然ながら、一連のイノベーションの取り組みを前に進めることだ。
すでに進展しているプロジェクトもあれば、今後の展開を待っている事業アイデアもあるだろう。あるいは社員の頭の中に、荒削りな構想があるかもしれない。いずれにせよ、着手すべき取り組みを最初の100日間で明確にする必要がある。
そこにはかなり具体的なもの、例えば新たなテクノロジー製品に最も適した市場の特定なども含まれるかもしれない。あるいは、より幅広い事業機会の探索かもしれない(単に「ウェアラブル」など)。特定の組織能力の開発でもよい。ワッツが「今後長きにわたって見返りが得られる投資」として勧めるのは、「アイデアや製品を素早く安価で試験できる組織能力」の構築だ。
賢明なイノベーションリーダーは、これから探求を始める長期的な取り組みに投資する一方で、早期に結果を出して信頼を得るために短期的な事業機会にも取り組む。
もしイノベーションのポートフォリオに短期的なプロジェクトしかなければ、中核事業に携わる人々の一部は、「イノベーション部門ではなく自分たちの事業部で手掛けてはいけないのだろうか」と疑問に思うだろう。そしてそのポートフォリオでは、最もエキサイティングで破壊的なアイデアが見落とされている可能性が高い。だが反対に、もし長期的な案件しかなければ、その実現に向けて長らく取り組んでいるうちに、自社の忍耐力が途切れてしまうリスクがある。
そして早期の成功を望むならば、速やかに失敗し、損失を被ることを避けてはいけない。真のイノベーションに求められるのは、失敗を恐れず、そこからの学びに価値を見出すことである。
とはいえ、失敗は誰にとっても怖いものだ。1度の損失がイノベーションのパイプライン全体に悪影響を及ぼすことのないよう、十分な数の案件を進行させておこう。1つの取り組みを「素早くやるのも、安くやるのも、手堅くやるのもいい。だが3つすべてはできない」とワッツは言う。失敗が明らかになったプロジェクトの中止を初めて決める時、支援してきた幹部とあなたはその決断を、堂々と誇りを持って宣言しよう。
これらを100日間でやるのは大変だと思われるだろうか。その通りだ。イノベーションには組織を前向きに変革する力があるが、たやすいものではない。
HBR.ORG原文:The Chief Innovation Officer's 100-Day Plan September 17, 2014
■こちらの記事もおすすめします
イノベーションを現実に動かしたトムソン・ロイター6つの実験
イノベーション・オーガナイザー:ジョブズのような組織をつくる

スコット・アンソニー(Scott Anthony)
イノサイトのマネージング・パートナー。同社はクレイトン・クリステンセンとマーク・ジョンソンの共同創設によるコンサルティング会社。企業のイノベーションと成長事業を支援している。主な著書に『イノベーションの最終解』(クリステンセンらとの共著)、『イノベーションへの解 実践編』(ジョンソンらとの共著)、新著に『ザ・ファーストマイル』がある。

ロビン・ボルトン(Robyn Bolton)
イノベーション戦略を専門とするコンサルティング会社、イノサイトのパートナー。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)