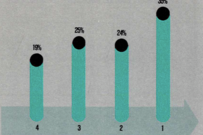ジェイコブスのアプローチ

鳥山 正博(とりやま・まさひろ)
立命館大学ビジネススクール 教授
専門は、マーケティング戦略、マーケティングリサーチ、エージェントベースシミュレーション。国際基督教大学卒(1983)、ノースウェスタン大学ケロッグ校MBA(1988)、 東京工業大学大学院修了、工学博士(2009)。1983より2011まで株式会社野村総合研究所にて経営コンサルティングに従事。 主な著書に『社内起業成長戦略』(マグロウヒル 2010 監訳)「企業内ネットワークとパフォーマンス」(博論 2009 社会情報学会博士論文奨励賞) 「エージェントシミュレーションを用いた組織構造最適化の研究 : スキーマ認識モデル」(電子情報通信学会誌 2009)などがある。
コンピュータや通信の発展、そしてグローバル化により企業組織や組織風土は変わらざるを得ない。しかしケースメソッド方式は、強固なピラミッド構造の伝統的な米国企業のあり方が無意識の前提となっており、こうした時代の変化に対応しているとはいえない。その前提のもとでは、優れた上司は、部下が用意した情報に基づき果敢に意思決定を行い、それを組織に徹底させることができるということに他ならず、経営者が避けるべき最大の問題行動は「優柔不断」であった。そこで、まさに強固なピラミッド組織の中にあっての良い管理者の条件となる2点(意思決定力と説得力)を鍛えるのがケースメソッドであったのだ。
では、時代が下るとどんな組織になるのか。それには、西海岸のハイテク企業群をイメージすれば良い。現代に生きる我々にはわかることだが、強固なピラミッド構造の組織から、よりフラットでカジュアルな組織になり、プロジェクトやクロスファンクショナルチームで仕事をすることが増え、外部の人たち、すなわちITベンダー、ベンチャーキャピタリスト、コンサルタント、提携先、アウトソース先、フリーランスの専門家、大学の研究者等と仕事をすることが格段に増えた。また、海外とテレカンファレンスをしながら仕事をすることも増えた。
そのような中で、自らゴールを見つけ、立場と行動原理の違う多様な人たちを巻き込んで成果を出すようなリーダーシップが求められるようになった。また何より働き方や必要とされるスキルが激しく変化するようになった。
この変化をジェイコブスがどこまで正確に予見できていたかは知る由も無いが、少なくとも従来型の強固なピラミッド組織は崩れ、働き方やリーダーシップのあり方が変わることを確信していたに違いない。変化を先取りし対応するには、従来型の単なる実務家でなく、超一流の理論的な若い頭脳を採用し、現実とのぶつかり合いの中で変化を起こしていくべきであると考えたのだ。
そこで雇われたのが、若手で一流の数学者、統計学者、経済学者、社会学者、行動科学者などである。問題は、彼らに象牙の塔の中に閉じこもらせずに、いかに経営者と深い話をさせるか、また、それに基づいていかに新しいカリキュラムを開発させるかであった。そのためのインセンティブと補助する仕組みが必要だった。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)