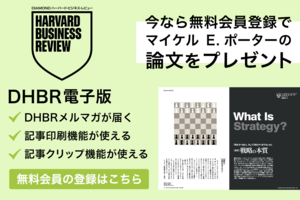◆アンバランスの勝利
1989年、東欧の共産主義体制が倒れはじめたとき、西側諸国の有識者たちは安易な説明に飛びついた。資本主義が勝利した──そう主張したのである。しかし、それはとんでもない間違いだった。その誤解がいま大きな不幸を生み出している。
1989年に勝利を収めたもの、それはバランスだった。共産主義体制の国々は、政府セクター(部門)に権力が過度に集中し、著しくバランスを欠いていた。それに対して西側諸国は、政府セクター、民間セクター、そして言うなれば「多元セクター」の間のバランスが十分に取れていた。しかし、この点が正しく理解されていなかったために、その後、多くの国でバランスが失われていった。民間セクターの力が過度に強まったのである。
◆私たちが担う多元セクター
社会にとって重要な三つのセクターのうちで最も理解されていないセクター──政府セクターでも民間セクターでもないセクター──は、「非営利セクター」「第三のセクター」「市民社会」など、さまざまな不適切な呼び名を与えられてきた。本書では、このセクターがきわめて多様な団体で構成されていることを表現するために、「多元セクター」と呼ぶことにする。この呼称なら、政府セクターと民間セクターに並び立つ存在としてイメージしやすいだろう。
さまざまな財団や宗教団体、労働組合、協同組合、多くの一流大学や一流病院、グリーンピースや赤十字のような非政府組織(NGO)……。政府が所有しているわけでも、民間の投資家が所有しているわけでもない団体、言い換えれば、政府セクターにも民間セクターにも分類できない団体が数多く存在する。メンバーが所有している団体もあるが、ほとんどの団体は、誰によっても所有されていない。このなかには、容認しがたいと感じる状況に抗議する社会運動(ソーシャル・ムーブメント)や、好ましいと考える変化を起こすために、たいてい少数の人が主導して始まる社会事業(ソーシャル・イニシアチブ)も含まれる。前者の例としては、「アラブの春」の民主化デモ、後者の例としては、再生可能エネルギーの普及を目指す活動などが挙げられる。
存在感のある活動をしている団体も多いのだが、多元セクターは驚くほど注目されていない。左対右の大論争のなかで埋没していたからだ。
多元セクターは、政府セクターと民間セクターの中間に位置するわけではない。政府セクターと民間セクターが両端を占める直線上に存在すると考えるべきではないのだ。政府セクターと民間セクターがまったく性格の異なる領域であるように、多元セクターもこの両セクターとはまったく違った領域なのである。
バランスの取れた社会は、三本の脚に支えられた椅子のようなものだ。一本の脚は、国民に尊敬される政府に土台を置く政府セクター。私たちは、そうした政府に保護されている面が大きい(警察機能や規制など)。もう一本の脚は、責任ある企業を基盤とする民間セクター。私たちはそうした企業に、雇用の多くと、商品やサービスの大半を依存している。そしてもう一本の脚は、強力なコミュニティを舞台に形成される多元セクター。私たちは、このセクターのさまざまな団体に帰属意識を抱くことが多い。