――人材マネジメント改革には大きなエネルギーが必要です。企業は何から始めるべきでしょうか。
牧岡 人材マネジメントの運用に空白は許されませんので、現状、動いている仕組みを使いながら変革をスムーズに進めるには、まずは社員への影響や運用工数はできる限り抑えていくことを考えなければいけません。
そのためには、いきなり全体を変えるのではなく、全体的には現状の仕組みを回しながら、部分的な見直しをかけて実績を作り、はずみをつけて大きな変革に向かっていくやり方を採ることです。例えば、採用の選考プロセス自体は変えずとも、選考の中で見るべき視点を変えることは、比較的簡単にできます。
また、評価においては、評価基準・制度自体は変えずとも、フィードバックの仕方を変えるなど、まずは部分的な変更であるけれども、制度・仕組みの肝となる部分を変えることで、変革の効果を出すことができます。
植野 具体的には「部分的改善でも効果がでやすいポイント」をとっかかりとするという視点から、次の3つのポイントに着手してはどうでしょうか。
まずは、ハイパフォーマーの評価や登用に、これまでと違ったデータを用いてみることです。多くの企業でハイパフォーマーを定義し、評価に組み込んでいると思いますが、これまでは業績結果をもとに、学歴や過去の経歴に共通項がないかを見つけるものでした。「海外経験」や「若くしてマネジメント経験あり」などの情報から好業績を残す社員に共通項を求めるものです。
しかし、これではハイパフォーマーの資質や行動まではデータ化することができません。ハイパフォーマーの行動をデータ化するのには、これまではコンピテンシー診断などの多くの工数が必要でしたが、今は社内SNSでの発言・投稿行動や過去のトレーニングデータなど、非構造化データの分析によっても導き出すことができます。
次に、トレーニング体系の見直しです。これまで、日本企業では入社3年目や10年目といった決められた勤続年数で実施する階層別の研修が主体でしたが、近年欧米の多くの企業で活用されているMOOC(Massive Open Online Course)などのオンライン研修を用いて、個人のニーズによりいつでも受講できるようにすると同時に、頻度が上がった研修が職場でのパフォーマンスにしっかり結びつくよう、上司やメンターなどによるフィードバックやコーチングをタイムリーに行っていくことです。これは既存の制度を大きく変更しなくても実施可能です。
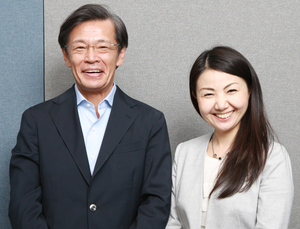
そして最後に、社員のパフォーマンスを高めるためのエンゲージメント向上の施策です。社員は、「成長機会」「職務」「共に働く人」「組織」「報酬・承認」など、さまざまな要素で複合的に企業を評価し、モチベーションを上下させています。これをEVP(Employee Value Proposition)と呼びますが、前に述べた通り、必ずしも金銭的な報酬がすべてではないことが重要なポイントです。
また、これらの要素は、職種はもちろん、社員のライフステージによっても変化していきます。人材セグメントごとに、このEVPの向上策を人材マネジメントの仕組みに織り込む検討を行い、社員の表彰制度や人事面談などに生かす、採用サイトのメッセージを変えるなどの打ち手であれば、比較的かけるエネルギーや混乱するリスクを抑えつつ、早く改革の一歩を踏み出せます。
(構成/河合起季、撮影/宇佐見利明)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





