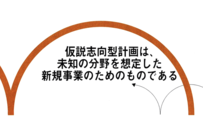ロビンソンとチェンバレン:
不完全競争の議論に見るポーターの源流
ポーターのファイブ・フォース分析とは、(1)企業間競争、(2)売り手の交渉力、(3)買い手の交渉力、(4)新規参入の脅威、(5)代替品の脅威という5つの力を理解することによって、自社が属する産業や戦略グループの構造的な収益性を分析できるという考え方である。
ポーターはさらに、その構造下における最適な「ポジショニング」を取ることで競争優位を確立できるという。その基本的なポジショニングは3つ存在する。1つ目は、他社に対してデザインや性能など商品特性で優位に立とうとする「差別化戦略」。2つ目は、他社に対して価格面で優位に立とうとする「コストリーダーシップ戦略」。3つ目は、それら差別化戦略やコストリーダーシップ戦略を顧客の範囲を絞って提供する「集中戦略」である。これが、ポーターの基本戦略と呼ばれる戦略の方向性である。
当然ながら、ポーターは突如としてこうした結論にたどり着いたわけではない。その基本的な考え方は、それより遥か以前に誕生したものである。そのため、その発展の経緯をひも解くことは、ファイブ・フォース分析を真に理解するためには不可欠である。
ロビンソンの議論は何をもたらしたか
不完全競争がなぜ生じるのか。この問いの答えを探究することこそ、ファイブ・フォース分析に続く原点である。
この議論の始まりは、19世紀に始まる経営者の時代(第3回参照)、すなわち近代的大企業が登場した時代に遡る。技術進化と市場成長、大量生産と大量販売に後押しされ、一部の企業は市場原理に影響力を行使できる規模にまで拡大した。その結果、市場メカニズムに影響される多数の市場参加者の行動が産業の競争状況を決定づける、という従来の考え方が、必ずしも当てはまらない状況がいくつも生まれる。少数の企業が市場に対して支配力を行使し、その動態を決定づける状況が観測され始めたのである。
このような現実の市場の構造に着目し、不完全競争の理論をもたらした初期の代表的人物は、ジョーン・ロビンソンであろう。
ロビンソン以前の時代、すなわち完全競争を前提とした時代は、価格とその背景に存在する産業構造は所与のものと仮定しており、企業や個人がどのような行動を取ろうと、それは変化しないことが前提であった。これは、1つひとつの企業がまだ小規模であり、産業全体に影響をもたらしえない状況下では、納得感のある説明であったと言える。
この理解のうえで、完全競争では、個別企業は自由に販売量を決定できる一方で、少しでも財の価格を引き上げようとすれば一気に需要がゼロになる、とされていた。これは、個々の企業が直面する需要曲線(以下、需要曲線と呼ぶ)は水平であるという前提につながる (図1参照)。
需要曲線が水平である状態は、企業行動と産業構造(それが反映される残余需要)が切り離された状態ともいえる。こうした状況下で、企業は産業構造を所与の要件としてとらえると理解されており、企業は、与えられた環境に応じてその行動を定める存在であった。
図1:完全競争の需要曲線

出典:筆者作成
それに対して、ロビンソンが1933年に記した『The Economics of Imperfect Competition(不完全競争の経済学)』[注4]では、現実の市場では顧客が分散して存在するため製品の提供に輸送費がかかること、そして、顧客は使用する製品に対して一定の信頼を置くことなどから、財の価格が需要量に対して一定にならない状況があるとした。
完全競争が想定するように、一定以上に商品の価格を上げると需要が一気にゼロになるような状況は、消費者の数が限られ、かつその商品に対する信頼や愛着があれば考えにくい。また、商品自体の価格をある程度引き下げたとしても、分散する消費者に商品を届ける輸送費を考えれば、需要が一気に増大することも考えにくい。そのため、個々の企業が直面する需要曲線は、財の価格を上げれば減り、下げれば増える形となりうる。さらに、不完全競争下における需要曲線は、新規参入や代替品の普及などによってその形を変える。
このようにロビンソン以降は、よりダイナミックに変化する需要曲線の性質を扱い、それに対して企業の数やその財の特性などが直接的に影響する、という議論が積極的に展開されるようになる。
こうした前提に立てば、企業は自社の利潤を最大化させるために、市場の需要に対する価格の曲線と、自社の供給に対する費用の曲線の分析に基づき、自社の行動を最適化させる。たとえば図2は、不完全競争の最も極端なケースである、独占市場における需要曲線と企業の費用と収入の関係性を示したものである(より厳密なものは経済学の教科書を参照していただきたい。ここではその基本的な発想だけを解説する)。
図2:不完全競争の需要曲線と企業行動

出典:著者作成
供給量を増やすほど財の価格が下がるのであれば、企業が販売量を増加させることで追加的に得られる収入は低減する(限界収入)。その一方で、企業が販売量を増加させるための費用は、規模の経済効果で減少するものの、一定水準以上では、むしろ技術的な困難などで上昇すると考えることすらできる(限界費用)。この場合、企業の最適な生産量は限界収入と限界費用の交点で定まる。追加的な収入と、それを実現するための費用が一致するまでは、企業は追加的な利潤を得られるが、それ以上になると赤字を垂れ流すことになるからである。
ここで重要なのは、企業の経営戦略が「市場の需要曲線の性質にも大きく左右される 」ということである。すなわち、ロビンソンの説明を現代から再解釈すれば、外部環境を分析することから経営戦略を検討すべき、という考え方の源流を発見することができる。
ロビンソンはさらに、需要曲線の性質、すなわち生産量を通じて企業がどの程度価格を支配できるかは、その財を生産する企業の数と財の代替品の有無に左右されると説明する。その説明は、競合の数と代替品の脅威が市場特性(需要曲線の性質)を定め、それが企業の最適な行動を決定づけると解釈できる。
これは、ファイブ・フォース分析における5つの要因の2つ、競争環境と代替品の脅威と大きく重なる。つまり、ロビンソンの議論には、ポーターのファイブ・フォース分析の源泉が存在するのである。
チェンバレンの議論は何をもたらしたか
ロビンソンと同時期に不完全競争の議論を展開した経済学者として、エドワード・チェンバレンにも言及する必要がある。彼の1933年の著作『The Theory of Monopolistic Competition(独占的競争の理論)』[注5]は、限られた数の寡占的企業、すなわち近代的大企業が取りうる「競争戦略」を主題とした最初期の作品である。
前述の通り、チェンバレン以前の経済学では、企業は与えられた環境に応じて、受動的にその行動を最適化させるという暗黙の前提を置いていた。それに対してチェンバレンは、企業が経営環境に応じて能動的に行動しうるという説明を展開している。つまり、企業が経営環境の分析を通じて自社の行動を決定するのみならず、主体的に経営環境の特性に影響をもたらすべく、戦略的な行動を取ると主張した。
たとえば、市場構造の特殊性と消費者の不完全性ゆえに、企業は広告支出を増大させる等の施策を通じて、他社と差別化する手段を選択するようになるという。チェンバレンは、当時の米国企業が広告宣伝に熱を入れていた状況を観察することから、寡占企業が不完全競争を繰り広げる状況では、必ずしも企業は受動的な存在とはならないと理解するに至ったのだろう。企業は販売費用(Selling cost)を能動的に増加させることで、総需要を増加させ、また顧客に自社のブランドを優先的に選択させることができると彼は言った。
さらにチェンバレンは、そうした差別化によって、個別企業が市場の需要曲線の位置や形状に影響を与えられると説明する。需要曲線は市場参加者全体の行動の総和であるが、自社のみが他社より安い価格を提供することは可能である。それが実現すれば、一時的にせよ自社の販売量だけを増大できる。さらに、財の低価格化を通じて一部の企業の市場退出が生じるのであれば、結果的に自社のシェアを増大させることも可能となる。
これは、個別企業による戦略的行動を意味している。自社の基本戦略としての差別化と低価格化。ここにも、ポーターの競争戦略の源流を見ることができる。なぜなら、ポーターが説く3つの基本戦略のうちの2つは、差別化と低価格化であるからである。
産業組織論は不完全競争の議論から発展を遂げた
産業構造は企業の利益率に影響を与える。
これは産業組織論のごく基本的な理解である。ロビンソンとチェンバレンに代表される不完全競争の議論は、その後、産業構造とそれに伴い変化する企業行動の細緻な分析へと進化していった[注6]。
完全競争の市場では、自由競争によって多数の競合が乱立しているため、業績は一定以上には向上しない。その状況では、企業間の競争の結果として社会的厚生が最大になる可能性はあるが、激しい競争で企業の業績は頭打ちとなる。それは、利潤を最大化できるのは競争が存在しない独占市場であり、企業にとってはできる限り競争のない産業構造が好ましいということを示す(表1)。
表1:産業構造の分類の例

出典:ジェイ B. バーニー『企業戦略論 上』(岡田正大訳、ダイヤモンド社、2003年、p. 117)を参考に著者作成
そして、そうした理解から次第に、市場や産業の構造を自社に有利に導きうるという議論が完成されていった。当初は所与の要件として考えられていた市場や産業の特性も、企業行動が影響を与えうるもの、企業が選択しうるものとして解釈されるようになったのである。
当初、こうした理論的な発達は経済学の世界にとどまっており、経営学の世界との間には議論の断絶が存在していた。しかし、産業組織論で蓄積された知見が、1970年代の終わりから経営戦略の世界に突如流入し始める。その口火を切ったのは、ハーバード大学で産業組織論を研究していた経済学者のグループであり、そこで博士号を取得したのちに同校のビジネススクールに職を得た、若かりし頃のマイケル・ポーターであった。
[注5]邦訳は『独占的競争の理論』(青山秀夫訳、至誠堂、1966年)
[注6] ここで解説したのは、あくまで初学者のための初期的な議論である。より厳密な理論と、戦略に対する経済学の議論の進展については、Besanko D, Dranove D, & Shanley M. 2016. Economics of Strategy. Wiley: Hoboken. (邦訳『戦略の経済学』、ダイヤモンド社、2002年) などが参考になる。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)