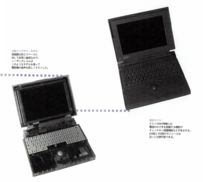「ブレスト」は、成果に結びつかない
入山:いま、多くの日本企業では、イノベーションを起こすには「ブレイン・ストーミング(ブレスト)」が有効だと信じられています。事あるごとにブレストが行われ、結局イノベーティブな発想が生まれず、バーンアウトしている(燃え尽きている)現状は見過ごせません。
ブレストでイノベーションが起こりにくいことは、スタンフォード大学のロバート・サットン教授も指摘しています。彼が以前『アドミニストレイティブ・サイエンス・クォータリー』誌に発表した論文では、多くの心理学者がこれまでにさまざまな実験を行い、ブレストの効果に関する調査を進めた結果、あまりうまくいかないという事実がわかったと結論付けています。なぜなら、ブレストでは参加者が自由に思っていることを発言していいというルールがありますが、実際には心のどこかで「これは言ってはいけない」という他者を気にする心理的なブレーキがかかり、結局は言いたいことをすべて吐き出すことが難しいからです。
しかもブレストでは、誰かが話しているときはそれを聞かなければなりません。誰かの話を聞いているときは、自分の思考が停止してしまうのです。ブレストで順番に誰かの話を聞かなければならない状態だと、自分の思考にとって時間の無駄になってしまうのです。
ナップ:ブレストを足掛かりに、新たな思考が構築される面もないわけではないので、ブレストに効果がないと断定することはできません。
ただ、私がグーグルでブレストをした限りでは、確かにブレストでイノベーティブなアイデアを生み出すことは難しいという実感を得ました。アイデアの始まりは、浅いものであったり、抽象的なものであったりするものです。それを「種」として、長い時間をかけてじっくりと考えたほうがいいこともあります。
しかしブレストでは、1人でじっくりと時間をかけて考えたアイデアが、反射神経によって出てきたアイデアに負けてしまうことがあります。本来であればイノベーションに育つかもしれないアイデアが、そこで潰されてしまうことさえあるのです。
入山:おっしゃる通りです。優れたアイデアを生むためには、一人ひとりがじっくりと考える必要がありますね。
ナップ:ただし、健全な競争は大切だと思います。それぞれがより強い考えをじっくりと考え、それらをぶつけ合い、平等に戦わせるのです。グーグル時代、あるソフトウェアのデザインをしているときに、「こうしたらうまくいくから、やってみてほしい」という指示を出したことがあります。私が1人でじっくりと考え、仕組みをつくり、プロジェクトのメンバーにその通りにやってもらったのです。
本当は、メンバーとして参加していたエンジニアやマーケターの中には、私より優れたアイデアを持っている人がいたはずです。そのアイデアを私のアイデアに組み込むためには、彼らにもアイデアを生み出すプロセスに参加してもらったほうがよかった。そのほうが手遅れになりません。
スプリントでは、チームを構成して難題に取り組みます。このように、スプリントが効果的な点は、同時にみんなで作業することができるところです。さまざまな役割のメンバーが参画することが大切なのです。









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)