特長⑤アダプティブな人材・組織
環境変化に応じた戦略・ビジネスモデルシフトに、人材・組織を俊敏にトランスフォームできる組織
新たなデジタルビジネスモデル・戦略の青写真を描くことができても、それを実現するためには人・組織を変えない限り、絵に描いた餅・失敗に終わる。これまでの既存事業の枠組みのなかでの戦略シフトにおいては、人材・組織シフトは大きな問題ではなかったが、既存事業のパラダイムを超えたデジタルシフトにおいては抜本的な人材・組織のシフトが求められる。
たとえば、デジタルビジネスやスマートファクトリーを立ち上げようとしてもデジタル人材(例:データサイエンティスト)が自社にはほとんどいない。日本でデータサイエンティストを採用するのは至難の業で、採用できたとしても多くのプレミアムを支払わないといけない。どうやってデジタル人材を獲得・育成・処遇・リテインしていけばよいのか、というのは経営者の頭痛の種になっている。
この難題の一つの解としてデジタル人材を有しているプレーヤーとのアライアンスがある。たとえば、アクセンチュアはGE、ミシュラン、KDDI等のクライアント企業とデジタルビジネスのJVを設立してきたが、アクセンチュアのデジタル人材を投入し喫緊の事業の立ち上げをしながら、デジタルトランスフォーメーション・アカデミーと呼ばれるデジタル人材育成プラットフォームも活用しながらクライアント企業のデジタル人材を育成し、段階的にフェードアウトしていく手法を取っている。
もう一つデジタルトランスフォーメーションで陥りやすいのがオペレーション軽視の罠である。デジタル事業に関連する文化、ケイパビリティは前回も触れたように、Bitで構成されるデジタル領域は一見少数のデジタルスター人材がレバレッジを効かせて事業創出するように見えるが、その実膨大な労働集約的なオペレーションに裏打ちされていることが多い。
GoogleやFacebookのようなデジタル先進企業の新たな新事業の裏では、膨大なオペレーションが動く。たとえば、不正広告や不正動画のチェック、大多数の外部クラウドソーサーやパートナーの管理、定則チェック。さらにAIの導入に際しても、初期の大量教師データの作成のために、大量の人員投下が必要となる。これらの作業は、表層で消費者の目に留まるデジタルサービスの裏側で動く必須作業だ。
さらに、それをグローバル共通品質で運用するとなると、各国法規やカルチャーへの対応も求められ、その工数は膨大となる。上述の企業たちは、そのようなオペレーション作業の外部化を、コア機能の獲得と同様に欠かすことのできないピースとして重要視する。のるかそるかわからないデジタル新事業のオペレーションは徹底的に外製化することでリスクを担保し、同時にコア業務にリソースを集中投下することで、「リーン」と「タイミングを見極めた爆発的成長」を達成しようとしている。
さらに、コアファンクションすら外部化する事例も登場している。今年アマゾンに買収された高級スーパーWhole Foods Marketは自社のコアファンクションである宅配機能をクラウドソーシングで買い物代行を行うInstacartに委託した。日本で同様の提携が進みつつあるが、GMは自律運転での移動市場の創出に向けてスタートアップのLyft提携。FacebookはMessenger serviceのローンチ後80日でその目玉機能の一つであるボットを約1万1000件投じたが、外部の開発リソースを利用している。
このように多くの先進企業が「リーンマネジメント」と「爆発的な成長」という一見相反するデジタル事業の成功ドライバを外部ネットワーク化、パートナリングで達成しようとしている。日本企業の行きすぎた内製主義は、デジタル事業の推進に際しては大きな足かせとなることもある。スキルの賞味期限が30年から5年に短縮されたといわれる昨今、デジタル最前線で戦ううえでは人の調達の面でも、既存理論の枠組みを超えるべきだ。
* * *
日本企業がVUCA・デジタルディスラプションを勝ち抜いて、グローバルの価値創出競争のメジャープレーヤーとして復活するカギは、自己変容する組織:Living Organizationへ変革することであることを本稿では申し上げた。
実際、デジタルビジネスの未来の青写真を描いた経営者は、描いてみて初めて人材・組織を変えないととてもその絵は実現できないことに気づき、人材・組織のトランスフォーメーションに着手している。
まずは自社の未来のビジネスの青写真とそれに至る戦略を描くことがないと何も始まらない。そのうえで、企業によって本稿で論じた5つのポイントのどこに大きな課題があるかを見極めて、何から手をつけていくかのロードマップを定め、トランスフォーメーションを進めていくことが肝要である。
しかしながら、根源的に最も重要なのは、自社を守ってきた免疫機能をディスラプトするだけの勇気と覚悟を経営が持てるかどうかにある。それがないと既存事業のしがらみに圧し潰されてトランスフォーメーションは成功しない。東京オリンピックに向けて好業績が見込まれ変革原資のあるここ2~3年に、自己変容できるかどうかが日本企業の命運を分けるであろう。
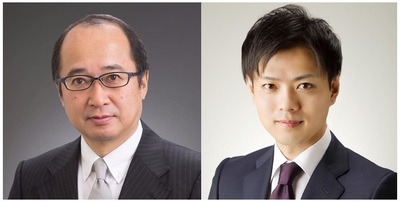
宇佐美 潤祐
アクセンチュア 戦略コンサルティング本部
人材・組織変革統括 マネジング・ディレクター
(写真右)
倉嶋 佑理
アクセンチュア 戦略コンサルティング本部
シニア・マネジャー




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





