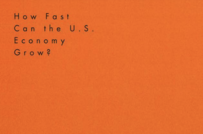強みは業務の標準化と
医師とのネットワーク
――他社との違いを教えてください。ウェルビーの強みは、どこにあるのでしょうか。
私たちの一番の強みは、マニュアルをもとに、どの事業所においても、またどの利用者に対しても、均一の品質を持つサービスの提供ができていることです。設立初期の段階からマニュアルをしっかりと作り込み、さらに毎月、現場からの声を吸い上げて更新してきました。内容を会得してもらうため、マニュアルテストを全スタッフに実施して、合格点が取れなかったスタッフは本部に呼び出して受かるまで追試します。
それによってスタッフの仕事を標準化したことが、当社の成長の大きな要因でしょう。このマニュアルは当社の命ともいえるものですから、 タブレット端末に収め、時間が来ると読めなくして持ち出しができないようしっかり管理しています。
――業務プロセスの標準化になぜそこまでこだわられたのでしょうか。
それには良品計画の松井忠三元会長の『無印良品は、仕組みが9割』(角川書店)という本との出会いがありました。メガネチェーンのJINS、田中仁CEOが「無印良品の成功はきちんとしたマニュアルをつくったことにある。うちでも推進したい」と絶賛されたことを耳にして、私も読んだところ、感銘を受けました。すぐに現場の事業所のトップや本部の社員に本を買い与えて、2回ずつ読んできなさいと命じたほどです。
当社も早速、プロジェクトチームを設置してマニュアルづくりを始めました。もともと上場経験から内部監査の重要性も理解していたので、同時に内部監査室も設け、各事業所がマニュアル通りの運用をしているかどうか監査して徹底させました。現在もその仕組み通りの運営をしています。
――ただ、心の悩みを抱えている利用者と向き合う仕事だけに、なかなかマニュアル通りとはいかないのではないでしょうか。
もちろん、利用者によって症状はまるで違いますから、臨機応変さが求められます。原則的な対処法はマニュアルに書いてありますが、個別の対応は現場に任せることになります。
そのため、地域で関わっている方々との連携が重要になります。利用者を支える仕組みが地域ごとあり、医師や地域のサポートセンター、行政などが集まって会議をして、本人とも話し合いながら就労までの支援を進めていきます。会議ばかりでなく、日常からコミュニケーションを密にして、利用者のいまの状況のフィードバックに力を注いできました。そうした一種の営業活動が功を奏して、支援者たちの信頼を高め、利用者が自然と集まる仕組みが作れました。
特に精神科医とのつながりは当社の大きな強みです。たとえば、若手精神科医の方々が集まる会合に毎回呼ばれて参加しています。そこで知り合った先生たちの勉強会にも出席しています。
この6月からは、九州大学名誉教授で、日本精神神経学会理事長の神庭重信先生にも当社の社外取締役に就任いただきました。
医師は治療が進み社会復帰可能と判断できても、就職までの道筋を持ちません。そこで私たちに紹介いただくことになるのです。そのネットワークによって新たな地域に出店した場合にも近隣の精神科医を紹介してもらえ、すぐにサポート体制が作れます。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)