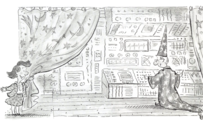妊娠喪失の苦しみ
妊娠中や出産時、あるいは出産直後に子どもを失うことによる打撃は、あまりに大きい。日々の生活に支障が出たり、対人関係に消極的になったりするケースもあるし、精神をかき乱されたり、感情が失われたりするケースもある。
研究によると、妊娠喪失を経験した人は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、抑鬱、不安、睡眠障害に陥りやすい。たいてい1年も経てば症状が解消するが、強い悲しみが長引く人もいる。
そのような状態は「複雑性悲嘆」と呼ばれる。罪悪感に苛まれたり、子どもがいる人を羨んだり、苦痛が続いたりする人が少なくない(特に最初の子どもを妊娠喪失で失った人は、自分が「親」であると位置づけづらく、悲しみと辛さにいっそう拍車がかかる場合もある)。
流産や死産を経験した女性は、情緒的な苦しみだけでなく、肉体的な苦しみも味わうことが多い。ときには、それが何週間も続いたりする。検査や治療を続ける必要がある場合は、そのたびに悲しい経験を生々しく思い出させられる。
見落とされがちだが、パートナーも大きな苦しみを味わう。パートナーの同僚たちは、その人が大きな喪失を経験したことを知る機会がない場合もある。研究によれば、特に男性は自分のパートナーを支える役割を期待されるため、みずからが悲しむ機会をほとんど得られず、あまりいたわってもらえない。
妊娠喪失を経験した人たちは、職場でも思いがけないときに、ちょっとしたきっかけで、悲しみがこみ上げてくる。しかも、同僚たちのぎこちない振る舞いにも苦しめられる。
ある男性は、職場でエレベーターに乗ると、妊娠中の同僚にあとずさりされたと感じた。「私と近づきたくないかのようだった。死産が感染するとでも言わんばかりに」と、この人物は私たちに語った。同僚女性は気を使ったつもりだったのかもしれない。しかし、男性はそうは感じなかったのだ。
私たちは以前、職場で人々がどのように死を経験し、それに対処しているかを研究したことがある。そのとき、死をタブー扱いする西洋文化の傾向が、仕事の場ではいっそう強まるという指摘をよく耳にした。
子どもの死、とりわけ出産前の死では、死をめぐる沈黙がいっそう重苦しくなり、当事者に悲痛な思いをさせる。死による喪失感は、それがなかったことのように扱われると、いっそう強まることが多い。周囲の人がまだ妊娠を知らない段階でお腹の子どもが失われたケースでは、特にそのような状況になりやすい。その場合、当事者は一人で悲しみに向き合わなくてはならなくなる。
これとは逆に、個人的な苦しみを他人に知られることが辛い人もいる。死産の場合、同僚たちが最後に見たのは、大きなお腹を抱えた妊婦の姿だったかもしれない。このようなケースでは、子どもを亡くした人は同僚にどう話せばよいかわからない場合もある。同僚たちも、どう接すればよいか自信を持てないことが多い。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)