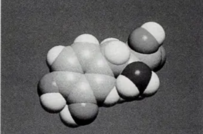-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業業績を損益計算書だけで判断することが難しくなっている。GAAP(一般に公正妥当と認められる企業会計の基準)による報告だけでなく、非GAAP利益やプロフォーマ利益と呼ばれるように、自社独自の基準による利益を報告する企業が増えているからだ。GAAPが万能な基準とはいえないだ、自社の業績を少しでもよく見せするためにGAAPを用いないのであれば、それも問題である。本稿では、非GAAP利益やプロフォーマ利益の利点と弊害を明らかにする。
ある会社が黒字か赤字か――この点は、経営者、投資家、銀行関係者、その会社の取締役にとって重大な関心事だ。投資家は黒字企業の株式を購入したいと考えるし、銀行もそのような会社に融資したいと考える。
しかし、こう言うと驚くかもしれないが、ある会社が黒字か赤字かという問いに答えることは、次第に難しくなってきている。損益計算書に記される損益の金額は、さまざまな数字が差し引かれたり、調整されたりしたうえで算出される。そのため損益計算書の数字を見ても、その会社のコア収益性は明らかにならない。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)