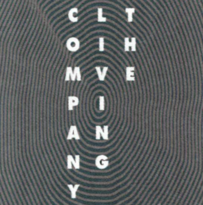マネジャーへの教訓
デジタル勤務でチームのメンバーが無理をするかもしれないことや、変則的な働き方をすることを、マネジャーは考慮しなければならない。
同じ成果を上げるために、場合によっては、より多くの時間が必要になるかもしれない。あるいは昼夜を問わず、社会的な結束や接触があまりない時間帯に1人で働くと、作業時間の長さがより負担に感じられるかもしれない。
チームのデジタルワークの指針で勤務時間やオーバーラップに関する決まりを確立することにより、これらの課題に取り組むことができる。具体的には次のようなポイントがある。
・集まる時間をつくる:チームの50%以上がオンラインで一緒に仕事をする「集合タイム」を決める。今回のデータでは、メンバーの半数以上が常時オンラインにいる時間は平均で7時間以上あった。これらの時間に合わせて、オーバーラップが増えることが利点となるプロセスのスケジュールを組み、グループ全体に影響を与えるような意思決定を下し、それを伝える機会にする。
・オーバーラップを強制しない:チームのオーバーラップが7時間連続しない場合や、常に50%以上のオーバーラップを達成できない場合も、気にする必要はない(今回のデータでも、オーバーラップには1日4~10時間の幅がある)。どのチームにも、オーバーラップが少ない時間帯に、個別に行うのが最適と思われるプロセスがある。
・スケジュールを細かく管理しすぎない:メンバーが自分の好きなタイミングで業務を遂行できるように、スケジュールに柔軟性を持たせる。今回のデータでは、ほとんどのチームのメンバーが、1日のうちでそのプロセスを最も効率的に処理できる時間帯に自然に仕事をしているようだ。
・ログオフさせる:メンバーが仕事に集中できる時間と空間を確保するための指針を決める。これには2つの形がある。1つは「ヘッドダウン」(集中)時間、つまり、特定の時間帯はチームミーティングを行わず、メンバーはどうしても必要な時以外は連絡を取り合わない。もう1つは「声をかけないで」サインをつくり、個人が集中する必要があるタイミングを周囲に知らせる。
デジタルワークの指針は固定しないこと。チームがデジタルコラボレーションの経験を積むにつれて、定期的に(たとえば各四半期の初めに)見直す必要がある。
マネジャーはデジタルワークの負担の削減にも努めなければならない。これは、リモート/ハイブリッドワークでは特に重大な課題となる。マネジャーがオフィスを歩き回ったり、負担削減の持続的なプログラムに基づいてチーム管理上の直感を働かせたりすることができないからだ。
労力を物理的に削減するためには、プロセスの末端で働くメンバーがどのような仕事をしているか、その仕事は構造化されたプロセスと構造化されていないプロセスがどのくらいの割合で構成されているか、そしてプロセスの改善やユーザートレーニング、自動化、基本的なITアプリケーションの更新など、複数のレベルでどのように改善できるかを、客観的に評価する必要がある。
マネジャーは、定期的な遡及的評価(デジタルワークの指針の一部に含める)や、社内外の業務コンサルティングチームの活用、あるいはデジタル環境におけるチームの働き方を理解するためのコンピュータサイエンスを応用した新しいツールを通じて、洞察や知見を再編成することができる。
* * *
リモートワークはすでに浸透しつつあり、それに伴いコラボレーションと生産性に新たな課題が生じている。
今回の調査では、リモートワークは「終わりのない」1日であり、生産性は時間帯を問わず向上して、従業員が孤立する時間もあるという、これまでの観察を裏づける結果となった。一方で、1人で仕事をすることは生産性の向上にもつながる。多くの場合、1日の時間帯によってタスクをうまく割り振っているようだ。
筆者らの分析は、チームのオーバーラップに関する指針を確立することの重要性を強調するとともに、リモートワークがもたらす現実的および心理的なマイナス面に対処する簡単な戦略を提案している。このような研究を通じて、パンデミックから学んだ教訓をもとに、ビジネスオペレーションを改善し、長期的には働く人にとってより持続可能なものにすることができる。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)