インシビリティはバーチャル環境で増幅される
職場のインシビリティに関する筆者らの研究が示唆するように、ほとんどの人が何かしら不作法を経験しているが、有色人種やLGBTQIAなど疎外されているグループの従業員は、より頻繁に経験している。
さらに、米国で働く有色人種にとって、バーチャル環境でのインシビリティは大きな懸念を生んでいる。話を遮られる、言い逃れをされる、遠回しに嫌味を言われるなどはすべて、インシビリティの一例だ。オンライン環境では、不作法な振る舞いがさらに容易になる。物理的な距離があるため、互いに離れているように感じ、問題行為が目に見える影響をもたらすこともほとんどない。
組織は従業員が受けた無礼な経験を軽視しがちで、さらに悪いことに、「ここではそういうやり方をする」と見なす。多様性のある労働力にとって重大な問題は、こうした些細な経験が、それを受ける側の仕事やメンタルヘルスに悪い影響を与えることだ。インシビリティが日常的になると、社会から疎外されている人々は自分たちが尊重されていない、価値を認められていないことの合図だと受け止めて、その組織を去るかもしれない。
インシビリティは、曖昧だからこそダメージにつながる。つまり、相手を軽視するような振る舞いに傷つける意図があるかどうか、不明瞭な場合が多いのだ。
たとえば、筆者らが話を聞いたある医療機関の従業員は、患者のケアについて詳しく説明するメールの最後に「わかりましたか?」と書かれていた、と振り返った。これを自分の知性が疑われていると受け取る人もいれば、単純な質問として読む人もいるだろう。インシビリティの曖昧な性質が解釈の余地を残している。
不当な扱いの理由がはっきりしない場合、従業員は自分に原因を求める内的帰属(私が何かしたのだろうか、能力がないと思われているのではないか)に陥りやすく、自信喪失、自尊心の低下、反すうに至る。
これは婉曲的な偏見として、あからさまな差別と同じように、従業員にも組織にもダメージを与える。あからさまな差別は容易に外在化する(彼は性差別者だ、彼女は人種差別主義者だ)。さらに、わかりにくい差別は組織の方針に則って特定し対処することが難しく、疎外されているグループの従業員には慢性的なストレス要因になりやすい。
バーチャルオペレーションへの移行は、すでに職場で排除されていると感じている従業員の不安を増幅する場合もある。バーチャル会議でのわかりにくい対人メッセージは、自分の意見が評価されている、自分の居場所があると受け止める人もいれば、ミュートにして聞かないほうが賢明な人もいる。
オフィスの廊下や休憩室、エレベーターでの偶然の出会いが少ない、あるいは存在しないため、バーチャル会議が組織との唯一の具体的なつながりだという人もいるだろう。インシビリティの対象になった人は社会的サポートを見つけにくく、より孤独を経験することになる。
インシビリティは目立たない
研究によると、インシビリティを上司に報告する従業員は1~6%にすぎない。これはある意味で当然とも言える。会議中に発言を遮られたと正式に報告すれば、ちょっとしたミスに過剰反応していると思われかねないのだ。
しかし、こうしたインシビリティを単独の経験として捉えるのではなく、侮辱的な行為のパターンを特定して、多様なバックグラウンドを持つメンバーのコミットメントや満足度、パフォーマンスを蝕む過程を明らかにする必要がある。
たとえば、ジョンは昨日の会議であなたの話を遮っただけでなく、前回の会議でも同じようなことをした。その前には彼の上司が、重要なメールからあなたを外したこともあった。最近の研究によると、こうした敵対的なやり取りは従業員にとって不快で腹立たしく、自分の価値を下げられていると感じさせる。
インシビリティを組織に報告しない場合、自分でどのように対処すればよいか。最も一般的な対応は、インシビリティの行為者(扇動者)を避けることだ。ただし、研究が示唆するように、扇動者を避けることも立ち向かうことも、その後のインシビリティを減らすことはなく、受け手側(ターゲット)に選択肢はほとんどない。
差別的なインシビリティの場合、相手に立ち向かうということは、既存の力関係に反して誰かの偏見的な扱いを非難するということだ。インシビリティは微妙で曖昧であるがゆえに、扇動者から過剰反応なトラブルメーカーだと非難されるかもしれないと思えば、ターゲットは立ち向かうというリスクと不快感をあえて選ぼうとはしないだろう。
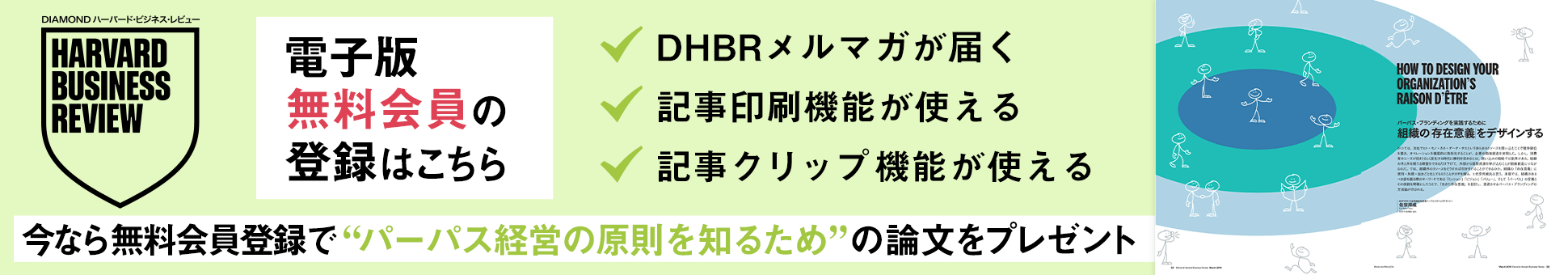




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









