なぜ従業員に自律性を与えるのか
単に「従業員が求めているから」という理由以外にも、従業員に自律性を与えるべき十分な根拠が存在する。
1985年、米国の心理学者リチャード・ライアンとエドワード・デシが、当時主流だった「人間を動機づける最大の要因は報酬だ」とする考え方に対して、疑問を投げかける理論を発表した。彼らの「自己決定理論」は内発的動機づけ、すなわち内なる心理的欲求に駆られて成長を求める自律的な動機こそが、人間の成功と充足感の最も基本的な触媒であると主張した。
ライアンとデシによれば、自己決定権があるという感覚は3つの要素、すなわち、自律性、有能感、関係性から成る。彼らは、ここでいう自律性とは「みずからの人生において、行為の原因・主体になりたいという欲求」だと定義した。
従業員により大きな自律性を与えることを自己決定権の推進だと考えれば、従業員の満足感、充足感、そして仕事に対するエンゲージメントの拡大を期待できる。なぜなら、そこでもたらされる結果は、本人固有の能力の結果として受け止められる可能性が高いからだ。同様に、もっと優れた働きをしたいという内発的動機としての役割も果たす。
だからといって、報酬や福利厚生といった外発的動機づけは不要である、あるいは効果がないというわけではない。もちろんライアンとデシも、みずからの画期的な研究について、何らかの「報酬」を求めていただろう。
しかし、このように「管理された」動機は、エンゲージメントや「よい仕事」を追求するうえで、中心的な役割を果たす心理的要因にはならない。従業員が、柔軟に働けることを給料や福利厚生よりも重要だと感じるのは、まさにこのためだ。
つまり、自律性はモチベーションに欠かせない要素であり、パフォーマンスとウェルビーイングを牽引する重要な原動力といえる。
自律性と柔軟性の関係
これまでも幾度となく指摘されてきたことだが、ハイブリッドワークにすべてを解決できる万能薬はない。実際、自分たちにとってどのような働き方が最善なのか、それぞれの組織が判断できること自体が、ハイブリッドワークの最も魅力的な特性の一つかもしれない。
そうした中でも、「自宅勤務と出社勤務のハイブリッドだが、1週間に出社しなければいけない日数が決められている」のが、最も一般的なモデルになりつつある。これは、アドビ、シティグループ、グーグルをはじめとする多くの大手グローバル企業が、このハイブリッドワークモデルを強力に推進していることと関係しているかもしれない。
とはいえ、ハイブリッドワークを構築する方法は、ほかにも数多く存在する。そして、さまざまなモデルを整理する最も簡単な方法は、従業員がいつどこで働くかではなく、それを自分自身で決められる自律性がどの程度あるかに注目することだろう。
従業員が望ましいとする柔軟性を確保するためには、どの程度の自律性を認めるべきだろうか。これを理解するために、筆者らは以下のピラミッド構造を考案した。これは現在、世界で最も一般的になっている働き方を、自律性と柔軟性のレベルに応じて整理したものだ。
自律性=低、柔軟性=低:全日出社勤務が義務づけられている。
自律性=低、柔軟性=中:在宅勤務と出社勤務のハイブリッドだが、どの日にどちらの勤務方法をするかは会社が決める(たとえば、マーケティング部門は月曜日と水曜日の出社が必須で、火曜日と木曜日と金曜日はリモートで働かなければならない)。
自律性=中、柔軟性=中:複数の場所で仕事をすることができるが、最低限の出社日数(週ベース)が決められている。
自律性=中、柔軟性=高:全日リモートワークが義務づけられているが、どこで働くかは自分で選ぶことができる。
自律性=高、柔軟性=高:いつどこで働いてもよく、会社のオフィススペースを全日利用することもできる。
組織から高い自律性を与えられている従業員は、その性質上、仕事に地理的制限が課されていないため、高い柔軟性を得ることができる。
ただし、高い自律性を認められている従業員全員が、さまざまなロケーションで働くことによって、その柔軟性を行使するとは限らない。単に、そうしたいと思えばできるというだけだが、組織から低いレベルの自律性しか与えられていない従業員には、そのような選択の余地はない。
コロナ禍でリモートワークへの移行が進んだ結果、組織では「自律性=中、柔軟性=中」というハイブリッドワークモデルが、最大の広がりを見せている。これも驚くべきことではない。なぜなら、従業員に完全な自律性を認めることと、フルタイムの出社勤務を義務づけることの中間に位置する、相応の妥協点だと見なされる可能性が高いからだ。
しかし、データが示しているように、従業員は自律性を行使することによって柔軟性を得たいと考えているのであり、自律性が認められない場合には転職もいとわない。このように従業員の自律性を最大化することは、職場の福利厚生ではなく、組織として競争力と妥当性を維持するために欠かせない要素となりつつある。
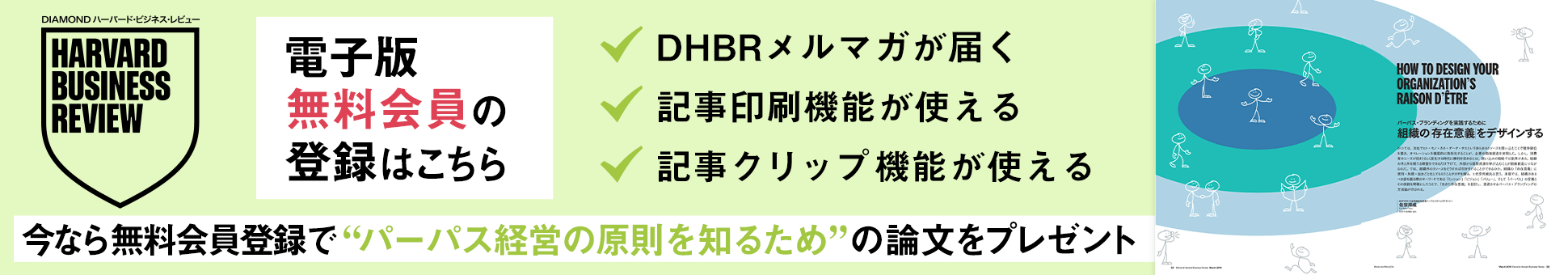





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









