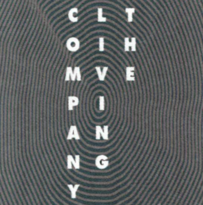●目標は「一つの数字」ではなく、「一定の範囲」で設定する
解釈の余地を残さない単一の目標を設定することは、長年、一般的だった。たとえば、「純利益成長率10%」「EBITDA成長率7%」「市場シェア15%獲得」というものだ。このアプローチは、予測可能で不安定性の少ない世界では、極めて有効だった。しかし、絶え間なく変化する世界では、そうはいかない。
では、どうすればよいのか。
「純利益成長率10%」という単一の数字の代わりに、市場に対応した範囲を決定するための有意義な議論をすることだ。たとえば、分析結果を参考に「8~12%」という範囲を決める。あるいは「市場シェア15%」という単一の数字目標を掲げるのではなく、「12~18%」「11~17%」というように一定の範囲を設定することで、チームに柔軟性を与えつつも、注力すべき目標から離れることなく、原理原則を守ることができる。
目標に幅を持たせることの効果には、科学的な裏付けがある。経営思想家のスティーブ・マーティンは、次のように説明している。
「フロリダ州立大学の研究者らは最近、目標設定におけるこの小さな変化が、いかに素晴らしい影響を与えるかを実証した。ある研究では、週2ポンド(約0.9キロ)の減量を目指す減量クラブのメンバーを、『週2ポンド減量』という単一の数字を目標とするグループと、『週1~3ポンド減量』という平均値は同じだが目標に幅を持たせたグループのいずれかに振り分けた。
幅のある目標を設定されたことが、メンバーの目標達成に対するモチベーションの維持(10週間の追加プログラムへの登録)に与えた影響は顕著であった。単一の数字で減量目標を設定されたグループの中で、減量の取り組みをより長期的に継続した人は半数に限られたが、幅のある減量目標を設定されたグループでは、その割合は80%近くに上った」
筆者らの実地研究でも、この科学的データを裏付ける結果が得られた。加えて、数字に幅を持たせるもう一つの利点も明らかになった。それは、目標設定をめぐって古くから存在する、組織の「上層部」と「下層部」の争いを解決することだ。
取締役会が高い目標を掲げると、チームはその目標を非現実的なものと考えることが少なくない。その結果、すべての関係者が目標達成までの道のりに不満を抱き、いら立ち、最悪の場合は完全にやる気を失ってしまう。
目標を一つの点ではなく、一定の範囲として考えることで、環境の変化に適応するための柔軟性が生まれる。目標の範囲を慎重かつ明確に設定することが重要であり、そして、実際に達成した数字がその範囲のどこにあっても、それを称えることが欠かせない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)