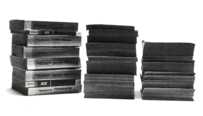5. ESG投資は死んでも、ESG投資制度は死なず
米国では、右派によるESGへの反発(「アンチ・ウォーク」運動の一環)が波紋を広げている。
フロリダ州は、巨大資産運用企業ブラックロックがESGと気候変動対策、ステークホルダー資本主義を支持していることに抗議して、20億ドルの資産を引き揚げた。テキサス州は、化石燃料企業や銃器メーカーへの融資を減らした銀行に対し、州政府との取引を禁じた。
サステナビリティの促進に携わる非営利団体Ceresのミンディ・ラバーの言葉を借りれば、こうした反発は「気候変動に配慮したビジネスは、財務に対する現実的な懸念に付帯しているものに過ぎず、イデオロギーに左右されている」というフィクションに基づいている。実際には、気候変動とクリーンテックは企業に巨大なリスクとチャンスをもたらす存在であり、収益性と将来性に大きな影響を及ぼす。投資家は、そうしたリスクを理解し、アセスメントに取り入れるべきだ。
もっとも、ブラックロックのような世界的な資産運用企業にとっては残念な話だが、並行して、別の角度からもESGへの反発が生じている。ESG投資という急成長分野の一貫性と透明性を高めようという動きである。
規制当局やNGOは、銀行がESGに配慮した投資を行っていると主張しながら、データや証拠を提示していない点を問題視してきた。あるドイツ銀行の子会社では、CEOがESG投資をめぐる「グリーン・ウォッシング」の容疑でEU当局の捜査を受け、辞任に追い込まれたほどだ。
ESGの定義の厳格化に伴い、17兆ドルとされてきた米国のESG関連商品の資産を8兆ドルと試算し直した研究もある。究極的には、精度を高めることになるため、こうした調整は望ましいものだ。
一企業の内部で、ESG投資をめぐって見解が錯綜するケースもある。HSBCではサステナブル投資の責任者が、サステナブル投資に強く「反対」を表明し、「気候変動は我々が懸念する必要のあるリスクではありません」と訴えた。
この人物は停職処分を受け、その後、会社を去った。そして、HSBCは化石燃料業界への主要な融資をいくつか停止すると発表した。
HSBCと同様、2022年には多くの投資企業がESGの推進に本気で乗り出した。世界でも最大規模のノルウェーの政府系ファンドは、ネット・ゼロカーボン目標を設定しない企業、トップに過剰な報酬を支払っている企業、取締役会の多様性に欠ける企業に反対票を投じると発表した。フランスの巨大金融企業アクサも同様の約束をした。また、小売企業セインズベリーズに対して、生活水準の維持に必要な賃金を支払うよう働きかけた投資家グループもあった。
6. サステナビリティ関連の基準や規制の頭文字が企業を席巻
ESGの評価をめぐって、大規模な仕組みづくりが進展している。サステナビリティに関するグローバルスタンダード──つまり、社会問題が自社のビジネスに与える影響について企業が何を報告しなければならない(または報告すべき)か──が急激に広がっている。
次々に押し寄せる質問に圧倒されてしまう企業もある。あるサステナビリティ担当役員は、2022年のサステナブル・ブランズ・カンファレンスで「ESGの調査表を記入している間に、地球は燃えてしまいます」と語った。
それでも、データや指標、基準が必要なのは間違いない。当てにならないように思えるかもしれないが、世の中を回すには基準は必須だ(安全性や耐火性の基準に達していない製品を買いたいだろうか)。
5で述べたように、ESG投資の世界は目下、混沌としている。その原因は、企業のリスクスクリーニングに焦点が当てられ、企業がより持続可能で、再生可能で、ネットポジティブか(環境負荷を埋め合わせ、さらにプラスの効果を生み出すか)という点がさほど注目されていないためだ。明確な定義は困難で、投資家がレーティングのために企業に尋ねる質問もばらばらだ。
こうした状況はある程度、予想通りといえる。突き詰めれば、現在使用されている3種類の主要な財務書類──貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書──は、何世紀もかけて、いまの形に進化してきたのである。
この課題への取り組みとして最も注目すべきは、グローバルな会計基準の設定に携わるIFRSが2021年に創設した国際サステナビリティ基準審査会(ISSB)だ。ISSBの基準はあまり効果的ではないという声もあるが、批評家やそのほかのステークホルダーがISSBに情報を提供しており、基準は今後も進化し、改善されていく可能性が高い。
その一方で、ISSB基準はすでに広がりつつある。2022年には中国、ナイジェリア、英国をはじめ多くの国で正式に採用され、大企業にISSBの基準を満たすことが義務付けられた。今後、中小企業向けの基準も登場することは確実だ(2021年には一部のプライベートエクイティ企業が独自の基準を作成した)。
7. 透明性の向上が続き、グラスボトムボートが海を行き交う
透明性は強大なパワーを持つ超巨大トレンドであり、テクノロジーや規制、規範の変化を含む多くの要因によって生み出されている。
テクノロジーによって透明性が高まった一例として欠かせないのが、極めてクールで、不気味さも伴う公開データベース「クライメート・トレース」だ。クライメート・トレースは炭素排出問題に取り組むいくつかの非営利組織がグーグルのフィランソロピー部門であるGoogle.orgから資金提供を受けて開発したものである。ウェブサイトが2022年11月のCOP27で発表された。衛星データとAIを活用して8万件近い温室効果ガスの排出源をマッピングしている。
たとえば、地図を拡大・縮小しながら、中国のすべての発電所を表示してみよう。ブラジルとペルーのボーキサイト鉱山やアルミニウム工場を調べることができ、それぞれの排出拠点の推定排出量が示される。宇宙から排出量を測定されてしまったら、地域コミュニティや規制当局の目を逃れることはできないだろう。
さらに、規制の透明性も加速している。スイスは2024年から、大企業に対して気候変動に関する情報開示を義務付ける計画を明らかにした(そのためには基準が必要だ)。
また、米国証券取引委員会(SEC)も新たな報告要件を提案している。この計画では、企業はスコープ1(事業所内での排出)とスコープ2(送電線経由で購入した電力による排出)の両面で炭素排出量を測定・公表する必要がある。SECによれば、スコープ3(サプライチェーンと顧客による排出)も間もなく導入される予定だ。
2022年に開催された多くのサステナビリティ関連イベントで筆者が耳にしたのも、このスコープ3の話題だった。企業は活用可能なデータの不足を懸念しているが、そのギャップは埋まりつつある。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)