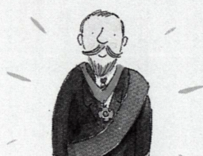8. 持続可能でない顧客を切り捨てるようにと、
2022年、PR大手エデルマンの全社会議で、従業員から「なぜ、うちの会社はエクソンモービルやシェルの仕事を受けるのか」という「鋭い質問」が飛び出した。
こうした社内圧力が加速する背景には、一部の賢いNGOの存在がある。クリーン・クリエイティブはPR企業や広告代理店に化石燃料企業との取引を止めるよう働きかけ、クライメート・ボイス(筆者は同社の役員を務めている)は、気候変動対策を支持するよう会社に圧力をかけたい従業員を支援している。また、グリンプスは、大手代理店で働く若い「クリエーター」が声を上げるための支援をしている。
直接的に大規模な炭素排出を行っていない企業──代理店やコンサルティング企業、銀行などのサービス業──は長年、自社を低排出企業とみなしてきた。しかし、銀行は融資を通じて膨大な炭素排出に関わり、コンサルティング企業や広告代理店は、誰の成長と成功を後押しするかについて、みずから選択していることが明らかになってきた。
若い世代の従業員が労働力として活躍するようになると、働く意義と雇用主の責任をより強く求めるようになる。筆者は2022年、ある大手コンサルティング企業のパートナーから、どのようなプロジェクトや企業の仕事を受けるかについて方針を定めなければ、優秀な人材を採用できないという話を聞いた。
9. ネット・ゼロ、そしてその先を目標に掲げる企業が増加
2050年、あるいはさらに前倒しで、炭素排出量を「ネット・ゼロ」とする目標を掲げる企業(フィンランドなどの国も)が増加しており、なかには、アップルのように自社のサプライチェーンまで含める企業もある。2022年半ばまでに、大手上場企業700社がネット・ゼロ目標を設定した。これは2年前より68%多い。
「ゼロ」の定義はカーボンオフセットを含めるか否かによって異なるが、企業は目標を設定し、行動を起こし続けている。重要なのは、重工業の分野で前進が見られたことだ。メキシコのセメックスは、代替燃料だけで操業する新たなセメント工場の設立を発表し、インドの鉄鋼大手タタ・スチールは水素を使って製造する鉄鋼「グリーン・スチール」をフォード・モーターに販売する。
このように高い目標を掲げる企業が多いなか、奇妙な例外もある。バンガードは、資産運用会社に排出量の実質ゼロ化を促す業界イニシアティブ「ネット・ゼット・アセット・マネジャーズ」(NZAM)から脱退した(参加企業の運用資産は計65兆ドルに上る)。運用資産10兆ドル規模の類似の枠組み「ネット・ゼロ・アセット・オーナー・アライアンス」は、2030年までに排出量を半減させると約束している。
バンガードに続く企業が出てくる可能性はあるが、多くはないと筆者はみている(自信はないが……)。今のところ、企業はネット・ゼロの目標を掲げているが、ある調査では、反発を避ける意味もあり(5参照)、目標を公表しない企業が4分の1に上る。この現象は一部で 「グリーン・ハッシング 」と呼ばれている。
10. イノベーティブで楽しいアイデアが満載
2022年の印象的なエピソードは何百もあるが、そのなかでも筆者の心をつかんだものをいくつか紹介しよう(パッケージ関連の話題が多い)。
・「ピンク税」(女性向け製品は男性向け製品より割高になる)を軽減すべく、CVSがタンポンを値下げした。
・マサチューセッツ州で、電気スクールバスの一団が、夏の電力ピーク時に送電網にエネルギーを逆供給した。
・バルセロナで学生が抗議運動を行い、気候変動教育を義務化するよう大学組織に働きかけた。
・ウォルマートが製品に含まれる有害化学物質を3700万ポンド削減した。
・マークス&スペンサーが詰め替え可能な掃除・洗濯関連商品の試行品を売り出した。
・ターゲットが使い捨て包装を減らす取り組み「ターゲット・ゼロ」を発表した。
・ホテルグループのIHGとユニリーバがホテルの客室で使用する使い捨てミニボトルを廃止した。
・ティンバーランドが「アップサイクル」用にブーツの返却を呼びかけた。
2023年を予測する
水晶玉で未来を見通すことはできないが、2023年について予測できることを以下に挙げよう。
・政治色が強く、捏造が多い「アンチ・ウォーク」運動が消え去ることはない。
・ゴッホの絵にスープを投げつけるといった、若者主導の気候変動への抗議運動が注目を集め、拡大する。
・「労働者はどこに消えてしまったのか」という問いが、引き続き先進国市場を苦しめる(理由として、新型コロナウイルス感染症による死亡、コロナ後遺症、感染不安による出社拒否、移民の減少などが挙げられてきた)。
・格差問題と、超富裕層による権力の行使方法について疑問が高まる(イーロン・マスクのツイッター買収がよい例だ)。
・エネルギー市場は極めて不安定な状態が続く。
・クリーンテック・エコノミーの議論の論点が、成長を支えるために必要なインフラに移行する。
・米連邦最高裁や州議会が再び権利を制限し(特に女性の権利)、企業は対応を迫られる。
・選挙が極めて重要であることは変わらない。
2023年も、サステナビリティが2歩前進したと思ったら、半歩後退し、さらに横にも何歩か動く、といった具合に激動の1年となることだろう。
"2022: A Tumultuous Year in ESG and Sustainability," HBR.org, December 21, 2022.





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)