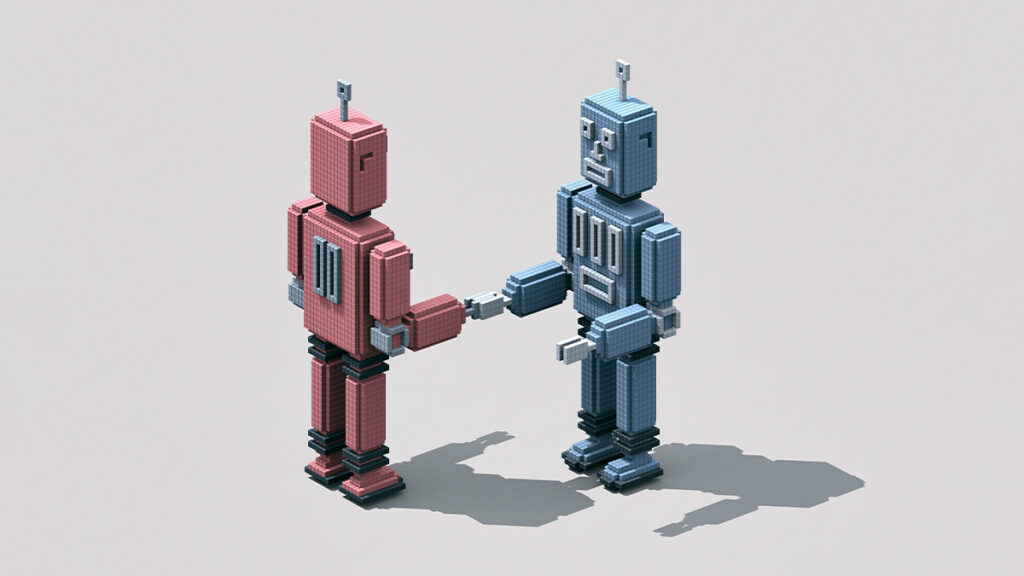
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ロボットを顧客サービスの現場で機能させるために
映画『スター・ウォーズ』シリーズに登場するキャラクターの「C-3PO」は、プロトコル(外交儀礼)に精通したロボットとして銀河戦争の最前線で活躍する。さまざまな文化圏のエチケットに詳しく、700万を超す言語を流暢に操るのだ。
このロボットアシスタントの描写は、言うまでもなく架空のものだが、現実の世界でもこれとは異なる最前線を舞台に、同じような形でロボットが人間を助け始めている。その最前線とは、顧客サービスの現場である。ヒルトンホテルの「コニー」やソフトバンクの「ペッパー」のようなロボットは、それほど高度なものではないが、ロボットが持つ言語と案内に関する能力を生かして、ホテルやレストラン、小売店で顧客体験を改善する役割を担っている。
このようなサービスロボットとやり取りした経験がまだないと思っている人もいるかもしれないが、実際にはほとんどの人が何らかの形ですでにやり取りを経験している。スーパーマーケットのセルフレジもその一例だ。新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、数年間でこの種のテクノロジーの普及が大きく加速した。店頭での人と人とのやり取りがウイルス感染の原因になったり、マスク着用をめぐって顧客とトラブルが起きたりすることへの不安が高まったためだ。
こうした状況が追い風になって、セルフレジは突然、顧客サービスの主流に躍り出た。パンデミックの不安が和らいでも、セルフレジが店頭からなくなることはないだろう。未来の顧客サービスでは、ロボットの活用が当たり前になりそうだ。
サービスロボットを活用することの恩恵は明らかだ。ウイルスの飛沫感染の原因をつくらないし、顧客のハラスメントで働き手が燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ることも避けられる。コストを削減し、効率性を改善し、骨の折れる業務を機械に任せられるようになる可能性もある。
ときどき不具合が生じたり、ソフトウェアをアップデートする必要があったりはするが、それを別にすれば、ロボットは病欠をせず、休日は不要で、有給休暇を取ることなく、1日24時間、週7日働き続ける。そのため、ホテルのフロントやレンタカー会社の店頭に、常にスタッフを配置できるようになり、顧客の利便性も向上する。
しかし、このような恩恵を現実のものにするには、サービスロボットを正しく設計し、正しく現場に投入しなくてはならない。そうでなければ、顧客や働き手がロボットと関わることを嫌がるようになる。ロボットを顧客サービスの現場で機能させるためには、具体的にはどうすればよいのか。最新の研究をもとに見てみよう。
ロボットを人間に似せて設計すべきだが、やりすぎは禁物
顧客は、顧客サービスに対して人間的な温かみと「スマイル」を期待する。そうだとすれば、サービスロボットは顧客を満足させることができるのか。
この点に関しては、愛らしい外見や感情など、人間的な要素を有するサービスロボットほど、顧客に満足感を与えられる可能性が高いことがわかっている。ただし、2022年に『インターナショナル・ジャーナル・オブ・ホスピタリティー・マネジメント』誌に発表された研究によると、人間らしいロボットが顧客の満足感を高めるのは、そのロボットが女性的で、いかにも社交的な振る舞いをする場合に限られるという。
誤解がないように指摘しておくと、「人間らしい」というのは、表情豊かな顔と、人間に似たボディーを持っているという意味ではない。実際、『スター・ウォーズ』シリーズに出てくるロボットの「R2D2」(そして最近の作品で登場した「BB-8」)は、顔も手足も声もないのに、見る人の笑いと共感を引き出す。逆に、あまりに人間らしすぎるロボットは、むしろ気持ち悪い印象を持たれて、不快感を抱かせてしまう。この現象は、「不気味の谷」という言葉で表現されている。映画『ポーラー・エクスプレス』を見たことがある人は、この点が理解できるだろう。
ロボットの外見を人間に似せることよりも重要なのは、顧客がそのロボットを感情の持ち主と感じるようにすることだ。2021年に『ジャーナル・オブ・アプライド・サイコロジー』誌に発表された研究では、日本で開業した史上初のロボット常駐型ホテルの宿泊客194人に対して、チェックアウト時に宿泊の満足度を尋ねた。半分の宿泊客には、チェックインした際に、ホテルで働くロボットを擬人化して考えるように、つまり、思考と感情を持った存在と見なすように指示しておいた。残り半分の人たちには、そのような指示は与えなかった。
この両方のグループはまったく同じサービスロボットと接したが、ロボットを人間的な存在と考えた宿泊客のほうが高い満足度を示した。その理由は、ロボットが思考を持っていると考えたことの効果というより、感情を持つ存在と考えたことの効果だった。
宿泊客は、ロボットが感情を持っていると見なした場合、そうでない場合に比べて、不手際を許す傾向も目立つ。「過つは人の性」という言葉があるように、顧客は人間らしいロボットが犯した失敗には同情的になるのかもしれない。したがって、まだ「ベータ版」の段階のサービスロボットを現場に送り出す際は、顧客が感情移入しやすいようにすることが重要だ。研修中の新人店員を見るような温かいまなざしで見守ってもらえるとよい。
旧来型のセルフレジを新しいサービスロボットに置き換えるだけでは、顧客の満足度を高めることはできない。顧客が求めているのは、感情的なつながりだからだ。しかし、完璧なパフォーマンスが求められているわけではない。人間を真似た奇妙な表情を持たせる必要もない。目的を達するためには、「ジェニファー」などといった名札を付けさせて、顧客にロボットの感情に配慮してほしいと呼び掛けるプラカードを用意するだけで十分だ。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









