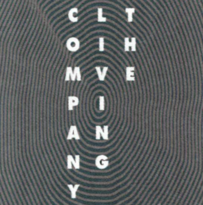政策問題に関与することは嫌かもしれないが、避けて通ることはできない
企業はもう傍観者でいることはできない。なぜなら「傍ら」など存在しないからだ。透明性の高い世界では、沈黙が多くを物語る。信頼度調査「2023年エデルマン・トラストバロメーター」では、回答者のおよそ70~90%が、気候変動、差別、貧富の格差などの問題に対して「CEOが立場を表明することを期待する」と答えている。
もちろん、前途多難ではある。しかし、ステークホルダーにとって、企業の一貫した姿勢は非常に価値がある。企業は、公平性を重視すると言っておきながら、政府が従業員や顧客の権利を抑制する動きを見せた時に、沈黙を守ることはできない。同様に、積極的な二酸化炭素削減目標を掲げておきながら、政府の排出量削減策に反対の働きかけをする(あるいは業界団体にさせる)ことは認められない。「企業の政治的責任」と一部で呼ばれるものを軸とした戦略の構築が必要となるだろう。
そこで、政治に関する重要な教訓が導き出せる。つまり、企業は、誰が味方なのかを再確認する必要がある。ある政党やその理念とつながるということは、もはや税率や業界への特別優遇措置や法律だけの問題ではない。
文化戦争が過熱するにつれ、ポピュリズムに傾倒する政治家は、あらゆる方面から企業を攻撃しやすくなった。したがって、自分の会社やセクターが、より公正でネットポジティブな(地球や社会への貢献が負荷を上回る)道を進み、二酸化炭素削減目標を達成し、弱い立場の従業員や顧客を守るために何が本当に役立つのかを見極めることである。その実現に誠意を持って協力してくれる政府関係者と連携しよう。
正しいことをする
公平で豊かな世界の実現をじゃまする政治指導者や、偏見から人々の基本的な権利を構造的に奪おうとする輩に屈してはいけない。怖いのはわかる。顧客や従業員など、企業のステークホルダーの多くが、怒りや攻撃に激しく同意している。
しかし、ご存じだろうか。おそらく彼らよりも大きな集団、特に若い顧客や従業員は、たとえ不快感を伴っても、企業が社会から取り残された人々のために立ち上がり、一貫した価値観を持つことを望んでいる。マースの新CEOであるポール・ヴァイハラウッホは、『フィナンシャル・タイムズ』紙との最近のインタビューで、ビジネス観や倫理観を明確にしている。「『ナンセンスな』政治的攻撃に直面して、社会や環境に関するコミットメントを後退させる企業は、ある世代の人材を遠ざけるリスクを冒している」
しかし、たとえどちらの集団が多数派なのかわからなくても、正しいことをすればよいのではないだろうか。このような問題の多くには、正しいことと間違っていることがはっきりとある。企業は、「好きな相手を愛する権利」を守り、女性や有色人種に平等な権利を与え、人類の共有物である気候が、人間の存在そのものを支える能力を維持できるように、戦い続けるべきである。
もちろん、その手段については、議論が可能であり、すべきである。たとえば、気候変動に対処するために、どのような政策の組み合わせや企業からのアプローチを採るのが適切なのか、といったことだ。だが、道徳的にも、経済的にも、科学的にも、行動することは正しい。そこに議論の余地はない。米国には、
主導する勇気
理不尽や不寛容に立ち向かう時は、従業員やその他のステークホルダーに、それがビジネス的にも、理念的にも、社会にとっても、受け入れられないことを示そう。勇気を奮い立たせるのである。
どのような論争もそうだが、特に意図的に仕組まれた論争には、断固とした姿勢を取る企業もあれば、一目散に逃げる企業もある。経口中絶薬をめぐる争いでは、薬局大手のウォルグリーンは、中絶薬を販売しないと言ったかと思えば、それを撤回するような不明瞭な態度を示した。この薬は、米国産科婦人科学会が安全かつ有効であると判断した合法的な医薬品である。短期的には、ウォルグリーンは共和党の政治家やある顧客層から一定の評価を得て、訴訟の危険も回避できるかもしれない。しかし、中絶は合法であるべきと主張し、
反ESGの投資家たちの戦いもまた、分断を生み出している。ブルームバーグが最近伝えたように、モルガン・スタンレーは「これまで以上に断固としてESGに取り組む」ことを選択し、2023年2月にさらに多くのファンドを立ち上げた。一方、ファンド大手のバンガードは、2050年までにポートフォリオをネットゼロカーボンに移行させるという世界的な合意から離脱した。バンガードのCEOは最近、『フィナンシャル・タイムズ』紙に「(ESG)投資が全銘柄を対象とする投資よりパフォーマンス的に優れているとはいえない」と述べた。
その主張は説得力に欠ける。特に、ESG投資が運用成績の(それも短期的な)高さを保証しなければならないと考えるのは、おかしなことだ。どのような投資テーゼ(対象カテゴリーについて立てた見通し。これに照らして個々の投資を評価する)も投資成果を保証できないし、テックやヘルスケアのような他の投資カテゴリーでも、それを求められてはいない。ESG投資はリスクを管理し、顧客を満足させることが重要なのであり、結果を保証するものではない。
一部の企業は、「グリーンハッシング」(greenhushing)と呼ばれる、もどかしい中途半端な方向に進んでいるようである。つまり、環境や社会的な取り組みを進めながらも、門限が過ぎたのちにこっそり戻ってきたティーンエイジャーのように、沈黙を守っているのである。たとえば、最新の調査では、4分の1の企業が気候変動に関する目標を公表しないと回答している。
昔からよく言われる「無駄な戦いはしない」は金言だが、戦うに値する戦いや権利はある。立場を表明すれば、自社が何を重視しているかをステークホルダーにわからせることができる。世論を動かし、支持者を増やし、批判者を黙らせることができる。無言でいると、味方を集め、集団的の勇気を高める機会を失う。
働くなら、率いるなら、誰しも勇敢な企業を望むのではないだろうか。
"Why Business Leaders Must Resist the Anti-ESG Movement," HBR.org, April 05, 2023.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)