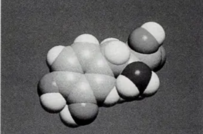武田薬品工業のシャイアー買収
日本を代表する製薬企業である武田薬品工業は、2019年にアイルランドのバイオテクノロジー企業であるシャイアーを620億ドルで買収した。報道によれば、武田は、エバコア、JPモルガン・チェース、野村ホールディングスといった、シャイアーに精通するアドバイザーを起用し、これらのアドバイザーは買収を支援した。
シャイアー側も財務アドバイザーとしてゴールドマン・サックス、シティーグループ、モルガンスタンレーを雇用した。このディールは、買収提案直前のリークによる両社の株価の変動や武田が負担した巨額の有利子負債等により困難を極めたが、同社はシャイアーの製品と事業の統合を成功させ、収益と成長機会の増加を実現した。
このディールにおいても、買収のために複数のアドバイザーを雇うことは、文化の違いに関する課題をもたらす可能性があった。シャイアーは欧州の企業であり、武田が採用したアドバイザーは、欧州の市場や規制に関する経験を十分に有しておらず、誤解や機会損失を招いた可能性がある。さらに、複数のアドバイザーが存在することで、特に言語の壁や文化の相違がある場合において、コミュニケーションに問題が生じる可能性もあった。
いずれの例も、M&Aを成功させるためには、複数のアドバイザーを雇うことが不可欠であった。しかし、買収の成功は、雇ったアドバイザーの数だけに依存するのではなく、効果的なチームワークと長期的なプランニングが重要であった。言及した事例のコンテクストにおいても、M&A案件で複数のアドバイザーを雇うに際しては、以下で示す課題と対峙する必要がある。
「料理人が多すぎるとスープが台無しになる」のか
米国の事例研究から考察する
本稿の問いは、複数のM&Aアドバイザーを起用することの功罪である。例えるならば、「料理人が多すぎるとスープが台無しになる」ことはないだろうか。
この疑問を検証するために、筆者らは日本のM&A事例に先行し、ABNアムロ銀行、エイブリィ・デニソン、DSM、フィリップスなどの多国籍企業をクライアントとして活躍する欧米の著名なM&Aアドバイザーに対してインタビューを実施した。具体的には、アレン・アンド・オーヴェリー、アトス、EY、デロイトなどの大手コンサルティングファームに対してである。
その結果から筆者らは、M&Aディールが非常に複雑である場合や、複数のステークホルダーのおのおのが代理者や助言者を必要とする場合、複数のアドバイザーを雇うことが必要かつ有用であるが、効果的なマネジメントなくしては深刻な問題を引き起こす可能性があることを確認した。
ある企業経営者は、アドバイザーは「ディールを成立させるために必要な推進力」である、と言っている。また、別のインタビューによると、「適切な方法で行えば、複数のアドバイザーが視点を加え、(全員が)最高の状態に保つことができる」と述べている。
しかし、インタビューに応じた人々は、4つの重要な理由から、「過密なM&Aの『台所』は時に災害の『レシピ』になる」ことも強調した。









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)