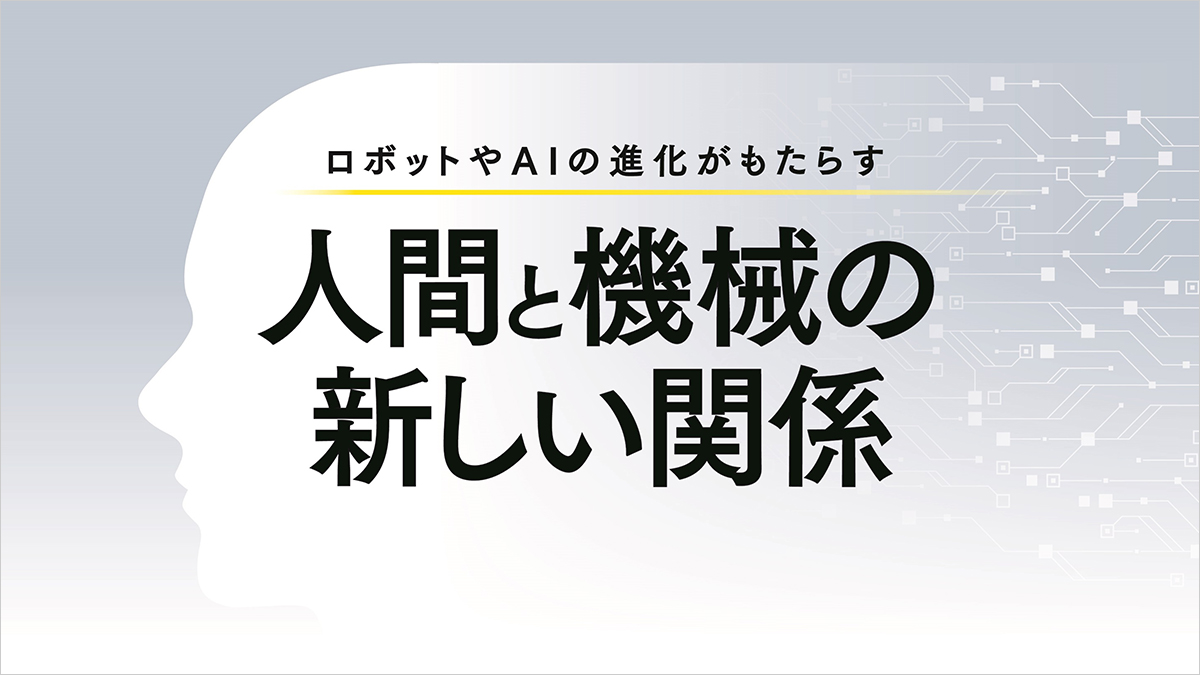
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
生成AIに必要な「プロンプト」が人間理解を促す
チャットGPTをはじめとする人工知能(AI)の進化は、人々に生産性の劇的な向上への期待と、仕事が奪われることへの不安をもたらしています。特集「人間と機械の新しい関係」では、AI・ロボットが人間や組織との関係性をどう変えるのかについて考察し、次のビジネス機会を探ります。
特集1本目は「製造現場は人とロボットの協働で進化する」です。ゼネラルモーターズの「未来の工場」が閉鎖に追い込まれた原因は、完全自動化によって生産プロセスの柔軟性を失ったことにありました。自動化による恩恵を享受しながらも、生産性と柔軟性を両立させる方法について解説します。
特集2本目は「ニューロテクノロジーを職場でどう活用するか」です。人間の脳を機械と結びつけて分析し、従業員の生産性を高める動きが加速しています。企業は、新技術の活用策だけを考えるのではなく、従業員のプライバシー保護にも努めなければなりません。
特集3本目は「デジタルヒューマンの『雇用』が企業と顧客の関係性を変える」です。人間の顔を持つAIである「デジタルヒューマン」が顧客との接点を急速に担うようになっています。企業と顧客の関係性を深めるために何が必要なのか。4つの分類を通じてその方法を説明します。
特集4本目は、東京大学大学院の松尾豊教授による論考「AIの進化が人間理解を促し、新たな事業機会を生み出す」です。チャットGPTを代表とした生成AIの進化は、「プロンプト」という指示言語を通して、人間や組織の理解を深めます。そこから、ビジネスの新たな可能性が開かれることについて、AI研究をリードする筆者が解説します。
特集最後の「自在化身体論:人と機械の新たな関係性を構築する」では、東京大学の稲見昌彦教授へ、人間拡張工学の視点から人間の持つ可能性についてインタビューしました。光学迷彩や「第6の指」など、いまSFの世界が科学の力によって現実に近づきつつあります。
AIは新たな段階に進んでいます。AI・ロボットのさらなる進化は、人間や組織との関係性の再定義を迫ります。人でしかできないことや機械に任せるべきところなど、自社のビジネスプロセスあるいは事業そのものを見直す必要性に迫られています。
たとえば、雑誌の編集業務ならばざっと、企画→寄稿・取材・翻訳依頼→記事化→編集→校正→デザイン・タイトリング→品質チェック→印刷→配送という事業プロセスをたどります。チャットGPTを代表とする大規模言語モデル(LLM)は、これまで人間中心であった上流工程を代替する力があります。そのため、我々の未来は、AIを使いこなせる「アドバンストエディター」になれるかどうかにかかっています。
このように、今特集が自社やビジネスに与える影響について考察する機会となれば幸いです。
(編集長 小島健志)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









