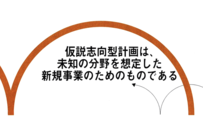2. 意思決定
奉仕に主眼を置いていると、人を喜ばせることを第一に考えるようになるが、それは実を結ばないケースが多く、終わりのない努力となってしまう。そもそも仕事の多くは、厳しい期限や難しいフィードバックなど、リーダーが何をしようと、本質的に不愉快なものである。
リーダーが、可能な限り他者の役に立とう、サポートしようという視点だけを拠り所にして意思決定を行っていると、それはバーンアウト(燃え尽き症候群)のもととなる。最悪の場合、自分たちを喜ばせることだけがリーダーの仕事だ、と従業員が思い込むような権利意識を生むことになる。このような情緒不安定が続くと、リーダーは厳しいが正しい判断を下すことができなくなる。
そうではなく、リーダーは、パーパスを軸に意思決定を行うべきである。たとえば、ミーティングでは「あなたはこれについてどう思いますか」「このやり方であなたは問題ありませんか」と尋ねるのではなく、「それを行うことによるインパクトは何ですか」「これは従業員や顧客にどのような影響をもたらすでしょうか」と尋ねるのだ。
医療機器メーカーでカスタマーサクセスの責任者を務めるキャサリンは、このモデルを使ってチームを「クレーム」から「アクション」へとシフトさせた。チームの業務の一つに、顧客への納期連絡があった。遅延がある場合には、顧客に電話で連絡をしていた。特にいらいらが募った日の終わりに、チームから「電話はもうかけたくない」との訴えがあった。「納品が遅れても気づかない顧客もいます」と泣き言を言い、他のメンバーも「配送トラックを早めることはできないのです」「電話をかけるのは無意味です」「心配なら向こうから電話してきますよ」と畳みかけてきた。
単にチームを喜ばせたいリーダーなら、電話をかけるのをやめさせるか、自分がかけることにしただろう。しかしキャサリンは、質問を使用してチームの目をより高いパーパスへ向けることができた。彼女は尋ねた。「納品が遅れることを知らなかったせいで何かあったら、顧客にどのような影響があるでしょうか」「私たちが先手を打つのをやめて、後手に回ったら、私たちの評判にどのような影響があるでしょうか」
この一見、単純な視点の転換によって、チームは自分たちの仕事が組織の包括的なパーパスに与える影響について考えるようになった。彼らの思考プロセスが変わったのである。つまり、自分たち自身の反応にこだわるのではなく、チームへの影響を考え、自分たちを大きな全体の一部と見なすようになった。チームは、電話をかけ続けることに決めたが、全員が毎日かけなくて済むように、ローテーションで担当することにした。チームをより高いパーパスに向かわせると、リーダーのプレッシャーが軽減され、チームはより協力的になるのである。
3. コーチング
どのようなリーダーでも、主たる職務はチームのコーチングである。しかし、アウトプットを求められ、そのうえにコーチングも行うとなると、部下の育成に時間を割くことが難しい場合もある。
最近、筆者らがホスピタリティ業界の営業マネジャーを対象に行ったコーチングプログラムで、参加者から、仕事がキャパを超えているという声が聞かれた。この会社には非凡な組織文化があり、マネジャーは総じて、しっかりとチームを指導したいと考えている。しかし、旅行が活況になり始め、営業担当者を増員したところ、マネジャーたちに余裕がなくなってしまっていた。
マネジャーたちに「誰をコーチングしているのですか」と尋ねた。すると答えは、「成績が最も芳しくない従業員」でほぼ一致していた。しかし、コーチングにかなり時間をかけているにもかかわらず、彼らの成績はわずかでも改善すればよいほうだと嘆いていた。
そこで筆者らは、サーバントリーダーシップからノーブル・パーパス・リーダーシップへと視点を転換させた。マネジャーたちに、誰にコーチングが必要かではなく、こう自身に問うよう促した。「私がコーチングに時間を費やした場合、最も大きなインパクトをもたらすのはどこだろうか」
マネジャーたちは、別の視点からチームを見るようになった。「最もコーチングのしがいがあるのは誰か」「学習スピードが速いのは誰か」「顧客に対する責任を担っているのは誰か」
プログラム終了後、マネジャーたちは、ハイパフォーマーとミドルパフォーマーにもっと時間をかけるようになった。ハイパフォーマーには、最も価値の高い仕事に関して個人的にコーチングした。ミッドパフォーマーにもさらに注意を払い、グループコーチングサークルやピア・トゥ・ピアのロールプレー研修を実施した。ローパフォーマーへのコーチングを放棄したわけではないが、コーチングを何時間も割く代わりに、オンデマンドコースやセルフスタディなどの自主学習に誘導した。
成果はすぐに表れた。ハイパフォーマーはさらに業績を高め、ミドルパフォーマーも向上した。さらに興味深いのは、ローパフォーマーが次の3つのうちのどれかを行ったことである。
・努力してミドルパフォーマーになった。
・マネジャーのコーチング時間をほぼ独占していた時と変わらず、わずかに改善した。
・自身の成長に責任を持つという課題を突きつけられると、みずから辞退した。向上心のない従業員の指導に何時間も費やすよりも、プロセスとして早く、フラストレーションも少なかった。
全体として、チームは記録的な収益を上げ、充実感も高まった。
サーバントリーダーシップは、私たちに人間中心の思いやりのある職場環境をもたらした。いまこそ次の飛躍を遂げる時である。現在の環境では、燃え尽きたリーダーが際限なく奉仕しようとすると、将来の成長に必要なイノベーション、レジリエンス、存在意義の感覚を牽引することが難しくなる。
ノーブル・パーパス・リーダーシップへと視点を高めることは、従業員とマネジャーが一致団結して変革を起こす力を得ることである。
"How to Be a Purpose-Driven Leader Without Burning Out," HBR.org, July 26, 2023.








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)