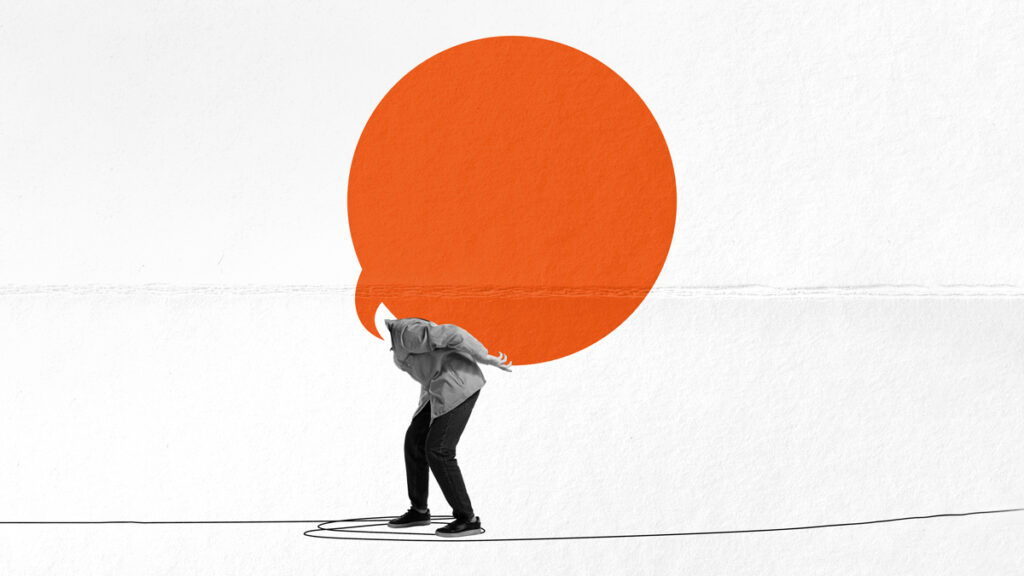
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ツールの増加で増えるコミュニケーション
一般的な労働者は1日にメールを77回チェックし、121件の新規メールを受信する。同時に、多くの人は複数のアプリケーションを切り換えながら、スラックやチームズといったアプリの更新通知、共有ドキュメントのコメント、さまざまな企業のポータルサイトからの通知などの間を行ったり来たりしている。
したがって今日の労働者が、断片的で予測不能かつ圧倒的な数のコラボレーションツールを前に、呆然としているのも無理はない。生産性向上を謳うツールそのものによって、がんじがらめにされているのだ。人々は負担が重すぎることを自覚して疲労を感じているが、押し寄せるコミュニケーションの勢いを減らすためにできることはほぼ何もないと思い込んでいる。
筆者らは、コラボレーションテクノロジーの肥大化が従業員に及ぼす影響を調べ、自分の仕事をコントロールできるよう支援する試みを実施し、この介入を「コラボレーションの浄化」と名づけた。本稿では研究結果(よい結果も悪い結果もある)について考察し、従業員のコラボレーションツールの使用を簡素化するためにリーダーは何をすべきかを概説する。
コラボレーションの浄化
「浄化」はアサナのワーク・イノベーション・ラボとアマゾン ウェブ サービスの協働により実施された。アサナとアマゾン双方の従業員で構成される58名のボランティアを、筆者らは2つのグループのいずれかにランダムで割り振った。
まずは参加者全員に、同僚とのやり取りで週に1回以上使うコラボレーションツール、例えばスラック、フィグマ、ズームなどについて報告してもらった。さらに、現在の仕事の目標を達成するうえで各ツールがどれほど貢献しているのか、そして各ツールの使用にどれほどの労力を費やしているのかについて評価するよう依頼した。
最後に、2週間にわたり使用を控える特定のテクノロジーを選んでもらった。第1のグループには、コラボレーションツールのうち半数の使用を2週間停止するよう依頼した。第2のグループは、排除するツールの種類と個数を自分で選んでよいものとした。参加者は全員、どのテクノロジーを排除するかに関する計画を筆者らに報告し、毎日日記をつけ、「承認済み」のリストにないツールを使ってしまった場合にはそのつど記録した。
この浄化は、引き算志向に関する研究から着想を得たものだ。その中には筆者らが以前にワーク・イノベーション・ラボで実施した、無駄な会議の排除と再設計を後押しするための介入も含まれる。
この研究は、人が問題解決に取り組む時の傾向として、より多くの複雑さと負担を自分と他者に課してしまうことを明らかにした。引き算のほうが効果的な戦略である場合でも、である。仕事から排除できるもの、排除すべきものについて落ち着いて考えるよう人々を促すことで、引かずに足したくなる衝動を克服する後押しができる。
よい結果:参加者はデジタルの負担に対する意識を高めた
両グループの参加者たちは浄化を始めると、自分の生活に充満しているデジタルクラッター(管理されずにため込まれるデジタルデータ)について、より強く意識するようになった。これまでほとんど考えもせず、削減や排除を試みることもなかった不要物だ。参加者の41%は、コラボレーションツールを多く使いすぎることが集中力と生産性に及ぼす影響について、より意識するようになったと自主的に報告した。
ある研究員は次のように述べた。「浄化によって自分が使っているさまざまなツールについて、そしてそれらが自分の生産性と集中力に及ぼしている影響について、より強く意識するようになりました。ツール間の行き来にはわずかながら負担が伴い、そこから生じる摩擦が集中力と生産性を阻害するのです」
参加者はツールの使い方についてより深く考えるようになっただけでなく、使用するコラボレーションツールの量を全体的に減らすために小さな一歩を踏み出した。参加者の過半数(53%)は、浄化を経て少なくとも一つのツールの使用頻度を減らすつもりだと答えた。技術スタック、すなわち組み合わされたソフトウェアツールの意識的な削減によって、より集中して仕事をするための時間と認知処理能力が解放されることを彼らは期待している。
ある顧客インサイトアナリストは、仕事を中断される回数を減らすために、注意が散漫になってしまいやすいメッセージプラットフォームなど一部のコラボレーションツールを使うタイミングについて、より慎重に考えることを浄化から学んだという。彼女が実践した変更の一つは、コラボレーションツールを集中的に使う時間を計画し、朝に10分、昼食後に10分、一日の終わりに10分とし、それ以外の時間はまったく使わないようにすることだった。
悪い結果:参加者は浄化の後、無力感と疲労感を強めた
介入による意外なマイナスの結果もいくつか見られた。参加者はツールの使い方についてより意識的になるよう筆者らに促された後、無力感が強まったと報告した。
減らすべきデジタルツールを見極めようと立ち止まって考えた時、多くの人はそれが時間のかかる苦行であること、または完全に不可能であることに気づいた。なぜなら、チームの内外で非常に多くの人々が参加者に特定のコラボレーションツールを使うよう期待、または要求しているため、その共有ツールを排除するという決断は当人だけの問題ではない、あるいはまったくの問題外であったからだ。
コラボレーションの浄化に誘発された意識によって、彼らは自分のツールに抵抗して見直しを図りたいと思うようになった。ところが多くの参加者は、逃れられないルールや伝統や力学によって、そうすることを阻まれていると感じたのだ。
たとえば、プロジェクトのリスク管理を担当する某マネジャーは、使用するコラボレーションツールを最小限に抑えようと試みても、成功するとは思えなかったと述べた。さまざまなチームが、自分たちの好みや会社の要求に基づいてさまざまなツールを使っている。このため彼女と同僚たちは、ほかの事業部の人々と意思疎通を行う際に、どのメッセージツールを使うべきか混乱することがたびたびあったという。
どちらのグループの参加者も、無力感とその結果生じる疲労を報告したが、ツールの半数を2週間使わないよう求められた第1のグループのほうが、影響はより深刻であるように見受けられた。この取り組みは困難なだけでなく、往々にして不可能であることが立証された形だ。参加者の多くは、ツールの使用を望み通りに減らす方法がないことに気づき、いら立ちと疲労感を覚えたのである。
コラボレーションツールのリストから必要に応じて何個でも柔軟に減らしてよいとされた第2グループの参加者も、徒労感とデジタル疲労を報告したが、苦痛の度合いはより低いように思われた。ツールを減らす取り組みは複雑かつ困難であり、その達成に向けた苦労を意識することで、図らずも無力感が増幅しうることが判明した。
これは、筆者らがさまざまな業界に属する63名の知識労働者にインタビューを実施した関連調査の結果とも一致する。どのツールを使うかを決める自由裁量が自分にあると従業員が感じているか否かによって、デジタル疲労の感じ方は異なることが判明している。
結論として、従業員は使用するコラボレーションツールの削減、または使うタイミングと頻度に関して打てる手がほぼ何もないことに気づくと、よりいっそうの無力感と疲労を感じるのだ。
あるソフトウェアエンジニアは、「これは個人のレベルで変えるのが非常に難しいことです」と述べた。ほかの同僚たちが使っているツールを自分が使わないと決めた場合、自分も同僚たちも仕事がやりにくくなるという。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









