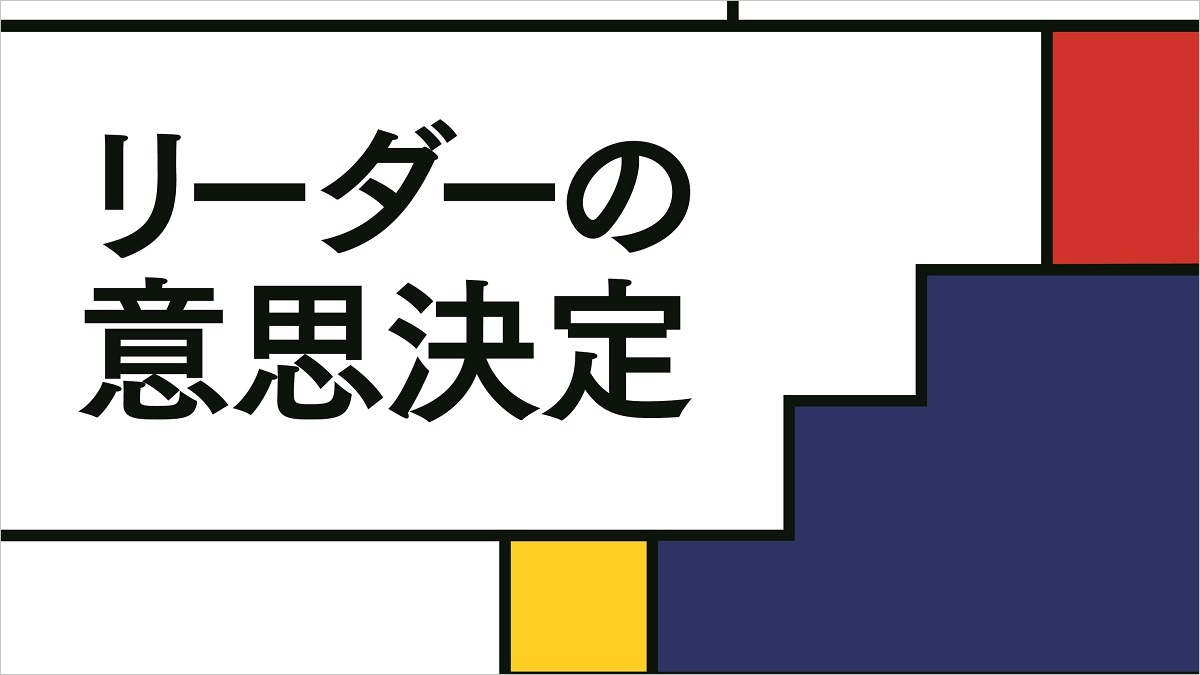
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
リーダーとは「決める」人
マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社で採用マネージャーなどを務めておられた伊賀泰代さんは、その著書『採用基準』の中で、リーダーがなすべきタスクとして4つを挙げています。その4つとは、(1)目標を掲げる、(2)先頭を走る、(3)決める、(4)伝える。リーダーとはリードする人ですから、(1)と(2)に関しては連想が働きやすいでしょう。(4)に関しても、人々に変革の必要性を理解してもらい、望む方向へ進んでもらわなければ事は成しえないことから、伝えることがリーダーの大切な仕事だと納得しやすいはずです。
では(3)「決める」についてはどうでしょうか。現在のように、ビジネス環境が刻々と変化する中にあって、こうだと的確な意思決定を下すのは容易なことではありません。特に、同じ社会、同じ組織の中にいくつもの価値観がせめぎ合い、それぞれの主張にもそれなりの理があるとなればなおさらです。しかし、そこで判断を保留していては、リーダーは務まらないのです。
こうした問題意識から、今号は異なる切り口から意思決定について考えた2つの特集をお届けします。特集1は「リーダーの意思決定」。1本目「痛みを伴う決断を下すことこそ、リーダーの仕事である」では、元ソニー社長兼CEOの平井一夫氏に、難しい選択を迫られた時のリーダーの意思決定について聞きました。
2本目「戦略的意思決定に欠かせない質問力を高める」は、意思決定の際に問うべき「質問」に注目します。よりよい意思決定には、よりよい問いを立てる力が物を言うことに気付かされる内容です。
続く3本目「データドリブンな意思決定はどこで道を間違うか」では、リーダーが意思決定のためにデータや調査結果を用いようとして陥りがちな5つの落とし穴を指摘します。また4本目「ベンチャーキャピタルに学ぶ意思決定の手法」では視点を変えて、有望なスタートアップを早期の段階から見抜くことに長けたベンチャーキャピタルから、適切な意思決定のヒントを探ります。
そして5本目に掲載するピーター F. ドラッカーの「意思決定の秘訣」は、半世紀以上も前に書かれたとは思えない本質を突いた内容で、リーダーが意思決定をする際に必ず立ち返りたい6つの手順が示されています。
特集2「分断の時代の企業倫理」についても読みどころをご紹介しましょう。ここに集めた3本からは、異なる価値観同士が相克するいまの時代に、言わば白でも黒でもない領域でリーダーが適切な判断を下すための手がかりを探ります。1本目「組織に『倫理』という判断軸をどう組み込むか」は、倫理哲学者のデイビッド・ロディン氏に聞いた、組織文化に倫理という判断軸を根づかせる方法論は、これからの時代に舵取りをするリーダーに重要な示唆を与えてくれるはずです。
2本目「分断の時代に企業が適切に発言する方法」では、社会課題に対して沈黙を保ったり無難な言葉でやり過ごしたりするほうがリスクになる昨今の状況を踏まえ、企業が取るべき「発言戦略」について論じます。
3本目「経営者は従業員アクティビズムとどのように向き合うべきか」は、社会課題の解決に我が社も貢献せよと声を上げる従業員に対し、企業リーダーはどのように対応すべきかを考えます。
よりよい意思決定につなげるために、今号のDHBRをぜひお役立てください。
(編集長 常盤亜由子)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









