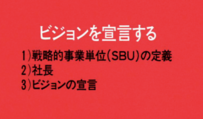-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
実力主義とインクルージョンは二項対立ではない
筆者は、実力の重要性を信じている。
だからこそ、筆者はインクルージョン(包摂性)を推進している。
一見、矛盾しているように思えるかもしれないが、そうではない。筆者が真に求めているのは公正さであり、人間は本質的にそれを求める傾向がある。実力主義の理想もインクルージョンの理想も、公正さを目指している。すなわち、誰かの気まぐれといった恣意的な障壁ではなく、本人の努力と能力が職場での成功を決定づけるシステムである。しかし、現実の世界は理想とは程遠く、この目標はまだ達成されていない。筆者がニューロダイバーシティ(脳神経科学的な多様性)と障害に関する国際的な活動の中で出会ってきた多くの事例が、それを示している。
たとえば、ブライアンを考えてみよう。ブライアンは非常に優秀である。コンピューターサイエンスと数学の二重専攻を3年で修了し、パターン認識テストでは、従来不可能と考えられていた成績を記録した。彼はサイバーセキュリティの職に情熱を注いでおり、その職務に理想的な資質を持っているように見える。それでも、仕事に就くことができない。なぜか。典型的な面接形式、すなわち「自分を動物に例えると何か」や「ゴルフとテニスのどちらが好きか」といった「奇妙な」質問が次々と出される形式では、彼はふるい落とされてしまう。スキルや能力が足りないわけではない。むしろ問題は、面接を過度に重視する採用プロセスにある。候補者に自閉症がある場合、とりわけ妥当性を欠くプロセスだ。
もし採用基準が、現実に職務を遂行する実力に焦点を当られていたならば、ブライアンをはじめとする多くのスキルと才能を持つ求職者は、最有力候補になっていただろう。だが、面接というのは実のところ、コーディングや会計、棚詰めといった実務的なスキルではなく、演技力を測定している。したがって、面接に依存する採用手法は、直接的なスキル評価よりも一般的に妥当性が低く、実際に仕事をこなす能力に優れている人にとって、とりわけ不公平で差別的なものとなっている。
評価基準に妥当性が欠けている時、最適な候補者を選ぶ行為は実力を反映するものではない。反映されるのは、バイアス、障壁、そしてインクルージョンの欠如である。真に優れた人材を選んでいるのではなく、公平な競争環境の一部に偶然存在できている限られた集団の中から、「何となく優秀そうな」人材を選んでいるにすぎない。驚くべき才能を示しているにもかかわらず、階級、非英語的な名前、ジェンダー、年齢、人種、外見、障害などに起因するバイアスのために不利な立場に置かれ、傾斜の激しい競争の坂道に追いやられている人々は選ばれない。
組織の成長に貢献する才能やスキルを持つ人々が、インターンシップから昇進、報酬に至るまで、日常的に排除や障壁に直面し、その力を発揮できないことが多い。実際、研究によれば、昇進や報酬の分配におけるバイアスは採用におけるバイアスと同様に広く存在しており、キャリア全体を通じて不公平を是正するどころか、むしろ助長し、増幅させている。
UXデザイナーとして受賞歴のあるケイトリンは、こうした障壁の現実を身をもって知っている。26歳の時、飲酒運転の車に衝突され、顔面マヒと言語障害を負った。話し方や外見はケイトリンのデザイン能力とはまったく関係がないにもかかわらず、彼女の採用面接は、人間あるいは人間のバイアスを学習したAIによるものであり、不採用という結果に終わる。フリーランサーとしても、大幅な割引料金で働くことを当然のように期待される。あるクライアントが「あのような顔を雇う人などいないだろう」と発言するのを、ケイトリンは実際に耳にしている。
次に紹介するソフィアは、トップクラスのデータアナリストであり、予測分析を導入することでサプライチェーンのコストを削減し、業務を効率化することで会社に数百万ドルの利益をもたらした。それほどの実績を上げているにもかかわらず、「新しいエネルギーが必要だ」との理由で昇進を繰り返し見送られ、そのうえ新任マネジャーの指導役をソフィアが任されるのである。56歳という年齢に対する偏見の前では、ソフィアの実力は正当に評価されないのである。
実力の尺度が包摂的でなく、その定義そのものが誤って理解されている限り、公正という理念は常に手の届かないままである。
実力とインクルージョンの間違った二分法
英国の社会学者マイケル・ヤングは、1958年に刊行された著書『メリトクラシー』において、「メリトクラシー」(meritocracy:実力主義)という語を生み出したことで知られるが、この作品が、2034年に書かれたという設定の架空の社会学論文であり、実は陰鬱な風刺として意図されていたことを知る人は少ない。
ヤングが描いた実力主義の未来社会は、知能指数によって生物学的優越が測定され、架空の「優生院」(Eugenics House)によって監視されるという、ディストピア的な英国であった。この世界では、エリートの親たちが、自分たちの知能指数の低い新生児を、下層階級に生まれた「賢い」新生児と取り替えたり、時には誘拐したりさえしていた。
ヤングは、実力主義が極端に推し進められると、他者の苦労や苦しみ、能力を無視する自己陶酔的なエリート層を生み出すと警告した。物語の語り手もそのようなエリートの一人であり、巻末の脚注によれば、反乱を起こす能力がないと信じていた下層階級の蜂起によって命を落とす。それにもかかわらず、多くの読者は実力主義を肯定的に受け止め、一般的な用法においては、才能と努力が成功を決めるという約束を伴う理想的な考え方として広まった。
現在、実力主義という枠組みは、意図に関係なく、成功の機会が平等に存在するという神話を温存し、不平等や不公正な障壁を正当化する役割を果たしている。現実には、人が生まれた環境によって、得られる機会には大きな格差が存在する。実力の評価は、客観的な成果ではなく、バイアスや社会資本によって左右されることが多く、歴史的に疎外されてきた人々は、他の人なら見逃される過ちに対しても厳しく判断されがちである。
公正に近づくためには、実力とインクルージョンの両方が必要である。実力とインクルージョンを対立するものと捉える二項対立的な誤った認識は、個人にも組織にも害を及ぼす。インクルージョンを伴わずに実力を過度に重視する文化は、制度的な障壁を無視し、特権を才能と誤認する。
一方で、形ばかりのインクルージョンは冷笑主義を助長する。インクルージョンが基準の引き下げと見なされるようになると、すべての人が自身の才能を最大限に発揮できるよう支援するという、本来のインクルージョンの必要性が正当性を失う。さらに、組織が実力を名目に排除を行うと、イノベーションや生産性向上の機会を逃し、実力とインクルージョンの双方において公正を取り入れている競合に後れを取ることになる。
実力主義社会という理想は魅力的である。ただし、それが機能するのは、ホームレスの子どもが信託財産を持つ子どもと同等の機会を与えられ、すべてが障害者にとってアクセス可能であり、女性の貢献が軽視されない世界においてのみである。しかし、現実の世界において、すべての人が対等な条件で競争できる真の実力主義を実現するには、多くの不公正な障壁を取り除く必要がある。そのためには、インクルージョンが不可欠である。
制度的な障壁を取り除くことによって、組織は、インクルージョンが実力主義を強化し、実力主義の仕組みがインクルージョンを強化するような環境を構築することができる。それにより、才能と努力が真に成功を決定づける組織を実現できる。
実力とインクルージョンを両立させるための組織戦略
実力とインクルージョンを調和させた公正なシステムを構築するためには、意図的な設計と継続的な評価が必要である。以下に、組織が従業員の潜在能力を最大限に引き出しながら、公正を実現し、実力のインクルージョンを確保するための実践的な4つの戦略を示す。
1.職務に即したインクルーシブな評価を設計する
真の実力を評価するには、実際の職務に即した、バイアスのない評価手法が求められる。たとえば、日々の業務を直接反映したジョブシミュレーション演習(開発者向けのコーディング課題やマネジャー向けのケースシナリオなど)は、従来の面接よりも実力を的確に評価することができる。
実力に基づくシステムを構築するためには、組織は社会経済的なバイアスを排除し、文化的中立性を検証するツールを導入し、障害のある候補者にもアクセス可能な環境を整備しなければならない。採用評価ツールと昇進方法の両方は、すべての集団における長期的な業務成果を予測できるものでなければならない。ここで言う「すべての集団」には、従来は除外されており、現在の予測モデルに用いられているデータに反映されていない集団も含まれる。
2.インクルーシブな能力開発の道筋を構築する
筆者にとって職場における初期の差別経験の一つは、専門能力開発は男性にしか提供されないと言われたことであった。筆者の実力や成果はいっさい考慮されなかった。こうした実力を軽視された経験が、公正な人材開発システム(つまり実力主義的でインクルーシブでもあるシステム)を構築したいという情熱の原点となった。
真に公正なシステムでは、組織はすべての従業員の可能性を育む。すなわち、オンボーディングやネットワーキングから経営幹部育成パイプラインに至るまで、キャリア開発のあらゆる側面が、多様な人材を包摂するよう設計されていなければならない。そのためには、ソフィアのような人材をリーダー候補から外してきた狭義の「可能性」の定義を見直し、拡張する必要がある。
3.公正さをシステムに組み込む
公正さがシステムに組み込まれていると、「特別な」プログラムは不要になる。最初から歩道の段差が取り除かれていれば、後付けのスロープは不要となる。昇進および人材育成における透明性は、疑念や訴訟リスクを未然に防ぐ。人々を公正かつ倫理的に扱うことにより、障壁の発生を未然に防ぐことができる。これにより、インクルージョンが自然に機能し、透明性によって実力が明確にされる環境を構築することができる。
このように、公正さが最初から組み込みまれたシステムは、筆者が提唱する、尊厳を重視し、成功する組織のモデル「カナリア・コード」の基盤となっている。そのエビデンスに基づく原則(透明性、有効なツールの使用、成果への注目、そして組織的公正)は、実力に基づく意思決定を促進する。また、従業員の参加と柔軟性によって、個人の強みと組織目標の整合性を最大限に高めることができる。
4.モニタリング、測定、継続的改善
インクルーシブな実力主義は、継続的な評価と調整によって、公正で有効なシステムを確保する必要がある。つまり、採用、昇進、離職、業績などのデータを定期的に分析し、何らかの不均衡が生じていればそれを特定し、是正策を講じる必要がある。加えて、実力主義に基づくシステムが引き続き機能していることを確認しなければならない。
さもなければ、実力という概念は、えこひいきや縁故主義、不適切な評価手法、あるいは「自分と似た人を選ぶ」バイアスによって容易に損なわれてしまう。調査結果について透明性をもって分析し、解決に当たっては参加型のアプローチを取ることも、経営陣に対する信頼感を高めるうえで有効である。これは、政治的・対人関係的な緊張が高まる環境において協働を促進するうえで、極めて重要である。
* * *
インクルーシブな実力主義とは、あらゆる形の才能を正当に認識し、評価するためのシステムを設計することである。組織は、有効な測定方法を担保し、バイアスを排除し、みずからの競争環境がどれほど公平であるかを正直に見つめ直すことで、公正が根づく環境を真に構築することができる。
"The False Dichotomy of Merit and Inclusion," HBR.org, February 24, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)