
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
人を業務に合わせるのではなく、業務を人に合わせる
新型コロナウイルス感染症の大流行が世界中の「仕事の常識」を覆してから4年近くが経つが、まだ多くの人が新しい日常を見つけるのに苦労している。
企業は、多くの相反する要求と格闘している。一方では、インフレ傾向と経済成長の鈍化に直面して、生産性を高め、コストを抑える必要があり、株主は当期純利益しか見ていない。また一方で、企業はマイクロソフトの最高人事責任者であるキャスリーン・ホーガンが「人間のエネルギー危機」と呼ぶ問題を解決しなければならない。多くの労働者が燃え尽き、働きがいを失い、いまだにリモートワークやハイブリッドワークに慣れなかったり、オフィスへの復帰要請にうんざりしたりしている。
また、新型コロナウイルス感染の後遺症を含む、健康問題を抱える人、看護・介護を担っている人もいる。さらに、生活費の大幅な高騰にも対処しなければならない。ある調査によると、42%の従業員が「企業は自分のことを気にかけていない」と答えている。
従業員の自律性、エンゲージメント、ウェルビーイング、柔軟な働き方を守りながら、企業は経済の不確実性や成長鈍化の中で、効率性と生産性を確保することができるのだろうか。企業が労働者の脳の多様性や障害に対応し、生産性をどのように引き出せるかに関する筆者の研究は、前進する道を指し示している。それはチームメンバー一人ひとりのユニークなニーズに対応できるという道である。企業は、「包括的な柔軟性」を取り入れることで、ケースバイケースで対応するのではなく、より大きな規模でエンゲージメントとパフォーマンスの強化を図ることができる。
このアプローチはまず、真に持続可能な柔軟性とは、勤務地や勤務時間だけの問題ではないことを理解することから始まる。それは、誰がどのような業務をどのようにこなすかを包含する問題である。つまり「業務を人に合わせる」ということであり、その逆ではない。このように人、価値観、長期的成功を中心に業務をデザインすることによって、企業は生産性、レジリエンス、包摂性、公平性を実現できるのである。
柔軟性の凍結
コロナ禍で、知識労働型組織が生き残り、イノベーションを起こし、財務的に繁栄するためには、広範な柔軟性が不可欠だった。それにもかかわらず、多くの企業は皮肉なことに、いまだにそれを恒久的に採用することに難色を示している。
むしろ、個人差を軽視する古い制度や画一的な規定に立ち返ってしまった。仕事の遅い人が一人いたら、全員をマイクロマネジメントする方向に動き、セルフリーダーシップの違いや、生産性や士気への影響を考慮しない。一部の人が対面でないとやる気が出ないとなると、対面の仕事に疲弊している従業員も、足並みを揃えて出社することを求められる。
このような融通の利かない消極的なやり方では、持続可能な生産性を実現することは不可能だ。真に持続可能な状態で、生産性を追求したければ、柔軟で適応性のあるシステムをデザインする必要がある。体と心は人それぞれに異なり、企業がそれを無理やり一つのものとして扱おうとすれば、誰もベストを尽くせなくなる。
過去の例を考えてみよう。20世紀半ば、米空軍は墜落事故の多発に悩まされていた。ある1日だけで17件の事故があった。調査を行い、パイロットのミス、訓練不足、機械の故障などを除外した結果、コックピットに原因があることがわかった。1920年に設計されたコックピットは、1950年代のパイロットには窮屈で使いにくかったのである。
設計見直しプロジェクトではまず、パイロット4000人を対象に、胴の長さ、腕と脚の長さ、首周りと胸囲など、関連する10カ所の寸法を測定し、すべての平均値を割り出した。しかし、完全に平均的な体格のパイロットは存在しないため、その数値をもとにコックピットを設計しても、誰のためにもならない。
すると空軍は、それまでメーカーが不可能だと考えていたことを実行した。つまり、座席からフットペダル、ヘルメットストラップまで、あらゆるものを調節可能にしたのである。
この解決策は安価で簡単に実現でき、目を見張る成果があった。パイロットのパフォーマンスは急激に向上した。女性を含むより多くの体格のパイロットに対応できるようになったため、パイロットの多様性が高まり、才能あるパイロットが増加した。言うまでもなく、調節可能なシートはコックピットだけでなく、自動車にも標準装備されるようになった。
この「不可能」から「標準」への比較的早い移行は、2020年3月にロックダウンが起きた際のリモートワーク導入の経緯によく似ている。それを可能にするテクノロジー自体は1990年代から存在していたが、多くの企業は、2019年というごく最近まで、障害者に対する配慮としての在宅勤務を「合理性がない」として拒否していた。
ところが、コロナ禍になると、米国で在宅勤務を主とする人の数は急増し、2019年の5.7%(約900万人)から2021年には17.9%(2760万人)に上った。しかし企業はこのような、あるいはそれ以上のレベルの柔軟性にコミットしてよいものかどうか、まだ疑問視している。それは、「誰もが最高のパフォーマンスを発揮できるように、仕事の要素を調節可能にする」ことを十分深く検討してこなかったからである。
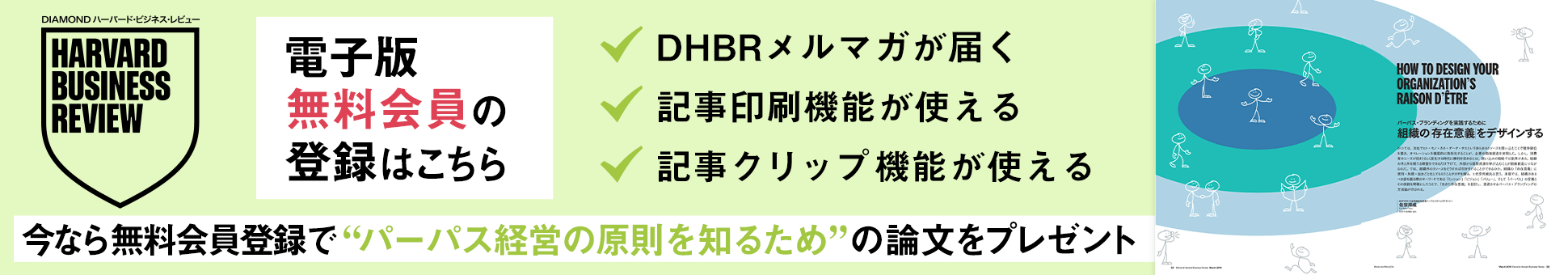





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









