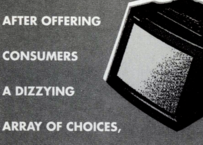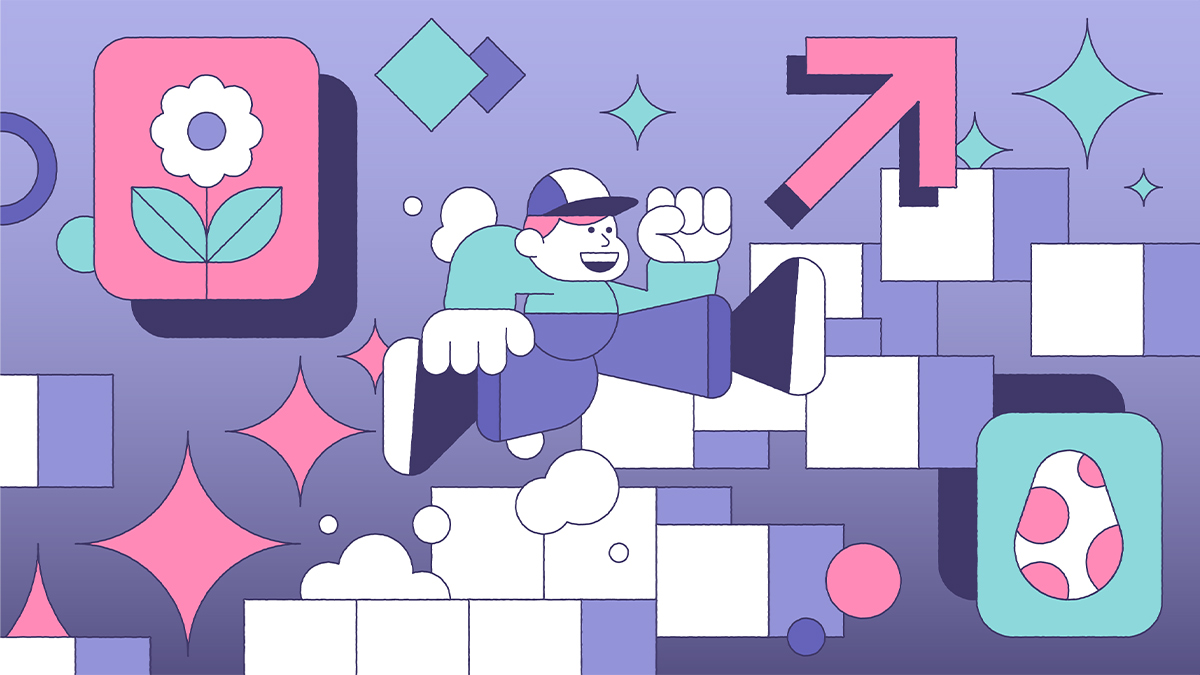
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業は「成長」以外の選択肢を検討せよ
多くの企業にとって、「毎年収益を拡大すること」は基本的な目標である。しかし、グローバリゼーションが後退し、多くの国々で人口の高齢化が進んで消費が減少し、サステナビリティへの懸念から一つひとつの購入の必要性を精査する人々が増える中、企業は成長に対する逆風に直面している。このような厳しい環境において、成長はとりわけ強力な差別化要因となりうるが、それだけにリスクも大きい。成長を何が何でも追求すれば、無駄な投資や企業の中核的な強みから資源を逸らすことによって、価値を創造するどころか、かえってそれを破壊する結果になりかねない。
そこで次の疑問が生じる。企業は、成長することなく、どのようにして持続的な価値を構築することができるのか。
安定性には特有の利点がある
筆者らはその問いに答えるため、過去20年にわたり、北米、欧州、日本の1万社以上の企業を研究してきた。その中から、同期間を通じて一貫してほぼゼロに近い収益成長だったという基準で、172社の「安定企業」を特定した。
これらの安定企業は、株主リターンが市場平均と同等でありながら、変動性は12%低かった。この低い変動性は、高いレジリエンスと長寿命の両方と相関している。筆者らが評価した20年間で、時価総額の90%以上を失う深刻な価値崩壊を経験した割合は、安定企業では平均的な企業の半分に留まった。また、安定企業の企業年齢は、典型的なS&P500のほぼ2倍で、平均して約100年に達していた。さらに、これらの安定企業のうち57社(全体の3分の1)は、総株主リターン(TSR)において市場を上回る成果を実現していた。
これらの市場を上回った57社を詳しく見ると、成功している安定企業には共通のパターンがないことが明らかになった。消費者と企業の両方を対象に販売し、商品だけでなくサービスも提供し、さまざまな業界に属している(ただし、競争が激しく、取り残される可能性がある急成長分野にはあまり参入していない)。
それでも、これらの企業には顕著な共通点がある。たとえば、安定したアウトパフォーマーの25%は、オーナーが支配権を保有していた(S&P1500企業では8%未満)。このことは、規律ある長期志向の価値創造アプローチを可能にするうえで、オーナーシップの意識が寄与している可能性を示唆している。これは、安定企業が積極的な成長に伴いがちなリスク、たとえば過度に野心的で大規模な合併・買収(失敗率70〜75%)を回避していたという観察結果と一致している。
その代わりに、これらの企業は、成長がない状況においても高いパフォーマンスを実現するために、4つの明確な戦略を用いていた。
1. 顧客志向の展開:アセットライトの戦略
低成長が見込まれる企業の多くは、高コストで新規顧客の獲得を目指すが、安定したアウトパフォーマーは既存の顧客関係からの価値最大化を図っている。これは、需要が減少している物理的商品から、アセットライトな(asset-light:資産をなるべく自社で抱えない)サービスやソフトウェアへの移行によって実現されている。このアプローチは、顧客との関係を深めるだけでなく、利益率を向上させ、資産集約度を低下させる。
このような移行を行った安定したアウトパフォーマーは、2004年から2024年の間に、資本支出を50%、売上原価を25%削減したことで、平均してEBITマージンを8パーセンテージポイント改善した。その結果、年平均で9%のTSRを達成した。
この戦略は、デジタル・トランスフォーメーションを進めているアセットヘビー型の業界や、サービス志向を強めているIT企業で特によく見られる。より広く見れば、コモディティ化や競争圧力に直面している企業にとっても、有望な選択肢となりうる。
その代表例がシーメンスである。2014年、同社はSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)とデジタルツイン技術への注力を発表した。この決定は、従来の産業コングロマリットから、デジタル産業のイノベーションリーダーへの転換を示すものであった。シーメンスは、ソフトウェアおよびデータ駆動型サービスを中核の提供価値に組み込み、よりレジリエントな収益構造と顧客との深い統合を実現した。過去10年間、この戦略を推進したシーメンスは、年率12%のTSRを達成した。
2. 高付加価値路線を取る:粗利益率重視の戦略
成熟企業はコスト削減を進める一方で、強力なブランドイメージに依存しがちである。しかし、品質を向上させることのほうが、より持続可能な価値創造の道であり、それによって容易には崩れない市場での地位を築くとともに、粗利益率の向上にもつながる。
「高付加価値路線」を取った安定したアウトパフォーマーは、20年間のサンプル期間において粗利益率を平均で12パーセンテージポイント改善した。その結果、主に粗利益率の拡大と堅調なキャッシュフローの貢献により、年平均9%のTSRを達成した。
この戦略は主に消費者向けビジネスで見られるが、製品の独自性や専門的な技術力によってニッチ市場で事業を展開する企業にとっても有効である可能性がある。代替不可能な存在となることで、これらの企業は価格決定力を高め、高級品であれ工業部品であれ、より高付加価値の市場へと進出することができる。
たとえば、英国に拠点を置くセラミックおよびカーボン材料メーカーであるモルガン・アドバンスト・マテリアルズは、航空宇宙、半導体、電気自動車といった、極限環境下での部品の高い信頼性が求められる分野の顧客ニーズに対応するため、優れた耐熱性、電気絶縁性、機械的強度を備えた製品を開発した。
筆者らの調査によれば、同社の優れた製品は価格決定力の向上をもたらし、20年間でマージンを倍増させ、年平均TSRはFTSE100を3%以上上回った。一方で、実質的な収益成長は見られなかった。
3. 内製化の強みを活かす:バランスシート重視の戦略
収益成長が見込めない状況では、バランスシートの拡大が価値創造に向けた別の選択肢となる。安定したアウトパフォーマーは、しばしば垂直統合によって資産基盤を拡大し、利益プールのより大きな部分を掌握することで、付加価値の向上を図っている。このアプローチにより、差別化された価値提案と競争優位性を強化する独自の資産ポートフォリオを構築することができる。
この戦略を採用した安定したアウトパフォーマーは、平均して垂直統合により総資産を倍増させた。バリューチェーンのより大きな部分を掌握することで、調査期間中に粗利益率を平均8%拡大した。また、これらの投資は高いリターンを生み出し、この戦略を採用した企業は平均して年率9%のTSRを達成した。そのうち5%はキャッシュフローの貢献によって実現された。
この戦略は、工業、公益事業、素材といった資産集約型のセクターで最も広く見られる。しかし、すでに差別化された製品と大きな市場シェアを持ち、サプライヤーからのコスト圧力に直面している企業にとっても、垂直統合は価値創造に向けた有力な選択肢となりうる。
ホスピタリティ業界には顕著な事例がある。多くのホテルチェーンが収益拡大を加速するためにブランドをフランチャイズ化する中、英国最大のホテルブランド「プレミア・イン」を運営するウィットブレッドは、すべてのホテルを自社で所有し、みずから運営しており、予約を独自プラットフォームに集約することで、デジタル配信と収益マネジメントも一元的に管理している。この統合戦略は急速な拡大に一定の制約を与えるが、常に高品質な顧客体験を提供し続けることは、同社の競争優位の重要な柱である。このアプローチにより、同社は過去20年間で年率10%のTSRを達成した。
4. 信頼性の高い手法:配当重視の戦略
安定した成熟企業は、積極的に成長を追求するのではなく、株主へのキャッシュ還元を優先する傾向がある。とはいえ、大幅な収益成長がなければ、増配への期待に応えることは難しく、高いTSRを達成するのは困難である。筆者らの分析では、配当による価値創造のもう一つの戦略として、配当を一貫して予測可能な形で提供することで、株式を債券のように機能させる手法が特定された。
この「債券的」アプローチでは、配当の変動性が市場平均より1標準偏差低く、投資家にとって高い安定性と低リスクを提供する。それにより、収益、マージン、配当の伸びが限定的であるにもかかわらず、市場を上回るパフォーマンスを実現した。これらの安定したアウトパフォーマーは、平均して負債資本比率を30%削減するなどにより、財務的な柔軟性を確保していた。これにより、高く安定したキャッシュフローによってTSRを支えると同時に、企業価値の評価倍率(バリュエーション・マルチプル)も年平均3%向上させた。
この戦略はあらゆる業界で見られるが、特に収益が予測可能で、投資パターンの変動が少ない企業に適している。たとえば、鉄道車両のリース会社GATXは、1919年以来、四半期配当を一度も途切れることなく支払い続けている。過去20年間、一度も減配することなく、配当の変動性もサンプル平均を1.5標準偏差下回る水準で安定していた。こうした安定性により、同社は年率12%のTSRを達成し、そのほとんどはキャッシュフローの貢献とバリュエーション・マルチプルの拡大によるものであった。
人材とイノベーション
低成長戦略の実行には、たしかに課題が伴う。第1に、成長は一般に、キャリアの進展、新たなスキルの習得など、さまざまな前進の機会を意味する。企業が積極的に成長していない場合、こうした機会は限られ、優秀な人材を惹きつけ、維持することが難しくなるおそれがある。
そのため、低成長アプローチを採用する企業は、人材戦略を戦略的に設計する必要がある。筆者らの調査対象企業の中には、安定性を活かして長期的な取り組みやパートナーシップに投資し、人材の獲得と育成を進めている企業も存在した。これらの取り組みには、ターゲットを絞った採用プログラム、専門スキルに特化した見習い制度、業界認定資格、地域の教育機関との連携などが含まれる。こうした手段は、コミュニティとの結びつきを強め、継続的な採用候補者の供給につながる。
たとえば、英国の住宅建設会社パーシモンは、地域の大学と連携して「パーシモン・アカデミー」を設立し、事業展開地域における見過ごされがちな労働市場を活用した。このプログラムにより、同社は新たな人材へのアクセスを確保し、事業ニーズに合致したスキル開発を促進し、従業員全体のエンゲージメントを強化している。この取り組みは初期の成功を受けて、現在では新たな地域へと拡大している。
人材パイプラインの確保に加え、安定企業は従業員への価値提案を見直すことで、長期的なエンゲージメントを高めることも可能である。たとえば、昇進といった縦のキャリアだけでなく、横方向の異動機会を強調することで新たな挑戦を促し、また、低成長戦略の下で変動性が低く雇用が安定していることに光を当てる。このような価値提案は、経済的に不安定な環境下でキャリアを歩んできた若年の労働者にとって、とりわけ魅力的に映るかもしれない。
米国を本拠とする食品・飲料会社、モンデリーズ・インターナショナルの社内人材市場「マッチ・アンド・グロー」では、従業員は通常の役割や職務を超えた短期プロジェクトに参加して、新たな経験を積み、さまざまなチームと協働することが可能となっている。2023年の開始以来、すでに25000人を超える従業員がこのプログラムに参加している。
一方、低成長企業が直面しうるもう一つの課題は、創造性や想像力が発揮されるイノベーティブな文化をいかに維持するかである。そうした文化がなければ、企業が現状に満足し、改善意欲が損なわれるリスクがある。しかし筆者らの調査対象となった安定企業の多くは、新市場の開拓や破壊的イノベーションを追求するのではなく、継続的かつ漸進的な改善の積み重ねによって成果を生み出すことの重要性を強調していた。
たとえば、英国の酒造会社ディアジオは、既存の製品ポートフォリオを強化するために、新興技術や新しい体験の統合に注力するイノベーションチームを立ち上げた。このチームは、ジョニーウォーカー・ブルーラベル向けに世界最軽量のウイスキーボトルを開発したほか、シードリップ・ブランドの消費者向けに、カクテルやギフトの個別提案を行うAIバーチャルコンシェルジュも開発した。
意外にも、低成長がもたらす制約は、イノベーションの強力な触媒となることがある。実際、急成長している企業の中には、創造的な問題解決を促すために、あえてリソースの使用に制限を設けている例もある。
たとえば、アウトドア用品や衣料品を手掛ける米国企業パタゴニアは、年間9%を超える成長を遂げており(そのため本稿のサンプルには含まれない)、みずからに対して商品の製造に使用する素材を制限する厳格なサステナビリティ基準を課している。オーガニックまたはリサイクル素材のみを使用し、顧客に購入点数を減らすよう促すことで、同社は修理や買い取りを含む先駆的なプログラムを展開しており、これらは同社の価値提案の中核を成している。
* * *
安定したアウトパフォーマーの戦略と成功は、成長だけが価値創造の唯一の道ではないことを示している。
とはいえ、企業のリーダーは次の点に留意すべきである。筆者らが特定した安定企業は、数十年にわたり市場を上回る成果を維持してきたが、いつかはその手段が限界に達する。マージンは100%を超えることはなく、配当の変動性もゼロを下回ることはない。安定戦略を採用したとしても、リーダーは状況の変化に応じて、成長機会を継続的に模索・再評価し続ける責任がある。
"Growth Isn't the Only Way for Companies to Create Value," HBR.org, June 03, 2025.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)