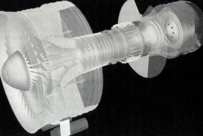-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
マネジャーの仕事に関する神話を超えて
「マネジャー」「管理職」という言葉には、近年どこかネガティブなイメージがついて回るようです。会社からは高い目標を課せられ、部下からは不満をぶつけられて板挟みに。「管理職は罰ゲーム」などという声も聞こえてきます。
しかしマネジャーとは本来、そのような存在ではないはずです。もちろん一筋縄ではいかない職務であるけれど、枝葉を払いのけたその先に浮かび上がってくるマネジャーの仕事の本質を、いまこそ見つめ直す時なのではないか。そんな思いで企画したのが、今号の特集「マネジャーという仕事」です。
特集1本目「マネジャーの仕事は『普通の創造性』を育むことである」に登場するのは、ヘンリー・ミンツバーグ教授です。ミンツバーグ教授はいまから半世紀も前に、当時主流だった「マネジャーとは計画・組織・統制を行う合理的な意思決定者である」というアンリ・ファヨール以来の静的なイメージを実証研究によって覆し、その後のマネジメント研究に大きな影響を与えた経営学の泰斗。教授は取材に対し、マネジャーはテクニックや測定に偏重せず、現場で得られる小さな気づきに着目せよと語ります。
2本目「マネジャーはビジネスの目的と結果をつなぐ存在である」は、グーグル日本法人代表の奥山信司氏に、マネジャーに求められる考え方や行動基準について聞きました。奥山氏による独自のフレームワークは、マネジャーが一段高い視座を持つうえでのヒントとなるはずです。
2本のインタビューに続いてお届けするのは、マネジャーが部下のモチベーションを高め、よりよい職場環境を築くうえで心得ておきたい2つのテーマです。特集3本目「『自分は必要とされている』と感じられる職場をどうつくるか」は、部下たちが「自分はこの組織に必要とされている」と感じられる職場づくりを実践するうえで知っておきたい「マタリング」について掘り下げています。
また、4本目「あなたが聞き上手になれない5つの理由」は、従業員と効果的な対話ができるようになるために傾聴スキルの身につけ方を解説します。
読者の皆さんがご自身の職務を見つめ直し、誇りを持って仕事に取り組んでいただくために、今号のDHBRをぜひお役立てください。
最後に、ミンツバーグ教授の古典的論文「マネジャーの職務」(DHBR2003年1月号)の一節を引いておきます。「マネジャーの職務ほど企業にとって大きな重みを持つものはない。社会が我々に仕えてくれるのか、あるいは、我々の能力や資源を浪費するのかを決定するのはマネジャーである。いまこそ、マネジャーの仕事に関する神話から脱皮する時だ」
(編集長 常盤亜由子)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)