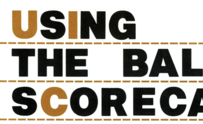なぜサムスンが地域専門家を1年間も新興国に送りこみ、最初の半年は仕事もさせずに現地の生活を観察させるのだろう。なぜ3Mが、顧客と一緒に顧客の問題解決に取り組み、顧客の視点から観察や実験を行うことを奨励しているのだろう。なぜ花王は店頭の棚の脇に立って、消費者の購買行動を観察することを社員に奨励してきたのだろう。それは、新しい勝ち筋を発見する上で、観察と実験が有効であることを知っているからである。
100パターンのプランを
検討する孫社長
ソフトバンクの孫正義社長は、戦略を実行に移す前に、少なくとも100パターンのプランを検討するといわれる。10パターンなら少し考えれば選択肢が出てくるが、100通りとなると、いま自分に見えていない選択肢を探しに行くことが求められる。
このため、新しい刺激に身をさらしつつ、無意識の世界が新しい着眼点を生み出してくれるのを待つ必要がある。こうした訓練の中から、駅前でADSLのモデムをタダで配るという着想が生まれてくるのだ。また、孫さんは「意志を持つことで脳は進化する」ともいっている。無意識の世界を活性化させることの重要さを、経験的につかんでいるといえるだろう。
現在、次世代のリーダー教育の多くは、すでに存在するフレームワーク、いわゆる定跡の教育に費やされている。これは意識の世界に着目したアプローチだ。しかし、環境が変わりゆく時代において戦略提言力を強化するためには、脳の80%を占める無意識の世界を活性化することが必要になる。そこでは、いま見えていない角度から、市場や事業を観察し続けることが重要になるだろう。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)