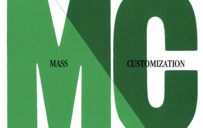「近代経営の父」と「職工の父」
「日本資本主義史上において、数少ない立派な実業家」と評価された大原孫三郎(まごさぶろう・1880~1943)は、岡山県倉敷の大地主で倉敷紡績を営む家に生まれますが、若い頃は放蕩三昧。謹慎中に、後に「児童福祉の父」「孤児の父」と称された石井十次(じゅうじ)と知り合い、彼の人生は大きく変わります。
石井の活動に感動した大原は、倉敷紡績入社後、工員の教育支援や労働環境の向上に努めるかたわら、貧民、孤児の救済や美術館の建設などの社会事業にも貢献します。大原の残した文化事業で最も有名な大原美術館は、倉敷の町を救ったともいわれています。
1932年(昭和7)、満州事変調査のために来日したリットン調査団の団員が大原美術館を訪れ、そこにエル・グレコやクロード・モネなどの名画の数々が並んでいることに仰天しました。以降、「クラシキ」の名が世界に知られるようになり、太平洋戦争下も世界的な美術品を焼いてはならないと、倉敷の町は爆撃を逃れたともいわれています。真偽の程はともかく、倉敷が空襲を免れたことは歴史的な事実です。
社会・労働問題の解決を一貫して提唱した近代経済学者福田徳三は、労働問題に関する経営者の姿勢を批判していますが、大原だけは例外として評価しています。また、福田とは対極的な立場のマルクス経済学者の大内兵衛(ひょうえ)も、「金を儲けることにおいて大原よりも偉大な財界人はたくさんいたが、金を散ずることにおいて高く自己の目標をかかげてそれに成功した人物として日本の財界人でこのくらい成功した人はなかった」と評しました。大原は、当時の専門家から「近代経営の父」ともいうべき高い評価を得ているのです。
実業家としては、倉敷紡績をはじめ現中国銀行、現中国電力などの社長を務め、大原財閥を築き上げ、社会事業としては、大原美術館のほかにも研究所、大病院、社会福祉施設などを現在に残し、社会や地域に多大な貢献をした大原は「企業メセナの父」とも呼ばれます。「企業メセナ」とは、企業が資金を提供して文化、芸術活動を支援することですが、この点につき作家の城山三郎は、「バブルにつれて生まれ、バブルとともに消えたメセナなどというやわなものとは、まるでちがう。(大原孫三郎の残した社会貢献は)正真正銘の力強い〝企業文化〟であった」と述べています。大原は、渋沢栄一と同様、財界人という枠を超えて「企業文化の父」と呼ぶにふさわしい文化遺産を後世に残しました。
渋沢栄一や大原孫三郎と同様に財界人という枠を超えて、日本資本主義の育成と発展に尽くした紡績業界の巨人がいます。鐘紡をわが国有数の大企業に育て上げ、「紡績王」「鐘紡中興の租」といわれた武藤山治(むとうさんじ・1867~1934)です。
 武藤山治(1867~1934)
武藤山治(1867~1934)
慶応義塾で福沢諭吉に直接の薫陶を受けた武藤は、アメリカ留学などを経て、経営の悪化していた鐘淵紡績の再建に努めます。明治20年代に起きた職工争奪問題では、職工がよりよい賃金を求め工場移動をする自由意志を認めるなど、当時過酷極まりないといわれていた職工の優遇を唱え実行した武藤は「職工の父」と称されました。後に1919年(大正8)にワシントンで開催された第一回国際労働会議に資本家代表として推薦されるほど、武藤は労働者から絶大な信頼を得た経営者でした。
武藤は、近代的な経営手法と家族主義に基づき、女子工員らの悲惨な労働環境を改善し、工場の近代化や従業員の福利厚生の向上を図り、寮や保養施設、娯楽場、女学校まで完備した鐘紡は模範工場として「女工の天国」と評されるまでになります。また、日本初の共済組合設置、注意箱(投書箱)の設置と雑誌の発行により社内のコミュニケーションを改善するなど、当時の紡績工場で働く女工たちの過酷な生活が克明に記録されたことで知られる細井和喜蔵(わきぞう)著の『女工哀史』ですら、武藤率いる鐘紡に対する賞嘆の声が随所に見られるほどです。
ヒューマニズムに基づく「家族主義」「温情主義」で従業員を優遇し、人道的な労務管理を実践した武藤は「日本の労務管理の父」ともいうべき稀有な経営者でした。
後に武藤は、政界に進出し衆議院議員を三期務め、1932年(昭和7)、時事新報社社長として、帝人事件で政財界の腐敗を糾弾中、凶弾に倒れました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)