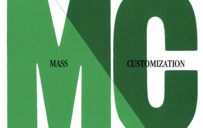明治工業の父――西村勝三
文明開化によって、日本人の衣服や履物にも洋風化の波が押し寄せます。この時、洋靴を普及させ、靴業の祖といわれたのが西村勝三(かつぞう・1836~1907)です。
佐倉藩(現千葉県佐倉市)側用人の三男に生まれた西村は、支藩の佐野藩(現栃木県佐野市)に仕えますが脱藩し、実業を志します。当初は鉄砲弾薬の販売で巨利を得ますが、外国米の輸入、米相場、雑貨販売、洋服裁縫店、陶器販売など多数の事業に手を広げ、大部分は失敗に終わります。転機は維新後にやって来ました。軍隊を近代化するうえで靴の国産化が急務となり、西村は軍靴製造で商機をとらえるのです。1870年(明治3)西村が東京・築地に日本初の製靴工場をつくった日にちなんで、現在3月15日は「靴の記念日」として靴業界でたたえられています。
西村は製靴業の祖としてその名を残しましたが、実はそれ以上の大きな功績を残しています。文明開化の象徴ともいうべき白煉瓦や硝子の製造です。
1875年(明治8)に品川白煉瓦(現品川リフラクトリーズ)を設立し、耐火レンガや赤レンガを製造、有名な「東京駅の赤レンガ」の全量を納入しているのです。さらに、ドイツの技術を取り入れた洋式硝子工場を創設し、1888年(明治21)にはビール瓶の大量生産に成功するほか、ガス、メリヤスなど数多くの事業を興しています。西村が「明治の工業の父」と称されるゆえんです。
文明開化を象徴した「たばこの父」
世俗や人々の生活習慣を大きく変えたという点で、たばこは文明開化を象徴するものの一つです。刻みたばこを煙管(キセル)で吸っていた日本人の間に、西洋人の吸うシガレット(紙巻たばこ)が瞬く間に広がり、やがて国産化が始まります。特に1884年(明治17)に発売された「天狗煙草」は、覚えやすいネーミングと口付の吸いやすさ、舶来品の半値という価格で庶民の支持を受け爆発的に売れました。販売したのは、岩谷松平(いわ やまつへい・1849~1920)です。
 岩谷松平(1849~1920)
岩谷松平(1849~1920)
薩摩藩の商家の次男に生まれた岩谷は、西南戦争後上京し、銀座(現松屋周辺)に呉服反物を扱う薩摩屋(後の岩谷商会)を開店します。派手な新聞広告で大きく売上げを伸ばすと、郷里薩摩の物産の一手販売元となり、薩摩絣、泡盛、鰹節のほか、故郷国分(こくぶ)の葉たばこなどを扱い、商社として急成長を遂げます。
明治30年代になると、外国たばこ会社の資本を背景に京都の村井吉兵衛がアメリカ葉を使った「ヒーロー」を発売しますが、これに対し岩谷は、「愛国天狗」「輸入退治天狗」などを発売します。両者はたばこが専売制になる1904年(明治37)まで「明治たばこ宣伝合戦」といわれた激しい対決を繰り広げ、たばこ産業の大立者として共に「明治のたばこ王」と呼ばれました。
岩谷が「父」としてその名を後世に残すのは、卓抜した広告センスによるものです。村井との壮絶な宣伝合戦で、「勿驚(おどろくなかれ)税金三百万円」「国益の親玉・東洋煙草大王」と大書した看板のほか、引札、新聞広告などを駆使し、以降の宣伝広告のあり方、さらには印刷技術の発展にも大きな影響を与えたことから、彼は「近代日本のPRの父」と呼ばれます。
岩谷は、赤マントに赤い足袋で赤い馬車を乗り回し、「大安売りの大隊長」と名乗って大声で宣伝して回り、人々の度肝を抜いたといいます。銀座本店も屋根から柱・壁までを真っ赤に塗り、店頭にはいくつもの大天狗面を掲げていました。日清戦争の勝利を祝う宮中の宴に招かれた時も全身真っ赤な装いで参内したため、明治天皇が「あれは何者か」と周囲に尋ねたそうです。これを聞いた岩谷は大喜びして、以後広告には「商一位大薫位功爵国益大妙人、岩谷松平」と記載しました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)