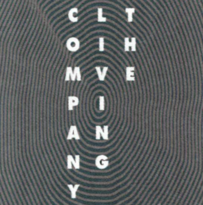郷土に残り、二つの偉業を遂げた柏木幸助
その紙巻たばこに欠かせないのがマッチです。明治初年、初めてマッチが輸入されると、たばこと同じく、全国に流行し国産化を志す人物が現れます。「わが国マッチ業の父」と称される清水誠(1846~1899)です。
金沢藩出身の清水は、1870年(明治3)に渡仏してパリ工芸大学で造船学を専攻します。1874年(明治7)、パリ滞在中の宮内少輔吉井友実(ともざね)から、貿易不均衡を解消するにはマッチの国産が必要と聞いて、二年後に帰国すると新燧(しんすい)社を設立、わが国初のマッチ製造工場(現東京都墨田区江東橋)で国産マッチの製造を開始します。製法を広めたこともあり、数年後には輸入マッチをほぼ駆逐し、国産マッチは主力輸出産業となり、日本はスウェーデン、アメリカと並ぶ世界3大マッチ生産国となりました。
国産マッチの製造では、もう一人、「父」と呼ばれた人物がいます。「安全マッチ」を製造し、中国にも進出するなどの成功を収めた、長州藩三田尻(現山口県防府市)出身の柏木幸助(1856~1923)です。
代々薬商を営む家に生まれた柏木は、少年時から化学に興味を持ち、清水とほぼ同時期に化学を応用したマッチ製造で事業を成功させました。しかし、工場が全焼したためマッチづくりを断念したところ、生家にあった寒暖計にヒントを得て医療用の体温計の製造を志します。独学と実験を積み重ねた末、ついに1883年(明治16)、水銀体温計の実用化に成功、「柏木体温計」を完成させました。外国製に比べて安く、手に入りやすいことから、柏木体温計は全国に普及します。第一次世界大戦後は国内市場を独占し、また諸外国に輸出もされ、1959年(昭和34)まで生産が続けられました。
柏木は、いまも郷里の人々から尊敬され、「水銀体温計の父」と称されています。郷里の誇りとして語り継がれる理由は、独学と実験の積み重ねという地道な努力によって偉大な発明をしたことはもちろんですが、それ以上に、この時代の化学者や発明家には珍しく(ほかに例がないといえるかもしれません)、柏木が東京や海外に出ることなく、終生三田尻にあって研究に没頭したことが大きいといえるでしょう。
(つづく)
「文明開化の父(1)」6人の墓所
本木昌造墓所(大光寺・長崎県長崎市鍛冶屋町)
浜田彦蔵墓所(青山霊園外人墓地・東京都港区南青山)
西村勝三墓所(東海寺・東京都品川区北品川)
岩谷松平墓所(梅窓院・東京都港区南青山)
清水誠墓所(玉泉寺・石川県金沢市野町)
柏木幸助墓所(光妙寺・山口県防府市東三田尻)
※タイトル写真出所:国立国会図書館ホームページ
浜田彦蔵写真出所:三省堂「画報日本近代の歴史2」、杉山彦三郎写真出所:静岡市杉山酒店
岩谷松平写真出所:たばこと塩の博物館





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)