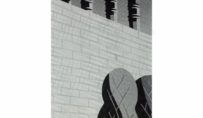遊びの存在
最後に、前回の連載において「アリ」のコミュニティを事例にとって、余りに効率化した「無駄ゼロ」の組織では、イノベーションは発現しにくいということを説明した。これはいわゆる「トリックスター」の問題である。
神話学や民族学にはトリックスターという言葉があることをご存じだろうか?トリックスターとは、神や自然界の秩序を破り、物語を引っかき回すいたずら好きとして描かれる人物のことである。もともとはポール・ラディンがインディアン民話の研究から命名した類型だが、後にユングの『元型論』で「トリックスター元型」として、人間の超個人的性格類型として取り上げられた概念である。
簡単に言えば、ハリウッド映画に出てくる「普段は困りものだが、緊急時に組織を救うことになる」キャラクター、例えば「ダイハード」のマクリーン刑事などが典型例である。現在の組織はいわゆる近代経営学の悪しき影響もあって、プロセス重視型の組織、効率重視型の組織が「あるべき組織」の典型例の様に言われているが、過去において大きなイノベーションを成し遂げた組織を見てみると、意識的に「遊び」が組み込まれていることが多い。
例えば有名なところでは3M社の「業務時間の15%を自分の好きな研究に投下してよい」とする15%ルールは有名だし、同様のルールを持っているイノベーティブな企業はグーグルやP&Gをはじめとして枚挙にいとまがない。また、15%ルールの様な「業務時間の遊び」に加えて、例えばホンダの二足歩行ロボット「アシモ」の様な、「イニシアチブの遊び」が、結果的にはセンサなどの開発に大きな貢献をしたことも知られている。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)