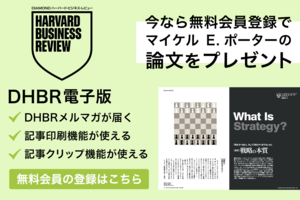最後のプレゼンターとなった児玉氏は大学時代をアメリカで過ごし、三菱商事に入社後ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得、2011年に独立され、グローバル人材の育成を目指すグローバルアストロラインズを設立されました。児玉さんはハーバード留学中の夏休みに、ジャンクフードの全米調理大会に出場し優勝されたたお話は弊社刊行の著書『パンツを脱ぐ勇気』で紹介されています。また昨年末に大和書房様から刊行されました『ハーバード流宴会術』では、宴会術を通したコミュニケーションの極意について書かれています。
さすがというべきか、児玉氏は会場を笑いで沸かせてくださいました。高校時代、米留学、MBA取得時のことなどに触れ、今後グローバルに活躍してゆくために必要な心構えを話さます。自身の小さなプライドを脱ぎ捨て、自分の弱いところ恥ずかしいところをさらけ出す。素の自分、自分の情熱を苦もなくさらけだすことで、重い扉が開いていったと語れました。
まったく違う経験、個性をお持ちの3名パネリストの方々ですが、今後求められる「グローバルな人材」について、途上国を視野に入れること、海外に出て行く際、自分の考えをしっかりと持つことの重要性など、共通する点が多く見られました。
プレゼン後、まず会場からの質問を受け、それらの質問を元にパネルディスカッションがスタートしました。進行役は、本誌編集長の岩佐です。
参加者からの質問は「グローバル化の本音と建前」「カリスマ性を持った人は今後現れるか」「外に出て行くことのハードルは?解決策は?」「海外の人はどのようにグローバル化をしていくのか」「欧米、アジアでグローバル化に対する心構えは違う?」「多文化入り交じる組織でのマネジメントのコツ」など、実に多彩です。
グローバル化とは実際どういうことなのかという質問に対し、小沼氏は現在の日本社会では「グローバル人材」という言葉のみが先行し、その具体的な中身は、ほとんどの企業が定義づけられていないのが現状」と指摘。
続いて児玉氏は、留学に臨む時、何より必要なのは「日本の文化を熟知することより、ありのままの自分をさらけだすこと」と自身の留学の原体験を説得力たっぷりに語られます。
これを受け、倉本氏は、今後日本や先進国が直面するであろう、避けられない経済構造の転換を見据え、「日本政府がグローバル化を進めるのは、このまま行くと単純に食えなくなるから」ときっぱり。さらに従来のアメリカ型、先進国型のグローバル化だけでなく、今後確実に世界経済で力をつける途上国に合わせたグローバル化が必要なこと、そしてアジア圏ではいまだ“欧米に習おう”という意識が強固だという問題点も指摘されました。