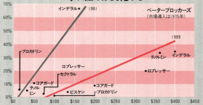限界の問題
本書では企業の境界の性質について考察し、それらを経営上・管理上の活動という観点から定義づけてきた。このように定義した場合、企業とは1つの計画の単位であり、成長にともなって、その管理責任が拡大するのと同様に境界も拡大する。しかし、企業が境界をもつということは、われわれの考えるカテゴリーの性質に由来しているのであり、現実にそれをはっきりと「観察」できるからではない。企業の境界とは、企業を市場から区別するものである。したがってそれが「現実的」であろうとなかろうと、「存在」しなければならない。なぜなら、企業と市場という二分法は、経済学者の分析思考の重要な基盤となっているからである。
G・B・リチャードソンは、1972年という早い時期に、きわめて洞察的かつ先見的な論文のなかで、この基礎概念が経済組織の分析にとっていかに不適切かを明らかにした。彼は、企業/市場という二分法の考え方そのものに挑戦し、調整には3つの手段、すなわち、命令、協働、市場による調整があることと、企業間の連携が企業の境界を曖昧にしつつあることを指摘した。さらに彼は、現実の企業は、市場取引という海に浮かぶ島ではなく、それ自体が、直接に競合し合うライバル、特別な関係にある製品やサービスのサプライヤーおよび消費者、一般的または特定の目的のためにやはり特別な関係にある個人や組織や他企業あるいは政府さえも含む1つのネットワークの構成要素であると指摘した。彼はこのように企業をとらえることの可能性について見事な説明をし、さらに誇張的にこう問いかけている。「われわれは、協働と市場取引という両極の間をどのように識別できるだろうか」(886ページ)。
ある企業が組織された当初は、市場に対して優位をもつという議論は成り立ちうる。なぜなら、比較的小さな規模の組織においては取引コストは小さいからである。時間とともに規模が増大すると、逆のことが起きやすいかもしれない。従事する活動のタイプに違いが生まれ、それがさらに拡大して、われわれの知る巨大企業の性質に根本的な変化をもたらすほど取引コストが大きくなるかもしれない。もしそうであるとすれば、このことはいかにして起きるのだろうか。革新のプロセス、知識の増大、ビジネスマンたちの野心は、累積的でこれからも続いていく。しかし、それらはどのような結果をもたらすのか。
『企業成長の理論』で展開された議論からは次のようにいうことができる。すなわち、企業の成長率は企業内の知識の成長によって制限されるが、企業の規模は、その境界が拡大し続けてもそこに管理の効力が及ぶ限りにおいて制限されない。新古典派経済学の理論では企業は1つの組織として扱われていないため、企業規模の限界はつまるところ、既存の製品群の費用曲線の上昇または需要曲線の下降のなかにしか見出せない。相次ぐ多角化により拡張が可能という観点から、需要が必ずしも成長の制限にならないのであれば、前者だけが規模に対する限界として残ることになる。また、本書では企業内部のダイナミクスに焦点を当てるため、規模や範囲に対するリターンは一定と仮定した。つまり、いかなる規模の企業も、他のいかなる規模の企業と同じく効率的であるとの仮定である。この点について私は、主張を裏づける証拠を特に示すことなく、企業は大規模化するにともなって必然的に非効率になるわけではないと論じた(少なくとも、本書を著していた時期まではこの兆候はなかった)。規模の増大とともに、企業の経営的職能と基本的な管理組織は、加速的な成長を処理するために再編されていくものと考えられた。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)